2019年5月16日に発行された日本経済新聞紙の朝刊一面に掲載された見出し「70歳雇用 企業に努力義務」を拝読しました。
現政府は5月15日に、働くことを希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高年齢者雇用安定法改正案の骨格を発表したそうです。
そして、高齢者の雇用主となる企業に対して、その選択肢として7項目を挙げたそうです。70歳まで定年を延長するだけでなく、他企業への再就職の実現や起業支援も促すなどの対策を、企業は努力義務として取り組まなければならなくなるそうです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「70歳雇用 企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」と伝えています。
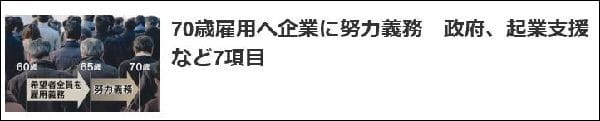
現行の高年齢者雇用安定法は、企業に希望者全員に対して65歳までの雇用を義務付けています。60際から64歳までの就業率は2018年に68.8パーセントで、2013年と比べて9.9ポイント上昇したそうです。10人に一人がまだ働き続けるという選択をしています。
今回の高年齢者雇用安定法改正案によって、65歳から70歳まで働けるようになると、60歳代の就業率が上がるとともに、その経済効果も期待できます。同時に年金を受け取り始める年齢も上昇しそうです。
内閣府の試算によると、65歳から69歳までの就業率が60歳から64歳までと同水準になれば、就業者数は217万人増えます。勤労所得は8.2兆円増加し、消費支出には4.1兆円のプラスになるとの見通しです。
政府の調査によると、は65歳から69歳までの高齢者の65パーセントの方は「仕事をしたい」と感じているそうです。その一方で、実際にはこの年齢層で就業している人の割合は46.6パーセントにとどまっているそうです。
現政府は、今回の改革によって就労を希望する高齢者が意欲的に働ける環境を整える方針です。

2018年時点での15歳から64歳までの「生産年齢人口」は、前年比51万2000人減の7545万1000人です。総人口に占める割合は59.7パーセントで、1950年以来最低となっています。要は少子高齢化が進み、働く方が大幅に減っています。
今回のこの改正案は、2020年の通常国会に提出される予定です。
日本では高齢化がどんどん進み、これからは70歳までは働く時代がやって来そうです。
現政府は5月15日に、働くことを希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高年齢者雇用安定法改正案の骨格を発表したそうです。
そして、高齢者の雇用主となる企業に対して、その選択肢として7項目を挙げたそうです。70歳まで定年を延長するだけでなく、他企業への再就職の実現や起業支援も促すなどの対策を、企業は努力義務として取り組まなければならなくなるそうです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「70歳雇用 企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」と伝えています。
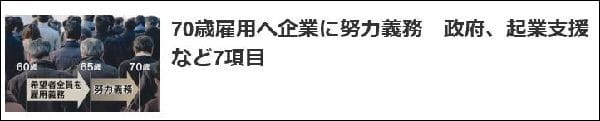
現行の高年齢者雇用安定法は、企業に希望者全員に対して65歳までの雇用を義務付けています。60際から64歳までの就業率は2018年に68.8パーセントで、2013年と比べて9.9ポイント上昇したそうです。10人に一人がまだ働き続けるという選択をしています。
今回の高年齢者雇用安定法改正案によって、65歳から70歳まで働けるようになると、60歳代の就業率が上がるとともに、その経済効果も期待できます。同時に年金を受け取り始める年齢も上昇しそうです。
内閣府の試算によると、65歳から69歳までの就業率が60歳から64歳までと同水準になれば、就業者数は217万人増えます。勤労所得は8.2兆円増加し、消費支出には4.1兆円のプラスになるとの見通しです。
政府の調査によると、は65歳から69歳までの高齢者の65パーセントの方は「仕事をしたい」と感じているそうです。その一方で、実際にはこの年齢層で就業している人の割合は46.6パーセントにとどまっているそうです。
現政府は、今回の改革によって就労を希望する高齢者が意欲的に働ける環境を整える方針です。

2018年時点での15歳から64歳までの「生産年齢人口」は、前年比51万2000人減の7545万1000人です。総人口に占める割合は59.7パーセントで、1950年以来最低となっています。要は少子高齢化が進み、働く方が大幅に減っています。
今回のこの改正案は、2020年の通常国会に提出される予定です。
日本では高齢化がどんどん進み、これからは70歳までは働く時代がやって来そうです。





















