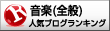△ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)
無性にクラシックが聴きたくなる時があります。
同じアコースティックな音なのに、なぜかジャズでさえ耳障りな時だってあるのです。いつもだと心地よく感じるはずのグルーヴ感が、逆に疲れを増加させるものにしかならないのです。
喉が渇いた時は水を飲みたくなるように、どこかが疲れている自分の気持ちが、クラシック音楽を求めているんでしょうか。
そういう時に聴きたくなる曲のひとつが、「G線上のアリア」です。ぼくの大好きな曲です。
■G線上のアリア
[Air From Overture No.3 BWV.1068/Air On The G-String]
■ヨハン・セバスティアン・バッハ
■1722年頃

『G線上のアリア100%』
「G線上のアリア」の作曲者は、ヨハン・セバスティアン・バッハ。原曲は、「管弦楽組曲第3番二長調 BWV.1068」の第2曲で、弦楽器だけで演奏されます。バッハがケーテンで宮廷楽長を務めていた1722年頃に書かれました。
今でこそこの曲は、バッハの作品の中では、「トッカータとフーガ」と並んで最も知られていますが、バッハの生前にはさして評判とはならかったそうです。
バッハの没後約100年後の19世紀半ばに再発掘され、それからはしばしば演奏されるようになりました。
1871年、ヴァイオリンの名手として名高いドイツのアウグスト・ヴィルヘルミ(1845~1908)が、この曲をヴァイオリンの一番低い弦(G弦)だけで弾けるように編曲しました。これがきっかけとなって、この曲は「G線上のアリア」というタイトルで広く知られるようになったということです。
ヴィルヘルミは多くの名曲を再発掘し、ヴァイオリン演奏用に編曲し直していますが、その中で最も有名なのが、この「アリア」というわけです。
現在では、弦楽器以外の楽器で演奏される時も、「G線上のアリア」として紹介されています。
ちなみに、「アリア」とは、本来は『オペラなどの、大規模で多くの曲を組み合わせて作られている楽曲における、叙情的でメロディックな独唱曲』という意味です。日本語では「詠唱」と訳されています。
ただし、「G線上のアリア」は独唱ではありませんから、本来の意味からは外れていると言えるかもしれません。

「アリア」は、おごそかで崇高な雰囲気の曲ですね。祈りのような美しいメロディーは、ドラマティックでさえあります。聴いているだけで気持ちが和らぐ清らかさがあるような気がします。
あまりにも美しいメロディーは、編曲者や演奏者の意欲をかきたててやまないらしく、さまざまな楽器によるさまざまな編曲があります。
ヴァイオリンはもちろん、チェロ、コントラバス、ピアノ、オルガン、二胡、ハンドベル、オカリナ、シンセサイザー、尺八、リコーダー、パンフルート、ハープ、琴、アカペラによるコーラス、などなど・・・。
クラシック畑の演奏ばかりでなく、ハード・ロック(イングヴェイ・マルムスティーン)、ラップとのコラボレーション(スウィートボックス)、ジャズ(ロン・カーター、ジャック・ルーシェ、マンハッタン・ジャズ・クィンテットなど)など、さまざまなジャンルのミュージシャンがこの曲を取り上げています。
また歌詞をつけて、歌曲として取り上げているヴォーカリストもいます。白鳥英美子(タイトル:Quiet Ways)や、サリナ・ジョーンズ(タイトル:Don't Speak Of Me)などです。
ぼくは、ヴァイオリンやチェロによって演奏されるものも好きですが、ほかには、オルガンや、コントラバスによる演奏も好きです。
とくに、ゲイリー・カーの弾くコントラバスの、ふくよかで温かみのある音で奏でられる「アリア」は、何度も何度も繰り返して聴いています。

ゲイリー・カー (コントラバス)
かつて、競走馬綜合研究所常磐支所で、音楽を聴かせた時の馬の反応を調べたことがあったそうです。
すると、ロック調の曲だと馬は興奮し、心拍数も平常の倍以上にはね上がりましたが、クラシック音楽を聞かせた場合は落ち着いた様子になるという結果が出ました。
最も沈静効果があった曲は、モーツァルトなどのゆるやかなテンポの曲で、その中にはこの「G線上のアリア」も含まれていたということです。馬は、半ば目を閉じてうっとりと聴き入っていたそうです。いい曲は馬をも惹きつけるんですね。
さしずめ、「馬の耳にアリア」といったところでしょうか。