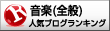朝目覚めると、予報通り今日も快晴。
暖かだけれど、どことなくひんやりした朝の空気を吸いながら新聞を取り出します。
スポーツ欄に目を通すと、わがタイガースはまたもや敗戦・・・。そうそう、昨夜は1対4になったところで中継を観るのをやめたんだった。
金本アニキは絶好調だけれど、そのほかの選手にさっぱり元気がない。もちろん精一杯やっているんだろうけど。。。アニキひとりにオンブに抱っこの状態では、この先が思いやられるなぁ。なかなか若手が育ってこない現状に問題があるのは目に見えている。
なんてことを考えながらパンとコーヒーで朝食を済ませました。
せっかくのいい天気、今日は何をしよう。といっても、ここ2週間ほどは年度末・年度始めで何かとバタバタしていたから、家でゆっくりしていたいのが本音です。パソコンの電源を入れて、とりあえずのBGMを何にしようか考えます。
最近、mukunohigeさんのブログで、アンディ・サマーズ(ポリス)のサイン会に行って一緒に写真を撮ってもらったことが記事になってたんですが、それに刺激されてポリスを聴いてみたくなりました。そこで取り出したのが「The Very Best Of Sting & The Police」です。

ギター、ベース&ヴォーカル、ドラムスの3ピース編成ですが、なかなかに練り込まれた、といってもキツキツに作り込まれたわけではなくて、音と音の間に余裕が見られるような、オトナの雰囲気のするロックです。「メッセージ・イン・ア・ボトル」とか「マジック」みたいなアップ・テンポの曲もありますが、それさえゆとりを感じます。ただガムシャラなだけなんじゃないんですよね。
後期アニマルズのギタリスト、アンディ・サマーズに、英国プログレッシヴ・ロックのカーヴド・エアのドラマーだったスチュアート・コープランドのいわば歴戦のツワモノが手を組んでいるからこその余裕もあるんでしょうか。
やや高めの声質で表情豊かに歌ってみせるスティングのヴォーカルはもちろん、エッジの効いたギター、バック・ビートが感じられるグルーヴィーなドラム、シンプルながら存在感のあるベースがきれいに溶け合ってますね。
そうそう、買ってあったDVD「ワンス・アンド・フォーエヴァー」も観なくては。これはベトナム戦争序盤のイア・ドラン渓谷の戦いをメル・ギブソン主演で描いたものです。原作者の一人、ハル・ムーアは、主人公として実際にこの戦闘に従事していました。もう一人の作者ジョー・ギャロウェイはUPIのジャーナリストとしてこの戦いに参加しました。

迫力ある戦闘シーンからは戦争の恐ろしさが充分伝わってきます。ムーア中佐とベトナム軍のアン中佐の知力を尽くした指揮ぶりもみどころのひとつでしょう。しかし、ベトナム側の視線も取り上げられていたり、家で愛する者の帰りを待ちわびる家族の姿などもふんだんに盛り込まれていて、単なるアメリカの勧善懲悪的な戦争映画とは一線を画しています。
これは原作を読んだんですが、いわゆる戦場での英雄的な働きを描いているのではなく、想像を絶する激烈な戦闘の中におかれた兵士たちの恐怖がありありと描かれていました。いわば人間ドラマともいえるシリアスな社会派作品でしたよ。
それから聴いたのが、オアシスです。
今までリリースされた全アルバムから、シングル曲やお気に入り曲をセレクトした、自己編集ベスト・アルバム(MD)なんです。
ダークでノリの良いギター・サウンドと、ジョン・レノンを彷彿とさせながらもどこかパンクっぽいヤンチャなヴォーカルがカッコいいなあ。時折り聴こえてくるオルガンやメロトロンがなかなか良いアクセントになってますね。
そして今日もう一枚じっくり聴いたのは、チック・コリア(ピアノ)とゲイリー・バートン(ヴィブラフォン)のデュオ・アルバム「クリスタル・サイエンス」です。

文字通りクリスタルな響きのするサウンドはどこか涼しげです。しかしながら両者のインタープレイは熱気をはらんでいて、ふたりだけで演奏しているとは思えない音の厚みを感じさせてくれます。チックとゲイリーがしのぎを削る、というよりは、ふたりがしっかりと手を組んで、同じ方向へ進んでいこうとしているような気がします。
机の上にはまだ封を切っていないCDがあります。ウェイン・ショーターの「スーパー・ノヴァ」、マイルス・デイヴィスの「パンゲア」、ジョー・ヘンダーソンの「ページ・ワン」、の3枚です。今夜からはこれらをじっくり聴いてみたいと思います。こういうささやかな楽しみが自分を待っているというのは気持ちの良いものですよね。
結局今日の日中はパソコンとCDとDVDで過ごしてしまいました。昼寝も少ししたし、何もなかったけれど平和な日曜日でした。(^^)
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
ここんとこ「自分的ベストテン」のお題にハマっています(^^)
先日はピアノ曲を取り上げたので、今回は鍵盤つながりということで、「オルガンが印象的な曲 マイ・ベスト・テン」を選んでみました。
ジャズにどっぷりと浸かっていた頃、あるジャズ・ピアノ弾きの方と話していて、「楽器はアコースティックの方が究極的には飽きないし気持ちが疲れない」という結論に達したことがあります。今思うとこれは極論だと思いますが、その時、例外の音色としてあがったものが二つありました。ひとつはフェンダーのエレクトリック・ピアノ「ローズ」。そしてもうひとつがハモンド・オルガン(もちろんレスリー・スピーカーに繋いだもの)だったんです。
ぼくの育った家には姉が習っていたためにエレクトーンが置いてありました。ぼくも幼稚園の頃、オルガンを習いに行かされましたが、わずか一日で脱走した思い出があります。でもオルガンがキライだったわけではなく、ピアノやオルガンを習う子がみな女子であることに抵抗があったんですね。だからちょくちょく家のエレクトーンはイタズラ弾きしてました。
オルガンとひとくちに言っても、教会にあるパイプ・オルガンを始めとして、クラシックで使われるオルガン、ジャズ・オルガン、ロック系統で使われるオルガン、R&Bで使われるオルガン、それぞれに持ち味があります。また、それらオルガン曲の数も膨大なもので、そのすべてを聴いたのか、というとそういう訳でもなく、ぼくが聴いて好きになったごく一部の曲群から自分的10大オルガン曲を挙げてゆきたいと思います。ただしクラシック系、ジャズ系は省き、ロック・ポップス系統のものだけにしぼってみました。
といいつつも、例外として「G線上のアリア」はあげておこうかな。これ、もともとは弦楽器のための曲なんですが、オルガンで弾かれる例も多く、そのメロディの素晴らしさと雰囲気にはとても心惹かれるものがあります。
次点 翳りゆく部屋(荒井由実)
スモーキン/Smokin'(ボストン)
「翳りゆく部屋」、日本のポピュラーから唯一選んでみました。このイントロの教会風オルガンは松任谷正隆氏が弾いているのかな。本当に光と影の鮮やかなコントラストが目に浮かんでくるような曲だと思います。ユーミンのレパートリーの中でも好きな曲。
「スモーキン」はギタリストのトム・ショルツがオルガンを弾きまくっているハードなブギー・ナンバー。めっちゃカッコいいですよ!
⑩ギミ・サム・ラヴィン/Gimme Some Lovin'(スペンサー・デイヴィス・グループ)
映画「ブルース・ブラザーズ」の中でも演奏されていますよね。当時弱冠16歳だか17歳だかのスティーヴィー・ウィンウッドが作り、オルガンを弾きながら歌っていた曲です。オルガン主体のサウンドに乗ったソウルフルな歌声が良いですね~
⑨ライク・ア・ローリング・ストーン/Like A Rolling Stone(ボブ・ディラン)
ディランはそんなに深くは聴いてないのですが、歌詞がとても文学的なんですよね。なんでもノーベル賞にノミネートされたこともあるとか。フォークのカリスマとして偶像視されていただけに、彼がエレキ・ギターを持ったことは大きな事件だったようです。その「エレクトリック・ディラン」の放ったビッグ・ヒット、「ライク・ア~」はバックに流れるオルガンが印象的。このオルガンを弾いているのがアル・クーパーです。彼はほとんどオルガンを弾いたことがなかったそうなんですが、この曲のレコーディングで適当なキーボード・プレーヤーがいなかったため、半ば強引に申し出て演奏したんだそうです。そのプレイはとても個性的だったので、このディランとのセッションによってアルはオルガン奏者として認められました。
⑧ハートに火をつけて/Light My Fire(ドアーズ)
ドアーズのオルガンの音色も実に個性的ですよね~ 一聴しただけで、「あ、レイ・マンザレクだ」と分かります。この曲はシングル・ヴァージョンもあるんですが、オルガンを堪能しようと思ったら、やはりアルバムに収められているロング・ヴァージョンをオススメしたいです~
⑦ショットガン/Shotgun(ヴァニラ・ファッジ)
オルガンの音色も目立ちますが、どちらかといえばこの曲はメンバーそれぞれのソロをフィーチュアすることで成り立っています。とはいえマーク・スタインの弾くオルガンは攻撃的で存在感バッチリ! オルガンがハード・ロックの中でも充分雰囲気をヒート・アップさせることができることを証明している感じですね。目立つといえば、この曲ではカーマイン・アピスのドラムも印象的。
⑥男が女を愛する時/When A Man Loves A Woman(パーシー・スレッジ)
いや~、この曲は名曲ですね。そしてパーシーの熱唱も名唱のうちに数えられるべきでしょう。いわゆる3連のロッカ・バラードです。派手なオルガンのソロはないですけれど、全編バックで流れるオルガン・サウンドは実にシブくて黒っぽく、曲の印象を決定づけていますよね。この曲はマイケル・ボルトン版も好きで、カラオケで無謀なチャレンジを繰り返しては、その度に自滅しています(^^;)
⑤七月の朝/July Morning(ユーライア・ヒープ)
10分以上にも及ぶ大作。ハード・ロック・バンドの作るバラードには美しいものが多いですが、この曲もメロディアス。オルガンを弾いているのはケン・ヘンズレーです。歪み系のエフェクターをかけた音色が個性的。中間部のソロはメロディックでしかも弾きやすいので、コピーしてカセット・テープをバックによく弾いて遊んでいました。
④聖地エルサレム/Jerusalem(エマーソン・レイク&パーマー)
もともとはこの曲、賛美歌だそうです。オルガン、ベース、ドラムスのオルガン・トリオで演奏されている、まさにオルガン曲。アレンジもオルガンもキース・エマーソンが担当しています。キースはロック界屈指のキーボード・プレーヤーとして有名ですね。ドラマティックで、そのうえ荘厳な雰囲気を湛えているこの曲、「プログレは難解だから」と思って二の足を踏んでいる方々にもオススメの名曲です。
③朝日のあたる家/The House Of The Rising Sun(アニマルズ)
1960年代を代表する名曲のひとつです。8分の12拍子で、トラディショナル・フォークをアレンジしたものです。エリック・バードンの歌声が実にソウルフル。エリックのヴォーカルと並んでバンドの売り物だったのが、アラン・プライスのオルガンです。この曲のソロはとても有名。オルガンがまるですすり泣いているように聴こえます。当時の日本のGSもこぞってこの曲をレパートリーに取り入れていたようですが、その中で唯一このアランのオルガンを完コピーしていたのが大野克夫氏だった、というのを何かで読んだことがあります。
②紫の炎/Burn(ディープ・パープル)
バッハのコード進行をモチーフにしたと言われている曲です。ギターとオルガンがハモるリフもかっこいいし、ヴォーカルもとっても渋カッコいい! ジョン・ロードの弾く間奏部分、実にドラマティックです。スピード感はあるし、メロディもクラシカルで実に美しいです。初期の頃の「ハッシュ」「ヘイ・ジョー」などの曲で聴かれるオルガンもサイケで良いですよね。
①にして別格 青い影/A Whiter Shade Of Pale(プロコル・ハルム)
もう万人が知っている名曲中の名曲でしょう。ぼくの好きな曲ベストテンにももちろん入ります。ぼくが「レット・イット・ビー」に続いて弾けるようになりたいと思った曲です。頑張ってマシュー・フィッシャーの弾くオルガン・パートを全編コピーしました~ この曲はエレクトーンの教材にも使われているんですよね。ゆるやかな8ビートに乗って雰囲気満点のオルガンが終始流れています。当時、「クラシックとR&Bが結婚した曲」だと評されていた通り、荘厳ながらもどことなく黒っぽい響きのする曲だと思います。過去にCFに使われたことも多く、有名なイントロ部分などは、ほとんどの人が知っているのではないでしょうか。

ロック・ポップス系のオルガンだけでなく、ジャズ・オルガンも好きですよ~ とくにやはりジミー・スミス御大! ジャズ・オルガンってブラス・セクションにも合うし、ギターとの絡みを聴いても楽しいんですよね。
もちろんクラシック系のオルガンも大好き。やはり教会音楽で使われているオルガンが荘厳で良いです。コントラバスとオルガンのデュオ・アルバムも何枚か持ってますが、クラシックの名曲をたくさん取り上げているので聴きやすく、よくCDをトレイに乗っけてます。
さて、「自分的ベスト10」、まだネタがありますので、まとまり次第記事にしてみたいと思います~(^^)
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
先日の記事の流れで、「ベスト10」モノをいろいろと考えています。
今日はその中で、自分的10大「ピアノが印象的な曲」をあげてみることにします。
ピアノといっても、例えばジャズやクラシックにはピアノ曲がゴマンとあるので、今回は範囲をロック・ポップスに限ってツラツラと思い返してみました。
でも、膨大な数のあるポピュラー・ソング、その中から「ベスト10」を決めるのは至難の技であり、不可能に近いので、この記事ではあくまでぼくの脳ミソの中に、とりあえず浮かんだもののなかから10曲選んでみました。
でも、思い出せずに、のどのところあたりでつっかえているものもたくさんあるかもしれないなあ。
次点 アイ・シャル・ビー・リリースト(ザ・バンド)
ボブ・ディランが作った曲でしたっけ。ぼくはザ・バンドの演奏の方が気に入ってます。イントロの高音のシングル・ノートが印象的です。C&W系のバンドのセッションでよく演奏した記憶があります。
⑩オネスティ(ビリー・ジョエル)
弾き語り系の代表的なもののひとつではないでしょうか。これなら弾けそう、と思ってチャレンジしてみましたが、ぼくクラスの腕では結構難曲で、途中で挫折してしまいました(汗)。歌も、歌ってみるとかなり難しかったです。
⑨ボヘミアン・ラプソディ(クイーン)
オペラ風味をたっぷり取り入れた曲だけに、ピアノもどこか壮大な感じがします。イントロと最初のメロディ・パート、それにエンディングが、主にピアノだけで構成されています。そのシンプルさと、中盤のコーラス・パートやギター・ソロの対比が美しいと思います。
⑧グッドバイ・イエロー・ブリック・ロード(エルトン・ジョン)
エルトン・ジョンもピアノの弾き語りスタイルだけあって、ピアノの印象が強い曲をたくさん残してますね。ぼくは「僕の瞳に小さな太陽」なんかも大好きです。「グッドバイ~」のピアノは、簡潔にして広がりがある、って感じがします。
⑦ザッツ・ミー(アバ)
ピアノ曲というと、しっとりしたイメージがあるんですが、ロックンロールやブキウギなんかの明朗系でもピアノは大活躍しますよね。軽快なアップテンポに乗った「ザッツ・ミー」もとっても楽しい曲です。コーラスの美しさもアバならでは。
⑥明日に架ける橋(サイモン&ガーファンクル)
ゴスペル・タッチの、荘厳で雄大な曲ですよね。ベスト・アルバム(2枚組レコード)の解説で、『バッハにインスパイアされた』とあったのを読んだ記憶があります。ぼくのピアノは、コードの構成音を主体とした弾きかたの、ナンチャッテ・スタイルですが、それでもこの曲は充分自分で楽しんでいます。
⑤イマジン(ジョン・レノン)
「シンプル・イズ・ベスト」という表現がピッタリなんですよね、この曲。バックはピアノ・トリオ主体なんですが、演奏が全然寂しくないんです。むしろどこか枯淡の味わいがあるような気がします。コード進行も単純なのに、とてもメロディアス。ジョンってやっぱりスゴいなあ、と思います。
④オール・バイ・マイセルフ(エリック・カルメン)
この曲は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番(作品18)第2楽章のメロディーをアレンジしたことで知られていますね。とってもドラマティックなサビを持つ名曲だと思います。聴くならロング・ヴァージョンの方をオススメします。中間部のピアノ・ソロがとても泣けるのです。エリック自身、クラシック出身なので、ピアノも専門的に教育を受けているみたいです。
③いとしのレイラ(デレク&ザ・ドミノス)
「えっ、これギター曲でしょー」と言われる方もおられるでしょうね。でもぼくは、後半部分の、ボビー・ウィットロックの弾くピアノも大大大好きなのです~。その部分はぜひ自分でも弾いてみたい、と思って、耳コピー+市販の楽譜+自分流テキトー・アレンジでなんとか弾けるようになりました。このピアノ・パートに乗って流れているスライド・ギターも泣かせますよね。
②デスペラード(イーグルス)
邦題「ならず者」。多くの歌手がこの曲をカヴァーしてますが、ぼくはなんといってもイーグルス版! この曲もどちらかというと弾き語り系でしょうか。美メロにプラスされた渋さがなんとも言えません。哀愁漂う歌声もたまりませんね~ この曲も自分で弾いてみたくて、耳コピー+テキトー・アレンジでなんとかモノにしました。部屋で時々歌いながらピアノ弾いて遊んでます。
①レット・イット・ビー
この曲は、以前にも記事にしたんですが、初めて聴いた時の印象が強すぎて、自分の中ではおそらく永遠のベスト・ピアノ曲になるでしょう。小学校の時に、オレンジ色の夕日が差し込む中で聴いたゴスペル・タッチのこの曲がくれた感動、忘れられません。中3の時に音楽の先生に教えてもらって、左手でコード、右手でメロディを弾くというパターンでこの曲を弾けるようになった時の満足感も忘れ難いです。のちにビートルズの完全コピー譜を手に入れたので、この曲のピアノ・パートはみっちり練習して弾けるようになりましたよ~

「ピアノが印象的な曲 10撰」、とりあえずこんなところでしょうか。
ある曲を聴いて、「自分も歌ってみたい」とか「弾いてみたい」と思わされること、そして自分が実際に歌ったり弾いたりさせられることってすごいことなんですよね。自分をそうさせる巨大なエネルギーがその曲にはあるってことですもんね。
だから、ぼくにこんな記事を書かせた上記の10曲+1、やっぱり魅力あふれる名曲ぞろいだということが言えるんだと思います。
また何か他の「自分的ベスト10」、思いついたら記事にしてみます~(^^)
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
ここ最近、Nobさんのところやイチロー・SUZUKIさんのところで記事になっているのが「好きな歌手ベスト・テン 男性篇&女性篇」です。
楽しそうな企画なので、ぼくもさっそくそれに乗っかってみました~(^^)
男性篇
①ポール・マッカートニー(ビートルズ、ウィングス)

以下順不同
フレディ・マーキュリー(クイーン)
スティーヴィー・ワンダー
沢田 研二
フランク・シナトラ
ドン・ヘンリー(イーグルス)
尾崎 豊
スティーヴ・ペリー(ジャーニー)
忌野 清志郎(RCサクセション)
ジョン・レノン
*番外…ボズ・スキャッグス、デヴィッド・ボウイー、ミック・ジャガー、イアン・ギラン、ロバート・プラント、などなど。
女性篇
別格 ジャニス・ジョプリン

以下順不同
カルメン・マキ(カルメン・マキ&OZ)
カレン・カーペンター(カーペンターズ)
美空 ひばり
アニタ・オデイ
吉田 美和(ドリームス・カム・トゥルー)
ちあきなおみ
アレサ・フランクリン
クリッシー・ハインド(プリテンダーズ)
キャロル・キング
番外…山根麻衣、スージー・クアトロ、シルヴィ・ヴァルタン、グレース・スリック、ジョニ・ミッチェルなどなど。
一応、あくまで「歌い手」としてぼくの琴線に触れたかどうか、というところを基準にしてみました。
男性篇は番外にロック界の大スターが集ってしまいましたが。。。
ポールは甘いバラードからハードなロックンロールまで幅広く歌いこなせ、しかも聴いているこちらに好感を抱かせてしまうようなマジックを持ってますね。
シナトラ御大の圧倒的存在感は、まさに彼が大スターであることを示していますよね。フレディもステージングからして他の歌手よりひとランク違ってましたよね。ダイナミックかつシアトリカルなステージ、魅力たっぷりでした。
スティーヴィーの歌は、曲もそうだけど、とにかくカラフル。いろんな鮮やかな色の数々が浮かんで来ます。
日本代表はジュリー。歌の表現力、色気、スター性とも文句なしではないでしょうか。
尾崎豊は、自分の身を削るような、悲痛な叫びが聴こえてくるような歌ですが、そこに共感を覚えます。歌に命をかけていたんではないでしょうか。
「ボス」こと忌野清志郎、ガンから復活してくれましたね~(^^)R&Bに深く傾倒した彼の歌とステージングは実に個性的です。
ドン・ヘンリーの甘く切ない声、相変わらずレディー・キラーぶりを発揮しているようですね。
スティーヴ・ペリーは飛翔感のある、伸びやかな高音が魅力です。
そしてジョン・レノン。いつもどこかトンガッたまま駆け抜けていったような気がしますね。ビートルズで最もロック・スピッリトを持っていたのは彼ではないでしょうか。
女性篇、ジャニスは別格です!まさにブルーズを歌うために生きてきた女性。派手なパフォーマンス、潰れかけた声での魂のシャウト。どこをとってもカッコいいです~
カルメン・マキは日本の女性シンガーの中で最も好きです。叙情的な歌も歌えば、ワイルドにキメたハード・ロックで聴衆を圧倒する、ヴォーカリスト中のヴォーカリストだと思ってます。
カレン・カーペンター!彼女の声はポップス界の至宝です。ほどよい甘さ、ほどよい深み、抜群の歌唱力と表現力。未だにファンが多いのも頷けます。
アニタ・オデイは映画「真夏の夜のJAZZ」で観て、いっぺんに大ファンになりました。バンドを手玉にとって自由自在に曲をリードしてゆく「おきゃん」なアニタ姐さん、可愛らしくもありました。驚異的なタイム感覚にも驚かされましたよ~
ひばり嬢は、亡くなる少し前にテレビで観た「川の流れのように」を聴いて、鳥肌が立ちました。とにかくうまい!感情移入がハンパじゃない。とにかく凄い歌手だと思います。歌のうまさでゆくと、吉田美和嬢なんかもかなりのものですよね。難曲を柔らかくサラリと歌うその実力、もっともっと評価されても良いと思います。ちあきなおみさんの歌は、何と言うか演劇を観ているような気がします。彼女の歌への入り込み方もなまなかじゃないですよね~
アレサ・フランクリンは「ブルース・ブラザース」でもお馴染みですね。ド迫力のR&Bシンガーですが、バラードを歌っても絶品だし、なんといってもゴスペルを歌う時の圧倒的声量と、神に全てを委ねて奔放に歌っているその姿勢には背筋に電気が走ります。
80年代のロック界を疾走したプリテンダーズの看板娘、クリッシー・ハインドの持つロック・スピリットもまばゆい光を放っています。「クリッシー姐さん」と呼ぶ方が親近感が湧くかも~
キャロル・キングの歌は、派手さはないんですが、じんわりと温かみが伝わってきます。いわゆるソウルフルなものなんですね。
こうしてみると、ぼくのセレクトは1970~80年代に集中しているような気がします。かつての名歌手を超えるような存在が未だに現れないのか、ぼくの好みが1980年代でストップしているのか・・・(汗)
でもあれやこれやと考えていると楽しかったですよ。
この後もお気に入りギタリストとかピアニストとかやってみようかな(^^)
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
ジャズには夜が似合います。だから、ジャズを語るのも本当は夜のほうが良いかもしれません。
唐突ですが、「良い演奏」ってどういうものでしょう。いろんな答えが出てくるでしょうが、ぼくの考える条件は、大雑把に括って「そこに感動があるかどうか」です。
素晴らしいテクニックがあっても、ハートが伴っていなければ感動は生まれないでしょうし、ハートだけが突出していても、それを聴衆に伝えるテクニックがなければ演奏者の思いは伝わりにくいでしょう。
良い演奏は聴衆を感動に導きます。感動した聴衆は熱い反応で演奏者に応えます。すると演奏者はさらにボルテージの上がった演奏を繰り広げることがしばしばあります。聴衆が演奏者を育て、燃え立たせているのですね。
マイルス・デイヴィス・クィンテットのライヴ・アルバム「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」の中に収められている「星影のステラ」には、感極まったある聴衆のダイレクトな反応が記録されています。緊迫感にあふれた見事な演奏ですからね、ムリもありません。(だからライヴ・アルバムはやめられないんです~ )
)
さて、キース・ジャレットに「スタンダーズ・ケルン・コンサート/オール・オブ・ユー(Keith Jarrett Trio/Tribute)」という、これもライヴ・アルバムがあります。
ぼくはこのアルバムDisc2の5曲目に収められている「オール・ザ・シングス・ユー・アー(All The Things You Are)」が大好きです。もっと詳しく言うと、「演奏と、曲の途中で沸き起こる大喝采」がとても好きなんです。

■キース・ジャレット・トリオ 「オール・オブ・ユー」
(Keith Jarrett Trio/Tribute)
■録音
1989年10月15日 西ドイツ、ケルン・フィルハーモニー
■録音メンバー
キース・ジャレット/Keith Jarrett (piano)
ゲイリー・ピーコック/Gary Peacock (bass)
ジャック・ディジョネット/Jack DeJohnette (drums)
◆オール・ザ・シングス・ユー・アー/All The Things You Are
◆発表…1939年
◆作詞…ジェローム・カーン/Jerome Kern
◆作曲…オスカー・ハマースタイン2世/Oscar Hammerstein Ⅱ
曲はキースのイン・テンポでのソロ・ピアノで始まります。音が目に見えるかのような鮮やかさで迫ってきます。ぼくはただ圧倒されるばかり。
美しい。
情熱的で、優美で、神々しささえ感じられるソロです。聴衆は、おそらく息を呑んでひたすら聴き入っているのでしょう。
そしてゲイリー・ピーコック(Bass)と、ジャック・ディジョネット(Drums)が合流すると、まるで魔法が解けたかのような熱狂的な拍手と悲鳴が、洪水のようにスピーカーからあふれ出てきます。
感動的でさえあるこの拍手の洪水で、ぼくの興奮もさらに増してゆきます。
この曲(演奏)からは、「演奏者と聴衆は二人三脚」である、ということを教わりました。

なお、この「オール・ザ・シングス・ユー・アー」は、ジェローム・カーン(作詞)とオスカー・ハマースタイン2世(作曲)のゴールデン・コンビによって1939年に作られた、永遠に残るであろうスタンダード・ナンバーです。
もともとはミュージカル「ヴェリー・ウォーム・フォー・メイ」のために書かれましたが、アドリブをするための曲かと思わせられるほどの音楽的面白さに満ちているところから、今ではインストゥルメンタル奏者からも絶大な人気を集めている、名曲中の名曲です。 キース・ジャレット・トリオ「オール・ザ・シングス・ユー・アー」
キース・ジャレット・トリオ「オール・ザ・シングス・ユー・アー」