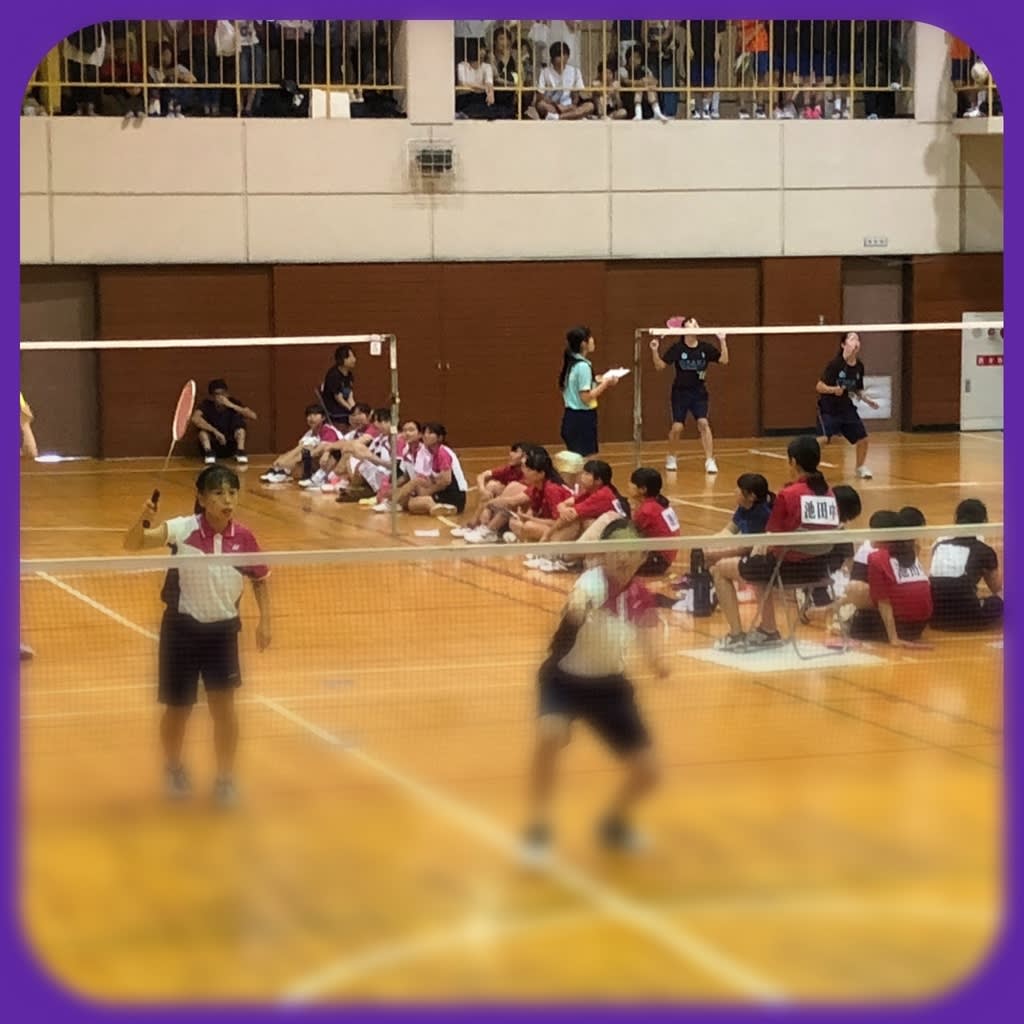1980年代の頃の中学校は、荒れていました。
当時、全国の中学校で校内暴力や器物破損、服装違反、非行が問題になっていました。
その頃は、生徒がもつ有り余るほどのエネルギーを外に向けて出していたのであり、それが暴力や非行などの問題行動として現れていたものと考えられます。
では、いまの中学生にはエネルギーがないのかと言えばそうではないと、わたしは考えます。
エネルギーはあるのですが、それは外向きに出しているのではなく、内向きに出しています。
それが、いじめや不登校になって現れているというとらえ方を、わたしはしています。
そこで部活動についてですが、1980年代の中学校での部活動は、生徒のエネルギーの外への出し方を、正しい方向に向けるという役割があったのです。
授業は成立しにくく、授業妨害や授業エスケープなどが起こり、生活指導も困難なことが多くありました。
そこで部活動で生徒を「管理」して、クラブで世間の良識や社会のルール、集団生活の過ごし方や集団の中での人間関係を教えるという役割には大きなものがありました。
ところが、そういった部活動の役割も1990年代の中ごろから変わってきました。
それは個人の自己選択や自己実現が叫ばれるようになり、教育でも個人がやりたいことを見つけるとか、「自分さがし」、自分の夢実現が重要視される社会へと変わってきたということです。
そこで、部活動も集団指導というよりは、生徒一人ひとりを自立させる指導・支援の場や機会として機能するように徐々に変わってきました。
生徒の願いも、自分がチームの一員で多くのチームメイトと仲間関係を築きたいというよりも、1対1のコミュニケーションをとりたいに変わってきたのでした。
かといって、学校での部活動がいらないかといえば、そうではありません。
部活動の役割の変化は、おもに顧問にとっての役割が「指導者」と「生徒」という関係が「わたし」と「あなた」という関係になったのであり、生徒にとっての部活動の意義はやはり大きいのです。
部活動を地域に移行していくのは、おもに土日の活動であり、部活の主体は地域になるとすれば学校は地域の連絡調整は密にしなければならなくなるでしょう。
とにかく、部活改革はその制度設計をしっかりと打ち立てていかないと、だれのための改革かわからなくなります。
学校が子どもの成長のすべてを担う必要がないのは確かです。
ですから、部活改革については地域スポーツに移行していくのが適切だと考えます。
だからこそ制度設計をしっかりしないと活動は迷走する心配があります。
中学生の3年間は、生徒にとっては一度きりであり、「いまは過渡期だからいたらない点はあります」ではすまないのです。