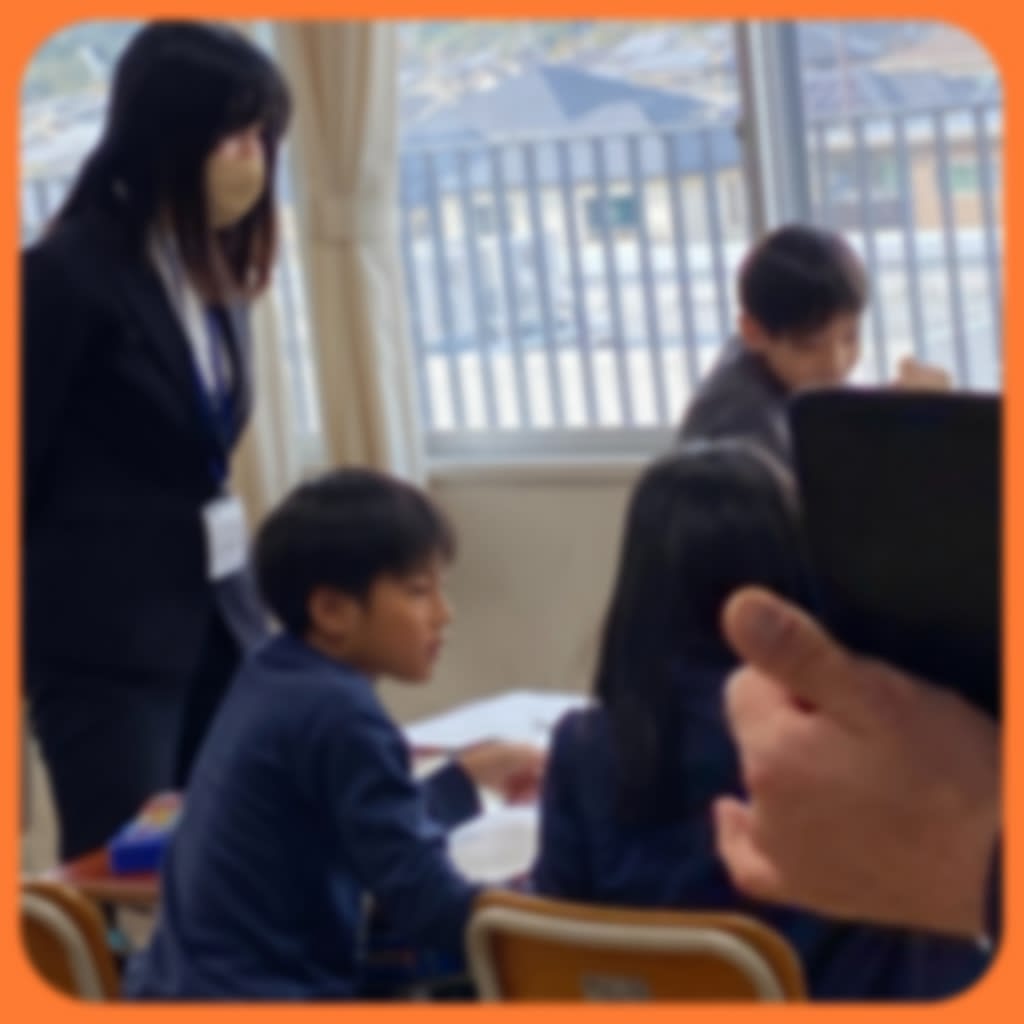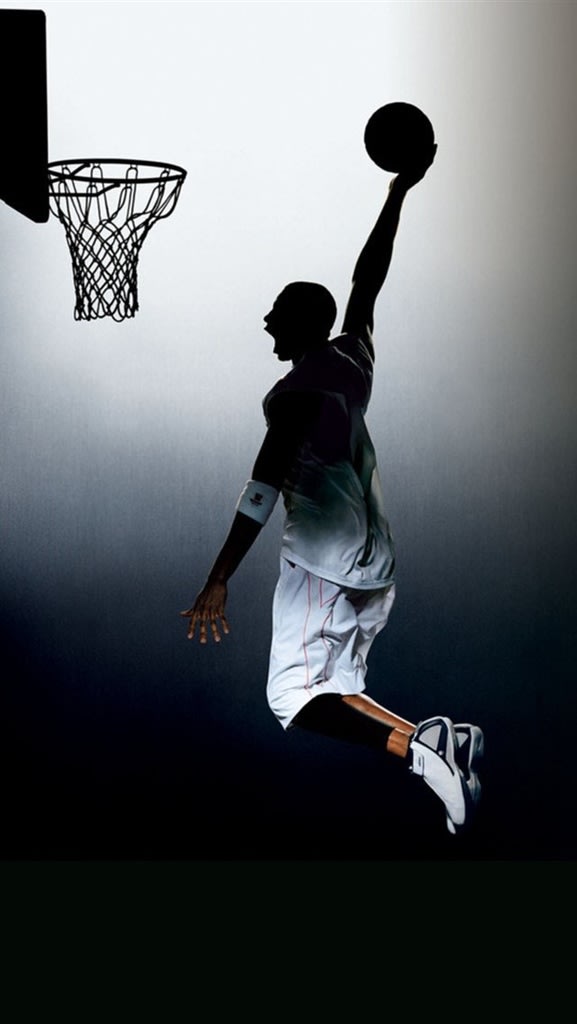日本は、本格的な働き手不足の時代に入りました。
日本では2011年以降、人口が減少に転じました。
少し前から日本では「働き手不足」と言われてきました。
ところがその後も、じつは働く女性や高齢者の増加で働き手の数は右肩上がりで増えていたのでした。
ですが、2019年の6700万人が頭打ちで、その後は減少していくという見方が現実味を帯びてきました。
人口減少の影響に直接さらされるようになったのが現在です。
賃上げできない企業は、働き手がいなくて将来を描けない時代になった。
そこで、今年度の採用では、初任給を上げて30万円超えにする企業が現れました。
そういった企業には、就活中の学生の応募がやはり集まります。
そのように賃金を上げることに余裕がある企業には、働き手が集まります。
しかし、上げることができない中小企業は人を確保できないのです。
今は、働く意思があれば、収入を問わないなら、たいていの人びとが雇用される状況です。
社員に会社への「奉仕」を求めるような昭和の発想で企業経営をやっていると、若手だけでなく、30代、40代の社員も逃げてしまいます。
過去の経営とは決別する必要があるのでしょう。
そういう意味では、今は働き手が企業を選ぶ時代になっています。
今春入社の新卒募集を行った企業の4社に1社が計画で定めた人数を確保できなかったといいます。
もちろん、初任給だけで決めるのでは不十分です。
各種手当や残業代、ボーナスを含めた実質の年収がいくらになるかなど、チェックするべき点はあります。
とはいえ、「初任給○万円」という打ち出しは、新卒者には大きな影響を与えるのでしょう。
もはや、賃上げをできない企業は今後経営が行き詰まる時代になったのです。