
今月16日、野田総理は一連の東電福島原発事故の「収束」を宣言しました。確かに原子炉内の水温が100℃以下となってはいますが、まだ誰も原子炉内を見ていないのでどうなっているのかが全く分かりません。メルトダウンとかメルトスルーとかの言葉が先走っているものの、水温計や圧力計等から内部の様子を推定するだけで、本当に中を覗けるのは何十年も後のことでしょう。
また、冷温停止になったと言っても、原発から半径30kmの市町村住民の大半は避難したままだし、いまだに冷却用の応急配管からは汚染水が漏れだしているし、タンクに溜まった汚染水は貯蔵場所がないぐらいの本数に達しています。そして、一番の懸念はほとんど進まない除染作業です。野田総理や細野環境相が除染のモデル事業を見に、何度か福島県に来ています。しかし、この除染作業の決め手がありません。基本的には土の表面5~10cm程度を削ったり、高圧洗浄機で屋根瓦や外壁を洗い流したりと、原始的な方法で行うことになります。9ヶ月経つ今でもまだモデル事業の段階で、本当に一部分しか行われていません(←我が家の近所では小中学校の校庭で表土除去が行われたのみです)。緊急時避難準備区域である浪江町や楢葉町の公共施設は自衛隊がデッキブラシや洗浄機でごしごしこすってくれています。原発から60kmほど離れた福島市や郡山市では町内会や全国から来ているボランティアさんがゲリラ的に行っています。もちろん、原発から半径20km圏内の警戒地区は放射線量が高いために、震災以前に暮らしていた住民でさえ立ち入り禁止です。「千里の道も一歩から」の格言がありますが、一歩、二歩で立ち止まっている感じです。
何故除染作業が進まないかというと、除染に伴って出る放射性物質で汚染された土壌を置く場所が決まっていないからです。個人の住宅や町内会で仮置き場を作り、次に3年後をメドに市町村ごと程度に中間貯蔵施設を造り、今後30年後を目標に最終処分場を完成させることとなっています。放射性物質を含む土壌を進んで引き受ける地区はありません。線量の極めて低い岩手県辺りの瓦礫だって、引き受けてくれる自治体がなかなか見つからなかった訳ですから、福島県の汚染土壌なんて進んで引き受けてくれない訳です。どこの都道府県も拒否するだろうから、結局は福島県内のどこかに処分場を造るしかないと思います。それだって、福島県民にとっては迷惑な話です。原発事故でいろいろな被害を既に被っているのですから、心情的にもういい加減にしてくれ状態です。
それに、除染作業自体が効果的なものと言えないからです。極言すれば、放射性物質は人間の力ではどうすることもできないということです。各種実験から、汚染されたコンクリートや屋根瓦を水で洗い流しながら、ごしごしこすっても放射線量が8割程度に下がるくらいだそうです。やらないよりはましですが、気の遠くなる作業です。除染は住宅だけでなく、道路も森林部も満遍なくやらなければ意味がないのです。膨大な森林面積(主に中通りと浜通りの境となっている阿武隈高地)を抱える福島県はこれが困難を極めると思います。森林の落ち葉部分や爆発時に葉が繁っていた針葉樹の葉の部分、針葉樹・広葉樹にかかわらず樹皮部分など、線量が高いことが報告されています。全部伐採という訳にもいかないので、悩ましいところです。
おまけに、個人的には水が心配です。除染モデル事業では剥ぎ取った表土を土嚢に入れ、それを防水シートの上に置いたり、ポリバケツに入れて保管したりしていますが、洗い流した水は集めるのが困難なためなのか、流しっぱなしです。流れに任せています。地面に染みこんだり、側溝に流れ込んだりしているのをテレビでよく見ます。土壌に放射性物質があるなら、水の中にもあるはずです。これがゆくゆくは河川や地下水、海へ行くのかと思うと、この原発事故の影響は何百年も尾を引くと思います。
また、冷温停止になったと言っても、原発から半径30kmの市町村住民の大半は避難したままだし、いまだに冷却用の応急配管からは汚染水が漏れだしているし、タンクに溜まった汚染水は貯蔵場所がないぐらいの本数に達しています。そして、一番の懸念はほとんど進まない除染作業です。野田総理や細野環境相が除染のモデル事業を見に、何度か福島県に来ています。しかし、この除染作業の決め手がありません。基本的には土の表面5~10cm程度を削ったり、高圧洗浄機で屋根瓦や外壁を洗い流したりと、原始的な方法で行うことになります。9ヶ月経つ今でもまだモデル事業の段階で、本当に一部分しか行われていません(←我が家の近所では小中学校の校庭で表土除去が行われたのみです)。緊急時避難準備区域である浪江町や楢葉町の公共施設は自衛隊がデッキブラシや洗浄機でごしごしこすってくれています。原発から60kmほど離れた福島市や郡山市では町内会や全国から来ているボランティアさんがゲリラ的に行っています。もちろん、原発から半径20km圏内の警戒地区は放射線量が高いために、震災以前に暮らしていた住民でさえ立ち入り禁止です。「千里の道も一歩から」の格言がありますが、一歩、二歩で立ち止まっている感じです。
何故除染作業が進まないかというと、除染に伴って出る放射性物質で汚染された土壌を置く場所が決まっていないからです。個人の住宅や町内会で仮置き場を作り、次に3年後をメドに市町村ごと程度に中間貯蔵施設を造り、今後30年後を目標に最終処分場を完成させることとなっています。放射性物質を含む土壌を進んで引き受ける地区はありません。線量の極めて低い岩手県辺りの瓦礫だって、引き受けてくれる自治体がなかなか見つからなかった訳ですから、福島県の汚染土壌なんて進んで引き受けてくれない訳です。どこの都道府県も拒否するだろうから、結局は福島県内のどこかに処分場を造るしかないと思います。それだって、福島県民にとっては迷惑な話です。原発事故でいろいろな被害を既に被っているのですから、心情的にもういい加減にしてくれ状態です。
それに、除染作業自体が効果的なものと言えないからです。極言すれば、放射性物質は人間の力ではどうすることもできないということです。各種実験から、汚染されたコンクリートや屋根瓦を水で洗い流しながら、ごしごしこすっても放射線量が8割程度に下がるくらいだそうです。やらないよりはましですが、気の遠くなる作業です。除染は住宅だけでなく、道路も森林部も満遍なくやらなければ意味がないのです。膨大な森林面積(主に中通りと浜通りの境となっている阿武隈高地)を抱える福島県はこれが困難を極めると思います。森林の落ち葉部分や爆発時に葉が繁っていた針葉樹の葉の部分、針葉樹・広葉樹にかかわらず樹皮部分など、線量が高いことが報告されています。全部伐採という訳にもいかないので、悩ましいところです。
おまけに、個人的には水が心配です。除染モデル事業では剥ぎ取った表土を土嚢に入れ、それを防水シートの上に置いたり、ポリバケツに入れて保管したりしていますが、洗い流した水は集めるのが困難なためなのか、流しっぱなしです。流れに任せています。地面に染みこんだり、側溝に流れ込んだりしているのをテレビでよく見ます。土壌に放射性物質があるなら、水の中にもあるはずです。これがゆくゆくは河川や地下水、海へ行くのかと思うと、この原発事故の影響は何百年も尾を引くと思います。













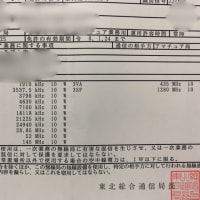

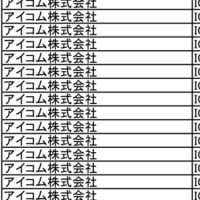
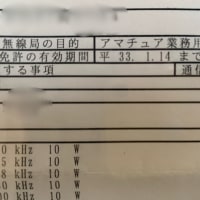
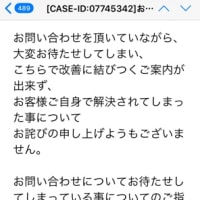
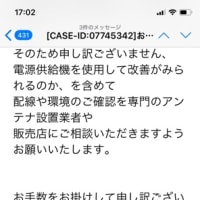
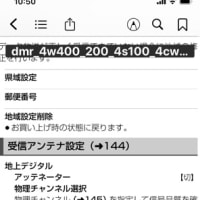
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます