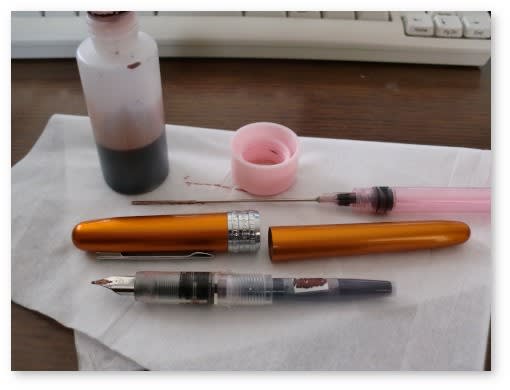雨降りの日曜午後、サクランボ果樹園の剪定はお休みで、山響こと山形交響楽団と仙台フィルの合同演奏会のために山形市のやまぎん県民ホールに行ってきました。3.11 の後、「東北は音楽でつながっている」のキャッチフレーズのもと、山形交響楽団と仙台フィルが合同演奏会を開くこととなり、2012年のマーラー:交響曲第2番「復活」(*1)やレスピーギの「ローマ三部作」(*2)などを聴いていますが、今回のお目当ては何と言ってもマーラーの交響曲第5番です。

開演前のプレトークは、西濱秀樹事務局長とこの4月から桂冠指揮者となる飯森範親さんのお二人で、2004年に常任指揮者に就任して以来、これまで山響のレベルアップと活動の発展に取り組んできた飯森さんには一つの区切りとなるもの、とのこと。本日のプログラム、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」より、「前奏曲と愛の死」およびマーラーの交響曲第5番についての解説、それにこの3月で 2nd-Vn の菖蒲三恵子さんと大和ゆり子さんのお二人が定年退職となることなどを紹介しました。
ステージ上に両方のオーケストラの楽団員が登場しますが、いつもの様子とはまるで違い、文字通り「ぎっしり」感があります。ワーグナーの「前奏曲と愛の死」の方は、フルート(3 ピッコロ持ち替え)、オーボエ(3 イングリッシュホルン持ち替え)、クラリネット(3 バスクラリネット含む)、ファゴット(3)、ホルン(4)、トランペット(3)、トロンボーン(3)、テューバ、ティンパニ、ハープ、弦5部となっていますが、その弦がすごい。ステージ左から第1ヴァイオリン(14)、第2ヴァイオリン(12)、ヴィオラ(10)、チェロ(8)、コントラバス(6) という楽器編成です。
政治犯として逃亡中にかくまってくれた恩人の妻と不倫をはたらくワーグナーの悪漢ぶりは「愛の耽溺」を描くこの音楽でも明らかですが、その背景を離れて音楽を聴けば、きわめて集中力に富んだ感情表現に思わず引き込まれます。音楽を専門とする方々には、調性の崩壊まであと少しのところまで行った驚くべき曲とみなされるのかもしれませんが、ワタクシのような素人音楽愛好家には、音楽史上もっとも名高い悪漢ワーグナーの本領を発揮した耽溺の音楽、でも不思議な魅力を持った音楽と言えるのかもしれません(^o^)/
15分の休憩の後、マーラーの交響曲第5番です。楽器編成はさらに拡大され、フルート(4 ピッコロ持ち替え)、オーボエ(3 イングリッシュホルン持ち替え)、クラリネット(3 バスクラリネット持ち替え)、ファゴット(3 コントラファゴット持ち替え)、ホルン(7)、トランペット(4)、トロンボーン(3)、テューバ、ティンパニ、パーカッション(4 シンバル、バスドラム、スネアドラム、トライアングル、グロッケンシュピール、タムタム、むち)、ハープ、それに 14-12-10-8-6 の弦5部です。ふだんからLPやCD等でこの曲を聴いていますが、こんなに鳴り物が多いことにはじめて気づきました。
第1楽章:葬送行進曲。冒頭のトランペットが見事に決まり、オーケストラが動き出します。テンポはややゆっくりめで、威厳ある葬列の歩みのようです。ホール中に響く音楽は、全体として暗めの色調の中に明るい光が差し込むところもあり、単純ではありません。第2楽章:嵐のように激しく、猛烈に。落ち着きのない不安定な激しさがありますが、低音楽器が歌うように奏でられるところなど、実に魅力的です。第3楽章:スケルツォ。ホルン席から1人が立ち、ソロを受け持ちます。田舎風の楽しく美しい音楽ですが、一方でオーケストラが鳴り響くところでは、大編成のパワフルさを爽快に実感するところでもあります。第4楽章:あの有名なアダージェット。ハープと弦楽合奏による、これも一種の耽溺の音楽なのかも。第5楽章:フィナーレ、ロンド。こういう音楽は、やっぱりある程度大きな編成でないと難しいのかもしれません。前に進もうとする力が迫力をもって迫ります。いや〜、良かった〜!

仙台フィルとの合同演奏会なのに、山響の桂冠指揮者への就任や定年退職者の紹介、花束贈呈があったりしたのは、2月の山響第299回定期演奏会が新型コロナウィルス禍のために中止となってしまったためでしょう。菖蒲さんは39年、大和さんは43年の長きにわたり、山響をささえていただいたとのこと。この年月の重みは、しばらく前に定年退職を経験した立場からも痛切に感じられます。宮城県など遠方から来県された皆様には、事情ご賢察のほど、よろしくお願いしたいところです。
ところで、今回のプログラム中には、「山響×仙台フィル合同演奏会2022」として、7月23日(土)15時から、やまぎん県民ホールにて、同じく飯森範親さんの指揮でブルックナーの「交響曲第8番」が予定されているとありました。あの大きな伽藍を見上げるような音楽。これも楽しみ〜!
(*1):
山響・仙台フィル合同による第222回定期演奏会でマーラーの交響曲第2番「復活」を聴く〜「電網郊外散歩道」2012年7月
(*2):
山響・仙台フィル合同演奏会2014でレスピーギの「ローマ三部作」を聴く〜「電網郊外散歩道」2014年7月