サークル日伊文化交流会で「押しばなキャンドルLEDを作りましょう!」の主催企画講座を開きました(2016.9.11) @板橋区
当サークルで 昨年開催の押しばなのコースターに続き今年は 「押しばなキャンドルLEDを作りましょう!」の主催企画講座を 地元板橋で開きました
押しばなの起源は イタリアの植物学者キーニがオーストリアの医官に標本を送ったことです
この日は滝沢馬琴(南総里見八犬伝等の戯作者)が「押し葉帖」を作ったところから始まる「押しばなの歴史」からご説明頂きました
伊東圭介が植物標本の作り方を始め 牧野富太郎(高知県出身の植物学者)が植物の標本を作り始めますが どうしてもセピア色になってしまいます
そこで 金森九郎元東大教授が 原色で標本を作ることに挑みました
講師の先生は この金森九郎氏の奥様が 講師のお子さんが通われていた地元のM幼稚園の園長先生のご友人であったことから この幼稚園で始まった押しばな同好会で「おしばな美術の会」の師範科を卒業後、現在、「暮らしに押しばなをの会」代表の緑川先生です
「ろうそくは 身を減らして 人を照らす」
キャンドルは蝋燭ですが 「洋ろうそく」は 現在は 芯を入れた型の中に 主に石油パラフィンとステアリン酸の蝋を流し込んで 一気に成形し作られています
一方で「和ろうそく」は イグサと和紙からなる芯に ハゼノキの実からとれる木蝋をとかして 塗り重ねて成形します
100万人のキャンドルナイトは 2001年にカナダで始まり 2003年の夏から日本でも始まったそうです
* 追加: 紀元前3世紀のエトルリア(現在のイタリアの一部)の遺跡から 燭台の絵が出土し、この時代にろうそくがあったことは確かだとされています(Wikipediaより)
* * *
机にカエデ(もみじは紅葉した葉の総称です)等の材料を並べて 和気あいあいと習いながらみんなで作りました
昨年は大人数のため 私自身は押しばなコースターを作る時間は取れませんでしたが 今年は自分も座って ゆっくり作ることができて満足満足~(*^^*)
どこから見てもまんべんなくカエデを貼るため LEDキャンドルにまず3つのシールを貼ります
そしてそのシールの下に3つのカエデをボンドで貼り 足もとにコエビ草を貼ってゆきます
ひとつとして同じ葉っぱはなく 押しばなはとても繊細です
りんどうも用意してくださったので いただいた材料をすべて にぎやかに貼ってしまいました~(笑)
次は上から退色防止の押しばな用ボンドを塗ってゆき 乾く間に絵本の読み聞かせ そして記念撮影!!
昨年見本のキャンドルを見てから いつか作ってみたかった押しばなLEDキャンドルを とうとうこの日作ることができました このためにこの講座をセッティングしたので~す(^^)/
また 昨年の東北こどもの村に引き続き 今年は 熊本地震の被害に遭われた子供たちの施設に 募金をさせていただきました
主催企画講座を助成してくださいました東都生協様に 心よりお礼申し上げます
開催のお知らせは こちら
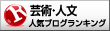 芸術・人文 ブログランキングへ
芸術・人文 ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
当サークルで 昨年開催の押しばなのコースターに続き今年は 「押しばなキャンドルLEDを作りましょう!」の主催企画講座を 地元板橋で開きました
押しばなの起源は イタリアの植物学者キーニがオーストリアの医官に標本を送ったことです
この日は滝沢馬琴(南総里見八犬伝等の戯作者)が「押し葉帖」を作ったところから始まる「押しばなの歴史」からご説明頂きました
伊東圭介が植物標本の作り方を始め 牧野富太郎(高知県出身の植物学者)が植物の標本を作り始めますが どうしてもセピア色になってしまいます
そこで 金森九郎元東大教授が 原色で標本を作ることに挑みました
講師の先生は この金森九郎氏の奥様が 講師のお子さんが通われていた地元のM幼稚園の園長先生のご友人であったことから この幼稚園で始まった押しばな同好会で「おしばな美術の会」の師範科を卒業後、現在、「暮らしに押しばなをの会」代表の緑川先生です
「ろうそくは 身を減らして 人を照らす」
キャンドルは蝋燭ですが 「洋ろうそく」は 現在は 芯を入れた型の中に 主に石油パラフィンとステアリン酸の蝋を流し込んで 一気に成形し作られています
一方で「和ろうそく」は イグサと和紙からなる芯に ハゼノキの実からとれる木蝋をとかして 塗り重ねて成形します
100万人のキャンドルナイトは 2001年にカナダで始まり 2003年の夏から日本でも始まったそうです
* 追加: 紀元前3世紀のエトルリア(現在のイタリアの一部)の遺跡から 燭台の絵が出土し、この時代にろうそくがあったことは確かだとされています(Wikipediaより)
* * *
机にカエデ(もみじは紅葉した葉の総称です)等の材料を並べて 和気あいあいと習いながらみんなで作りました
昨年は大人数のため 私自身は押しばなコースターを作る時間は取れませんでしたが 今年は自分も座って ゆっくり作ることができて満足満足~(*^^*)
どこから見てもまんべんなくカエデを貼るため LEDキャンドルにまず3つのシールを貼ります
そしてそのシールの下に3つのカエデをボンドで貼り 足もとにコエビ草を貼ってゆきます
ひとつとして同じ葉っぱはなく 押しばなはとても繊細です
りんどうも用意してくださったので いただいた材料をすべて にぎやかに貼ってしまいました~(笑)
次は上から退色防止の押しばな用ボンドを塗ってゆき 乾く間に絵本の読み聞かせ そして記念撮影!!
昨年見本のキャンドルを見てから いつか作ってみたかった押しばなLEDキャンドルを とうとうこの日作ることができました このためにこの講座をセッティングしたので~す(^^)/
また 昨年の東北こどもの村に引き続き 今年は 熊本地震の被害に遭われた子供たちの施設に 募金をさせていただきました
主催企画講座を助成してくださいました東都生協様に 心よりお礼申し上げます
開催のお知らせは こちら

























