
この絵は、11cm×13cmの小さな絵で、トイレの柱に貼られていたもの。
メモの1つでしょう。
このメモは、冬の間から目を惹きつけるものがあって、
時々、「今日はこの絵にしようかな?」等とよく思ったものです。
その度に、「いやいや、この絵は春になるまで待っておこう。」と何度も思いつつ、
この絵にぴったりな日がやってきた。
庭に春がおとずれ、庭の花達とコラボする日。
メモなので、太い水色の線は、空間のことを考えていた(思考していた)のではないかと思います。
青い中央の線は、猫を飼っているわたしとしては、
植木鉢にからにゅっと猫が顔が表したように思えたりします。
横の並んだ線は、胴体なのです。
花を描く。
花は、武内の絵では、いつもこの形。
今回の花の絵は、赤色が多く使われ情熱的な感じで、
春のふわふわした感じがしません。
暖かい日に、我家ではタンゴがかかっていました。
どちらかと言えば、タンゴの雰囲気の方がしっくりきます。
この絵は、冬の間に描いたものです。
春のことを思って、描いたのかもしれません。
春の陽気な日には、こちらのアルバムがかかっていました。
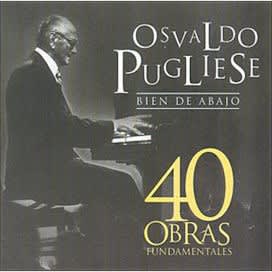
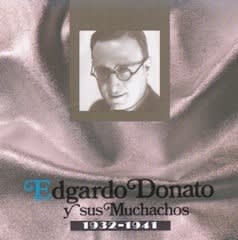
この2枚。
ちょっと古めかしいものだったみたい。
春になって、花が顔を出し、庭の雑草と交じり合って地面が見えなくなってきている様子が、
タンゴの音と合わさって、いい感じだなと。
台所から流れてくる音楽と、春の陽気が感じられる昼下がり、
脳内で視覚と音がミックスされ、意外と春とタンゴは相性がいいのかな?ということを考えていた。
その一時は、エアポケットに入っているような時間でした。
視覚と音がこんぐらがって。
わたしがそんな時間に陥っている間、ずっとアトリエからは絵を描く音がしていました。
このアトリエからの音、これはわたしのとっては日常が続いているという証しなのだなと思うと同時に、
また武内の実存の証しでもある音だと思う。
また、作品と武内は持ちつ持たれつの関係なんだとも。
そして、作品と武内はお互い等価なんだ・・・。
作家と作品の微妙な関係というのをはじめて考えました。
春の昼下がり、哲学者でもないのに「存在理由」とやらに思いがいく。
その音というのは、紙からビシッビシッというものやら、
シュシュと鉛筆が紙の上を走る音。
時折、バリッ、バリッと紙が折れるような音。
この音が、存在理由を物語ってくれるという、変な春。
庭は、ムスカリが満開で、チューリップが咲きはじめたところ。

↑中央のチューリップとムスカリは、昨年掘り起こすのを忘れ、植えっぱなしになっていました。
その部分は、雑草も混ざり合いワイルドな雰囲気があります。
チューリップの曲がり具合も、踊っているような感じなのです。

↑今年はチューリップの球根を購入していなくて、毎年掘り起こしているものだけを植えました。
チラチラと自生しているイフェイオン(ニラ花)が星みたいな花をつけています。
そこらじゅうに生えているので、この花が満開になると、圧巻です。
今は、咲きはじめ。

↑遅めに咲く水仙とイフェイオン。
この星みたいな花は、小さな球根で増えていっているよう。

↑株が大きくなったタンポポとムスカリ。
タンポポを見ると、見てきた刺しゅうの図案を思い浮かべてしまう。
アールヌーボーふうの刺しゅうもあって、西洋ではタンポポは愛されていたのね!と、
納得したり。
葉っぱの形がデザインするとモダンになるのもいいのかも。
植物は、装飾に取り入れられていることが多く、美しいものの源泉なんだなと思います。
左下あたりに、ルピナスの放射状の葉が見えます。

↑日付が違うのですが、このあたりはこんなふう。
それと、夕方に撮った写真です。
タンポポが異様に見事。
葉が若いものは、グリーンサラダに使います。
これは、苦味のあるグリーンリーフのかわりになります。
お浸しにして出したら、「これはやめて。」とダメだしされました。
「そうゥォ?」と言って、夫の分まで食べたりしました。
春、花が咲き、若葉がまぶしくなる頃というのは、
伸び出る感覚を感じることができる季節で、外に向かうような気持ちになれるのがいいなぁと思います。
庭の花が美しいな!と思う時、これを創造した神がいるなら、
なんて素晴らしいのだろうと本気で思います。
春は、わたしにとってそういう季節でもあります。
哲学的になったついでに、図書館でギリシャの哲学者“プラトン”を借りてきました。
はたして、理解できるのか?
大げさなわたしの話しに、最後までお付き合い下さった方、ありがとうございます。






























