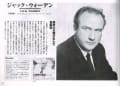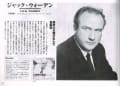『普通の人々』(80)(1981.11.5.)

ロバート・レッドフォードが、監督第一作目で、アカデミー賞の作品、監督、助演男優、脚色賞を受賞しただけあって、とても前評判が高い映画だった。
遅ればせながら見てみたが、正直なところ、あまりピンとこなかった。“普通の人々”とはいうものの、庭付きの結構広い家に住み、マイカーを所有し、週末やクリスマスはゴルフやパーティ…。これらを見せられると、やはりアメリカだなあという感慨を抱かされる。日本の“普通の人々”の生活水準と比べて見てしまうからかもしれないが、どこか違う世界のお話のように見えてしまうのだ。
確かに、この映画が描いた、父(ドナルド・サザーランド)、母(メアリー・タイラー・ムーア)、息子(ティモシー・ハットン)の三者三様の心の葛藤は、形は違えど、どこの家族にも存在するものだろう。けれども質が違う。最近、日本でも、女性の自立が叫ばれているが、欧米に比べればまだまだその足元にも及ばない。
この映画の母親のように、自分の世界を持ち、それを守ろうとする女性像は、まだまだ珍しいものとして映る。また、息子を治療する精神分析医(ジャド・ハーシュ)の存在も、甚だアメリカ的だ。
この映画で描かれている家族が、本当にアメリカの“普通の人々”なのだろうか。だとすれば、中流、あるいは上流階級という地位に溺れてしまった人々の甘えから生じる問題がアメリカの病の素なのか、という疑問が拭い切れない。
この映画の登場人物たちは、みんなどこか甘えているように見える。別に貧しいわけでもないのに、ただ互いに傷つけあって、本音を隠し合って生きている。貧しい家に育った自分から見れば、うらやましささえ感じてしまう。そんな家族だから、何か大きな事件が起これば一瞬にして崩壊してしまうのだ。
アメリカでは、この映画を見た人たちが絶賛したのだという。何のことはない。みんな「自分は中流だ。上流だ」という意識があるから、この映画に感情移入することができたのだろう。
自分としては、同時期に見たドキュメンタリーの『アメリカン・バイオレンス』(81)の方が衝撃的だった。アメリカの病の本当の根っこは、こんな中流家族の問題よりも、もっと恐ろしく、奥深いところにあるはずだ。
などと書いてきて、ちょっと、中流、上流階級に対するコンプレックスが出過ぎたかなと反省。
息子の精神状態を、徐々に解き明かしていくという手法は、謎解きの要素もあって効果を上げている。出演者も、それぞれ、難しい心理表現を見事に行っている。中でも、精神分析医役のジャド・ハーシュが光る。確かに、監督第一作目でこれだけの心理劇を撮ったレッドフォードの手腕はたいしたものなのだろう。
【今の一言】今から40年前、貧乏大学生は、この映画を見てこんなふうに感じたのだ。あの頃から見れば、一見、日本人の生活レベルは向上し、女性の自立も進んだかに思えるが、果たして本当にそうなのだろうかという気もする。


『チャンプ』(79)(再)(1980.11.24.丸の内ピカデリー.併映は『クレイマー、クレイマー』)

とにかく泣かせてくれる映画だ。何と言っても、子役のリッキー・シュローダーがお見事。憎らしいほどうまくて、抱き締めてやりたくなるぐらいかわいい。
例えば、スーツを着てはにかむところ、馬への愛情を示すところ、父親をたしなめるところ、父親との別れ、再会、そしてラストの「チャンプ・ウェークアップ」の叫び…。いやはやまいりましたという感じ。
加えて、父母役のジョン・ボイト、フェイ・ダナウェイのうまさ、アーサー・ヒル、エリシャ・クック・ジュニア、ジャック・ウォーデンという隙のない脇役たち。フランコ・ゼフェレッリの泣かせの演出、デーブ・グルーシンの甘美な音楽…。
子どもが死んでしまう悲劇の映画は多いが、この映画は父親が死んでしまう。それも、ボイトの見事なファイトシーンの後の実にあっけない死。これではまるで『がんばれ元気』のシャーク堀口じゃないか。だが、最後に、この男は初めて本当の意味のチャンプになれたのかもしれない。
それにしても、このシュローダーといい、『クレイマー、クレイマー』のジャスティン・ヘンリーといい、アメリカ映画の子役は皆すごいなあ。
名セリフ「パンツを一人で脱げないのは男じゃないんだぞ」
【今の一言】この映画、最初は当時付き合っていた彼女と一緒に見たのだが、この時はもう振られていたので一人で見たのだった。