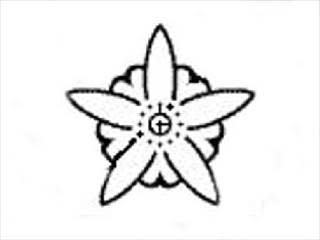焼津市(やいづし)は静岡県中部、志太平野(大井川の扇状地)の北東に位置する市です。高草山などの丘陵部を境に静岡市、西に藤枝市、大井川を挟んで吉田町と島田市に隣接。静岡市との境には「東海の親不知」とも言われる大崩海岸があり、深海湾と呼ばれる駿河湾に面した焼津漁港を中心に発展。「市の木:松」「市の花:サツキ」「市の鳥:ユリカモメ」を制定。 市名は日本神話の【『日本武尊』が東征の途中で地元の賊衆に襲われた時、草薙剣で葦を薙ぎ倒し、そこで賊衆を迎えうち、火を放って難を逃れた。その様相が烈火のように見えた、あるいはその火で葦が焼け燃え盛ったという伝承から「焼津」と命名された。】

遠洋漁業や水産加工業が有名で、中でも漁獲量の多い「マグロ」や「かつお」は、市内の至る所で目にすることができます(笑)
焼津漁港で水揚げされる魚たちは太平洋だけでなく、噴水の水浴びもやっちゃえば、温泉にだって入ります。


そして何と言ってもすごいのは、焼津のカツオは・・・・なんと!!空を飛ぶのです(^^;)・・・なんか焼津市のプロフィールからどんどん遠ざかる。
キャッチフレーズは「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ ~活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津~」
明治22年(1889)、町村制の施行により益津郡焼津村・西益津村・東益津村・広幡村・大井川町が発足。志太郡豊田村・藤枝町・大富村・静浜村・ 相川村・吉永村・和田村・小川村が発足。
1896年、郡制の施行により志太郡・益津郡の区域をもって、改めて志太郡が発足。
1901年、焼津村が町制を施行、志太郡焼津町となる。
1951年、焼津町が市制を施行、焼津市となる。
1952年、小川村が町制を施行、志太郡小川町となる。
1953年、焼津市が志太郡豊田村を編入。
1954年、藤枝町と西益津村が合併、改めて志太郡藤枝町が発足。
1954年、焼津市が志太郡藤枝町大覚寺上・大覚寺下地区を編入。
1955年、焼津市が志太郡東益津村、小川町、大富村、和田村を合併。
1957年、焼津市が志太郡広幡村越後島地区を編入。
2008年、焼津市が志太郡大井川町を編入、現在に至ります。
マンホールには、太平洋を回遊する魚群、荒波から顔を出す「かつお」が鮮やかに描かれています。
中央に「市の木:黒松」と「市の鳥:ユリカモメ」、その周囲を沢山の「かつお」が回遊しています。
「富士山」と「白波」海面をはねる「カツオ」のデザインは、マンホールカードにも採用されました。
プラ汚水枡のデザインは、「富士山」と「波」「カツオ」、「ユリカモメ」です。
昭和27年11月制定の市章は「カタカナの「ヤイヅ」を図案化したもので、市民の協力と伸びゆく市勢を象徴しています。」公式HPより
火消し半纏が描かれたカラー消火栓。背中には焼津市の市章、左右に纏が描かれています。
焼津市の市章がある「温泉」用の小型蓋。
焼津市の消火栓は他に、市章のあるもの、自治体名だけのものなど場所によって色々です。
花沢の里で見かけた「逆止(ぎゃくし)弁」(流体の背圧によって弁体が閉じて逆流を防止するもの)

「東海ガス株式会社」のガス専用蓋。

焼津市マスコットキャラクターはカツオの『やいちゃん』。かたくちいわしとトマトが大好物です。この巨大な『やいちゃん』を撮るにあたっては、焼津市観光協会の皆様の暖かいご協力を頂きました。おかげで貴重な横顔もばっちり、わがままに真剣に付き合って下さいました事、個人の小さなブログ上ですが、心からお礼申し上げます。


「焼津市観光協会」のスタッフの皆さんは、とても温かい心の方達ばかりで本当にほっと寛げる場所です。焼津に行かれた際には是非立ち寄ってみてください(⌒∇⌒)


撮影日:2011年11月&2016年12月&2018年11月
------------------------00----------------------
2017年12月9日、第6弾として全国64自治体で66種類(累計252自治体293種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。焼津市のマンホールカードは焼津駅前にある「焼津市観光協会」で頂けます。

1993年に設置開始されたマンホールには「富士山と荒波」と、日本で一・二の水揚げを誇る「カツオ」が二匹デザインされています。

【焼津市は遠洋漁業の基地として、主にカツオやマグロ、近海・沿岸のアジ・サバなどが水揚げされる焼津漁港を中心に、古くから栄えた港町です。 焼津漁港は、水産業の振興上特に重要な漁港を指定した「特定第三種漁港」のひとつに数えられ、その水揚げ量は全国有数。 特にカツオの水揚げ量は国内一、二を争うほどです。 焼津市のマンホール蓋には、焼津漁港の背景にそびえる「富士山」と「焼津海岸の白波」、そして、海面をはねる活きのいい「カツオ」をデザインしました。 市内には富士山のビューポイントが多数ありますので、マンホール巡りと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。】
訪問日:2018年11月14日