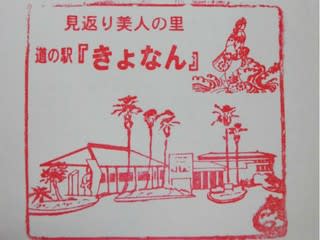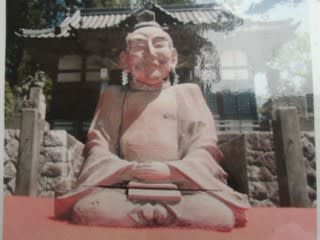南房総市(みなみぼうそうし)は関東地方および千葉県の最南端、房総半島の南端に位置する市です。2006年3月20日に、安房郡富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町が合併し発足しました。館山市、鴨川市、安房郡鋸南町に隣接。市域北部には県下最高峰の愛宕山(408m)をはじめ、富山(349m)など300メートル以上の山が連なり、西側には東京湾、東側及び南側には太平洋と3方を海に囲まれており、海岸線は「南房総国定公園」に指定。
キャッチフレーズは「ひと・ゆめ・みらい 地域で創る魅力の郷 南房総」

南房総市には、新旧いずれの自治体にもデザインマンホールはありません。わずかに、南房総市の市章の規格蓋を一種類見つけただけ、でも有っただけラッキー。

2015年9月16日制定の市章は「7つの地域を広がりのある花びら7枚にたとえて、南房総の暖かい春のイメージを図案化したものです。南房総市の夢と希望が自然と共存し発展する姿を表しています。」公式HPより

自治体章がついた上水道関連の蓋は仕切弁と消火栓の五種、それも上出来。





南房総市イメージキャラクター『みなたん』。白浜地区の海女さんがモデルで、南房総の海の幸と房州びわが大好物。愛されるキャラクターを目指して南房総市をPRしています。

撮影日:2014年5月24日&2019年3月6日
------------------------00----------------------
旧安房郡富浦町(とみうらまち)は千葉県の南、房総半島の南部に位置した町です。 館山市、安房郡:富山町、三芳村に隣接。町域の西は、南北10kmにわたり東京湾に面し、残る三方は山に囲まれた地形。北部には木の根峠を通る東西の山脈、東部には青木山を含み南北に走る200m級の山脈、南部には堂山を通る東西の小丘陵があり、町域北部は数千年前から隆起を繰り返してきた段丘が形成され山が迫る地形となっています。岡本川とその支流は東部の八束地区に河岸段丘を、下流部に平野を作り出して富浦湾に注ぎます。町名は、豊富な海産に恵まれる事を願って新たに定められた「瑞祥地名」。「町の木:ビワ」「町の花:菜の花」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、平郡富浦村・八束村が発足。
1897年、郡制の施行により、平郡・朝夷郡・長狭郡の区域をもって安房郡が発足。
1933年、安房郡富浦村が町制を施行、富浦町が発足(初代)。
1955年、安房郡富浦町と八束村が合併、改めて安房郡富浦町が発足。
2006年、富山町・三芳村・丸山町・和田町・千倉町・白浜町と合併、南房総市となりました。
新しい市庁舎が置かれた富浦町ですが、マンホール類は国土交通省のものがあったのみ。


折角調べた物なので・・昭和53年11月4日制定の町章は「「と」を三つ巴にし、町の名産であるビワの形にしたもの」。

雨の中をせっせと探した挙句が、上水道関連も自治体章の無い完全な規格蓋のみと惨憺たる結果に終わりました。




富浦町は生産量日本一の「房州ビワ」の産地で、季節には多くの直売所が並ぶそうです。富浦駅前の壁には、キャラクターらしき可愛い少女と、房州ビワが情緒的に描かれていました。

前回&今回立ち寄った「道の駅:とみうら」の記念スタンプは「枇杷倶楽部」の文字。

そう言えば、富浦にはもう一ヶ所「道の駅:おおつの里花倶楽部」が有りましたが、スタンプ台が古いと記念スタンプも残念な状態

でもそこで生まれて初めて見た白い極楽鳥花は、感動でした。

撮影日:2014年5月24日&2019年3月6日