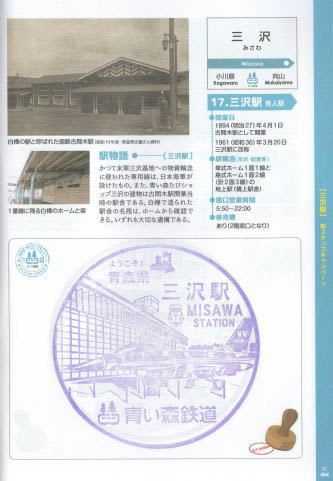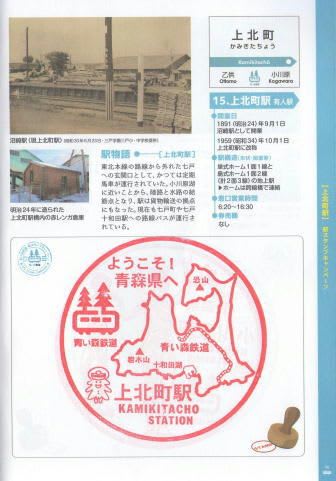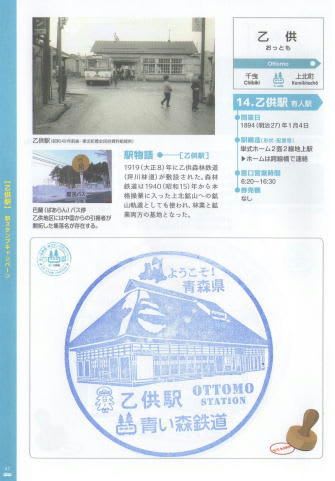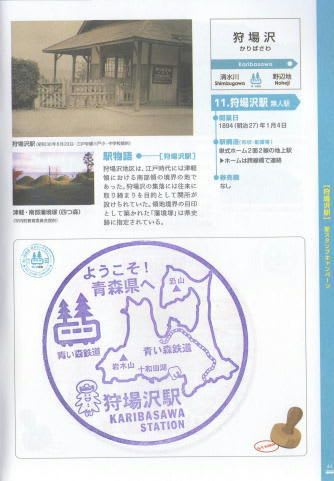【向山駅】

図案は「氣比神社」。
向山駅のあるおいらせ町の北部から三沢市にかけては、江戸時代に盛岡南部藩最大の藩営牧場である木崎野牧がおかれていました。
「氣比神社」は馬をまつる神社として古くから有名です。
【三沢駅】
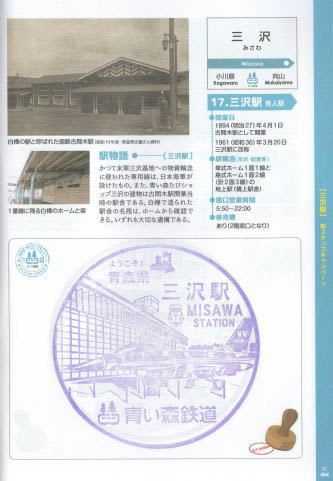
図案は「三沢航空科学館」。
昭和6年、三沢市の淋代海岸を飛び立ったミス・ビードル号が、41時間かけて米国ワシントン州ウェナッチ市に着陸した、北太平洋無着陸横断で有名で、小学生用の地図帳にもその地名が残っています。
戦後は、航空自衛隊が駐屯したり米軍が駐留したりする基地の街でもあります。
「三沢航空科学館」は、三沢市が設置した「大空ひろば」の一角につくられた、航空と科学の県立の博物館です。館内にはミス・ビードル号のレプリカや国産初の旅客機YS-11等が展示されています。
また、3階の展望デッキからは三沢飛行場が一望できます。
屋外の大空ひろばには、航空自衛隊やアメリカ空軍などから借受けている、F-104J、F-1、T-2ブルーインパルス仕様、F-16Aなどの実物が展示されています。
【小川原駅】

図案は「玉代姫・勝世姫像」。
玉代姫・勝世姫は「小川原湖伝説」に登場します。小川原湖伝説の舞台となったのが小川原湖と姉沼です。そこに近い駅が小川原駅です。
しかし、「玉代姫・勝世姫像」の最寄り駅は上北町駅です。
【上北町駅】
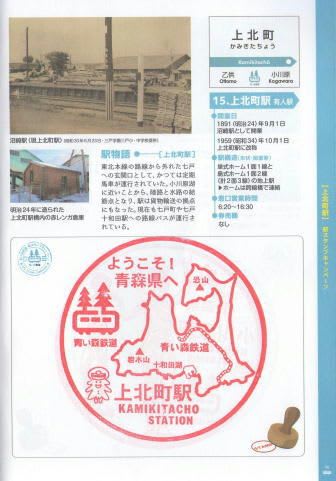
図案は「青森県」。
この図案は、青い森鉄道27駅中、上北町駅・陸奥市川駅・狩場沢駅の3駅だけです。
小川原駅の図案に使われている「玉代姫・勝世姫像」の最寄り駅なのですが、何とも不思議です。
小川原湖は「宝湖」とも言われるくらい水産資源が豊富です。ワカサギ、シラウオ、ハゼ、ヤマトシジミ、ウナギ。こういったものを組み合わせた図案でも良かったのではないかと思います。
【乙供駅】
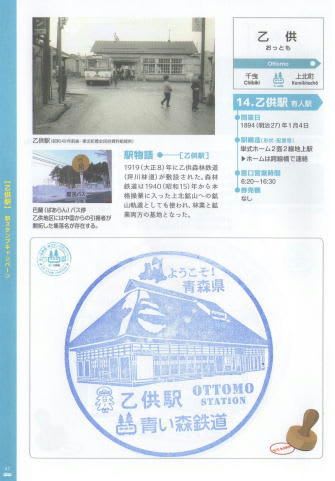
図案は「みどりの大地とロマンの森公園内にある茅葺屋根の『まなか』」
「みどりの大地とロマンの森公園」は、町営の複合公園で展望台や、山ツツジ・桜を楽しめる散策路、科学遊具などが整備されています。
茅葺屋根の「まなか」では、そば餅作りを体験できるそうですが、6~10月の土曜日だけオープンする、東北町特産品販売促進協議会が運営する「農家レストラン まなかのカフェ」が人気です。人気のランチは限定30食だそうですので事前に電話予約をしたほうが確実です。
【千曳駅】

図案は「日本中央の碑保存館」。
昭和24年、千曳駅から2km程離れた石文集落近くの赤川上流で、高さ1.5m程の自然石に「日本中央」と刻まれた碑が発見されました。
これが、12世紀末に編纂された「袖中抄」の19巻に「みちのくの奥につものいしぶみあり、日本のはてといへり。但、田村将軍征夷の時、弓のはずにて、石の面に日本の中央のよしをかきつけたれば、石文といふといへり。信家の侍従の申しは、石面ながさ四五丈計なるに文をゑり付けたり。其所をつぼと云也」とある、つぼのいしぶみ(壷の碑)ではないかと話題になりましたが、発見後、新聞社や学者が調査を行いましたが、本物のつぼのいしぶみであるとする鑑定がはっきりと出されていないのが現状です。
現在、千曳駅から4km程離れた国道4号沿いにある日本中央の碑歴史公園内の「日本中央の碑保存館」の中にこの石碑は保存されています。
【野辺地駅】

図案は「野辺地防雪原林と青い森701系車両」
明治24年、東北本線が全通しましたが、当初の地吹雪対策は線路沿いに雪よけの板塀や雪覆いの設置でしたが、強風で倒壊したり蒸気機関車の火煙で延焼したりして用をなさなかったそうです。
そこで、後に東京帝国大学の教授となり日比谷公園や明治神宮の森など、全国数百の公園・庭園の設計、改造、提言にかかわり、「日本の公園の父」ともいわれた、本多静六の進言と指導を受けて、地吹雪対策として明治26年に水沢駅・青森駅間に41ヶ所の造林が一斉に行われました。これが最初の鉄道林です。
昭和33年、当時の日本国有鉄道は、日本の鉄道に関する歴史的文化的に重要な事物等を保存、継承するための制度として、鉄道記念物として指定する制度をつくりました。
昭和35年、鉄道記念物第14号として「野辺地防雪原林(野辺地駅付近)」が指定されました。当初あった41ヶ所の中からなぜここが選ばれたのかは定かではありません。
【狩場沢駅】
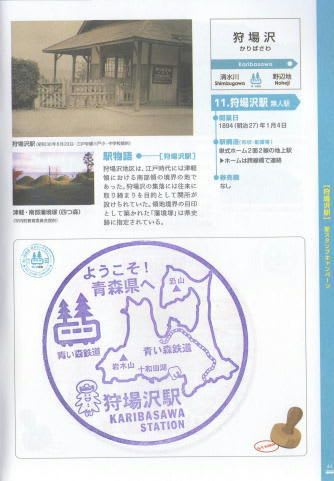
図案は「青森県」。
ここも何も無いわけではありません。
狩場沢駅がある平内町は江戸時代は津軽藩領、隣の野辺地駅がある野辺地町は南部藩領だったため、南部領と津軽領の境界の目印として旧奥州街道(現在の国道4号)沿いに築かれた土盛りの藩境塚が、駅から3km程の所にあります。塚の直径は約10m高さは約3.5m津軽、南部にそれぞれ2基ずつあることから「4つ森」とも呼ばれています。当時は藩境から離れたところにそれぞれの番所が設けられていました。
現在はここに、「馬門御番所」と「高札」が復元されています
これらを図案にしても良かったのではないでしょうか。
つづく