最近、データジャーナリズムというのがあるそうだ。
公開されているデータを読み解くジャーナリズムとのことだ。
データジャーナリズム――世界に広がる「データからニュースを発見する」挑戦
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130623-00010000-wordleaf-sci
によると・・・
今回の東京都議会選挙は、まさに、朝日、読売が、このデータジャーナリズムに移行せざるを得なくなった記念日となるだろう。
朝日新聞が
共産躍進、護憲・反原発の訴え届く 低投票率も影響か
http://www.asahi.com/politics/update/0623/TKY201306230252.html
という記事を載せた
(ただし、上記の判断は、共産党の判断であり、朝日は、都議選投票率43.50% 過去2番目の低さの記事の中で、「安倍政権の経済政策や脱原発、憲法改正の是非などの論戦は、有権者に十分届かなかったとみられる」と解釈している)。
また、読売新聞は、
という記事の中で「橋下共同代表の「慰安婦」「風俗」を巡る発言で苦戦し2議席にとどまった」と記載している。
これらに対し、
2013年東京都議選の簡単なデータ分析
http://www.huffingtonpost.jp/taku-sugawara/2013_1_b_3488128.html
では、公開された都議会選挙の結果をもとに、上記のことが、妥当かどうか検証している。
生データが公開されてしまうと、データをもとに、その論旨が言えるかどうかを評価できてしまう。
いままでの新聞は、公開されているデータを加工して(元データは隠して?)載せていた。それゆえに歪曲した解釈も載せることが可能となっていたが、今後、このようにデータが公開され、そのデータを元にネットで様々な批判がされるようになると、朝日、読売も、早晩、いままでのような記者が勝手に解釈した記事を載せるのではなく、ビッグデータに基づいたデータジャーナリズムに移っていかざるを得なくなるだろう。
つまり、公開されているデータの所在を明示して、そのデータをデータサイエンスに基づき分析した上で、自分の主張をしなければならなくなってくるだろう。そうしなければ、記事は信用されなくなる。
マスコミも、データサイエンティストとビッグデータ市場に組み入れられて行かざるを得ないかもしれない。
公開されているデータを読み解くジャーナリズムとのことだ。
データジャーナリズム――世界に広がる「データからニュースを発見する」挑戦
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130623-00010000-wordleaf-sci
によると・・・
今回の東京都議会選挙は、まさに、朝日、読売が、このデータジャーナリズムに移行せざるを得なくなった記念日となるだろう。
朝日新聞が
共産躍進、護憲・反原発の訴え届く 低投票率も影響か
http://www.asahi.com/politics/update/0623/TKY201306230252.html
という記事を載せた
(ただし、上記の判断は、共産党の判断であり、朝日は、都議選投票率43.50% 過去2番目の低さの記事の中で、「安倍政権の経済政策や脱原発、憲法改正の是非などの論戦は、有権者に十分届かなかったとみられる」と解釈している)。
また、読売新聞は、
という記事の中で「橋下共同代表の「慰安婦」「風俗」を巡る発言で苦戦し2議席にとどまった」と記載している。
これらに対し、
2013年東京都議選の簡単なデータ分析
http://www.huffingtonpost.jp/taku-sugawara/2013_1_b_3488128.html
では、公開された都議会選挙の結果をもとに、上記のことが、妥当かどうか検証している。
生データが公開されてしまうと、データをもとに、その論旨が言えるかどうかを評価できてしまう。
いままでの新聞は、公開されているデータを加工して(元データは隠して?)載せていた。それゆえに歪曲した解釈も載せることが可能となっていたが、今後、このようにデータが公開され、そのデータを元にネットで様々な批判がされるようになると、朝日、読売も、早晩、いままでのような記者が勝手に解釈した記事を載せるのではなく、ビッグデータに基づいたデータジャーナリズムに移っていかざるを得なくなるだろう。
つまり、公開されているデータの所在を明示して、そのデータをデータサイエンスに基づき分析した上で、自分の主張をしなければならなくなってくるだろう。そうしなければ、記事は信用されなくなる。
マスコミも、データサイエンティストとビッグデータ市場に組み入れられて行かざるを得ないかもしれない。












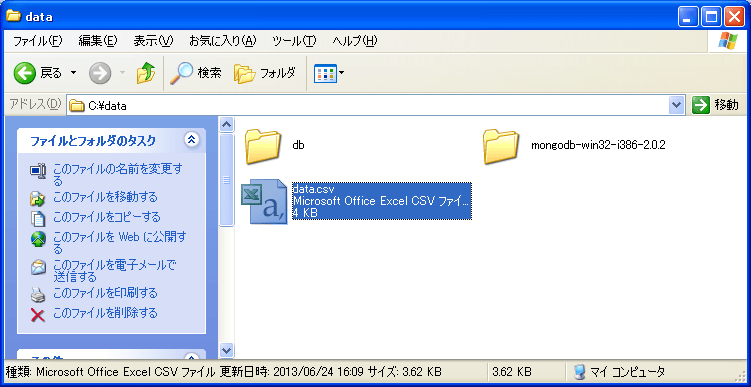
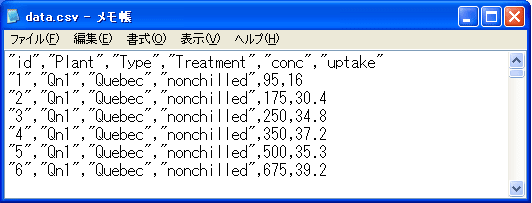
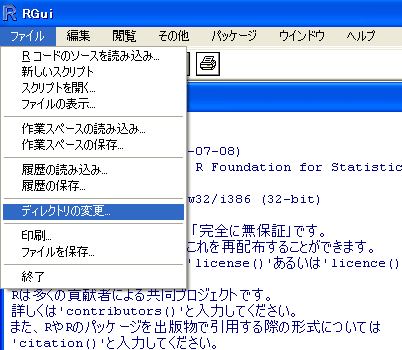
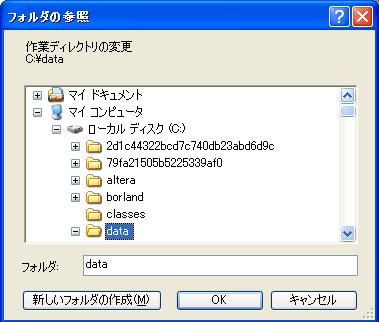
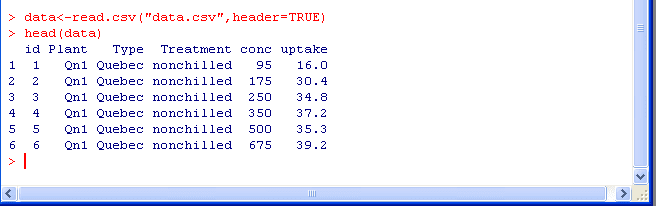
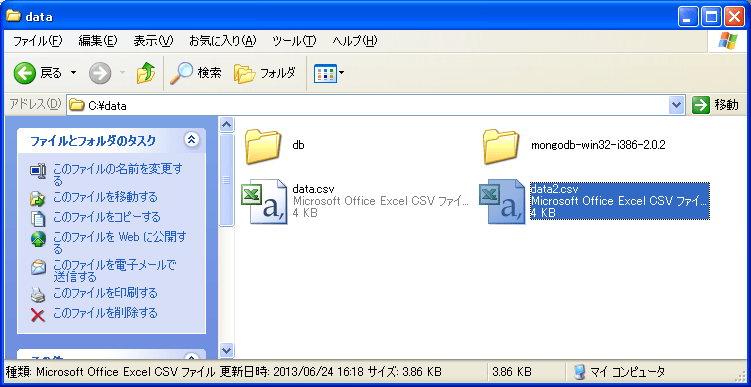
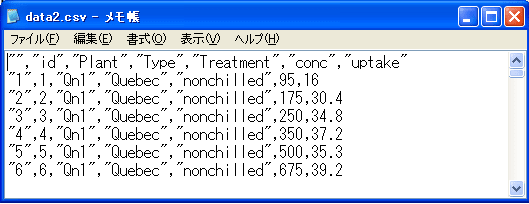
 ウィリアムのいたずら @xmldtp
ウィリアムのいたずら @xmldtp



