令和3年2月13日(土)
朧月夜 : 月 朧

朧に霞んだ春の月、薄絹でも垂れたような柔らかな
甘い霞んだ感じである。 朧夜は、その月の在る夜。

春のぼんやり霞んだ月の夜。名残の寒さと生暖かい
陽気を、綯い交ぜたにした季語。

中日春秋より、
2月12日は作家、司馬遼太郎さんの命日「菜の花忌」
著作の「菜の花の沖」にちなみ、名付けられた。
今朝(2月13日)の中日新聞のコラム「中日春秋」に
作家司馬遼太郎さんと半藤一利さんの「朧月夜のエピソ
ード」の記述があったので紹介したい。

『菜の花畠に入日薄れ―。唱歌「朧月夜」を歌う声に、
司馬遼太郎さんは「それ、何の歌だ」と尋ねたそうだ。
菜の花が大好きな司馬さんのためにと、歌ったのは作家
半藤一利さんである。小学校に通う代りに図書館に入り
浸った所為で、有名な唱歌を知らなかったとは、長い付
き合いの半藤さんの見立てだ。人がコーヒーを一杯飲む
間に司馬さんは、300ページほどの本を三冊読み終え
ていた。
唱歌の話に片りんが見える「神がかった」読書量と力、
取材や知識への熱意の人であったそうだ。
「資料を「読んで読んで読み尽くして、その後に一滴
二滴出る透明な滴を書くのです。」という言葉とともに
半藤さんが書き残している。
司馬さんが亡くなり二十五年経った。12日は命日「菜
の花忌」である。「半藤君、俺たちは相当責任がある。
こんな国を残して子孫に顔向け出来るか」。

没する一年前に語ったという。憂えていたのは、ひたすら
金儲けに走り、金儲けに操られる様な社会だった。
「足るを知る」の心が大切になると、世に語りかけようと
していた。憂いは過去のものになっていないだろう。
災害、経済の混乱、疫病の流行、、、、、。
司馬さんなら何を語るかと思う事も多い、四半世紀である。
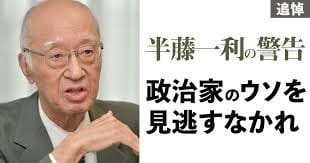
憂いを伴にし、後を継ぐように昭和を書いてきた半藤さん
も他界した。著作の中に残された滴に、声を探したくなる
「菜の花忌」である。』 (中日春秋より記事を引用した)
今日の1句
どのみちも混沌として朧月 ヤギ爺
みち(道、路、径)
道 : 道路等、物事の方法、道すじ
路 : 経路等、行き方、手段
径 : 直径等、真直ぐ伸びた道










