
発達トラウマ障害(DTD)=愛着障害の子ども。ヴァン・デ・コーク教授の The body keeps the score : brain, mind, body in the healing of trauma 『虐待されたら、意識できなくても、身体は覚えてますよ : 脳と心と身体がトラウマを治療する時どうなるか?』p.165,第4パラグラフから。
性的虐待をされた娘たちは,正常な発達とは全く異なる発達をすることになります。この娘たちは男友達も女友達もいませんし,それは,この娘たちは自分も人も信頼できないからです。この娘たちは自分のことが大嫌いですし,この娘たちの身体も自分の身体を攻撃するくらいですから,悪いことで目立ったり,黙り込んでしまったりするわけですね。性的に虐待されてきた娘たちは,通常の,憧れによって衝き動かされた,くっついたり離れたりするゲームの中では,育っていきません。このゲームをやってれば,ストレスに晒されても,冷静さを失うことはありません。他の子ども達も,性的に虐待されてきた娘たちと関わりたがらないのが普通でしょ。性的に虐待されてきた娘たちは,あまりにも風変わりなんですね。
ですから,性的に虐待されてきた娘たちは,誰も信頼していない上に,自分のこと,人のことも無知のままです。しかも,自分の気持ちを整える場も,心構えもありません。騙されやすい条件が,思いがけず? そろってしまいます。










 おとぎ話の鈴鳴らし 自然の力や神の意思を感じていたい。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p91の第2パラグラフ......
おとぎ話の鈴鳴らし 自然の力や神の意思を感じていたい。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p91の第2パラグラフ......

 反抗的人間 Noとハッキリ言う≪市民的勇気≫ 先日このブログでご紹介しました、岡田尊司さんの『子どもが自立できる教育』の一節。「ヨーロッパの教育......
反抗的人間 Noとハッキリ言う≪市民的勇気≫ 先日このブログでご紹介しました、岡田尊司さんの『子どもが自立できる教育』の一節。「ヨーロッパの教育......
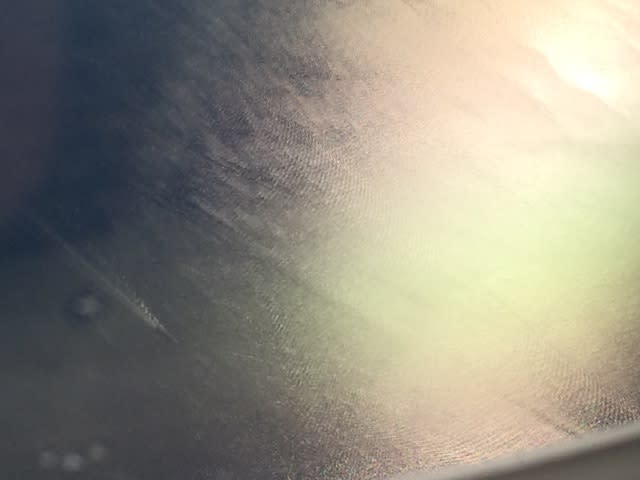
 反抗的人間 Noとハッキリ言う≪市民的勇気≫ 先日このブログでご紹介しました、岡田尊司さんの『子どもが自立できる教育』の一節。「ヨーロッパの教育......
反抗的人間 Noとハッキリ言う≪市民的勇気≫ 先日このブログでご紹介しました、岡田尊司さんの『子どもが自立できる教育』の一節。「ヨーロッパの教育......




