<はじめに、を読んで>
「本を書くとき一番最後にきめることは、最初に何を書くかである」という書き出しで始まる本書の「はじめに」が素晴らしい。前に読んだ『知の逆転』もそうだったか、書き出しがいいと読むテンションも上がる。
精神科医である著者が、自らの患者を物語という視点で描き出す。
ある機能の不足は、果たして単なる喪失なのか、それとも別の理由があるのか。
興味深いテーマです。
<読後>
オリヴァー・サックスの『妻を帽子とまちがえた男』を読んだ。
表題は、視力には何の異常もないのに、見たものを全体として捉える能力が欠落しているがために、妻を帽子とまちがえた男から来ている。この他に、知的障害があるにもかかわらず20桁の素数を言い当てる双子や、自閉症にも関わらず素晴らしい絵を描く子供などが登場する。
著者は脳神経科医で、登場する人々は実在する彼の患者だ。著者は彼らの障害を興味本位で見せびらかすのではなく、また同情するのでもなく、彼ら一人一人の物語として著していく。
数多くある人間の能力の一部が欠落するとはどういうことなのか。また、その逆で一部が異常に発達するとどうなるのか。さらに、その両方が混在する場合もある(冒頭の双子は床に散らばったマッチ棒が111本あると瞬時に把握し、一瞬で因数分解までやってしまうが、彼らは四則計算ができない)。
人間の能力、主に脳に起因する様々な...不思議な現象に驚く。
これまで、霊感の一種かと思っていた第六感なるものが科学的に証明されていることにも驚いた。つまり、自分の肢体がどの位置にあるか目をつむっていてもわかる感覚だそうだ。この第六感を失った人は、目で体の各部分を見ていないと歩くことも物をつかむこともできない。
人間の不思議な世界の扉を開けてくれる本だった。
「本を書くとき一番最後にきめることは、最初に何を書くかである」という書き出しで始まる本書の「はじめに」が素晴らしい。前に読んだ『知の逆転』もそうだったか、書き出しがいいと読むテンションも上がる。
精神科医である著者が、自らの患者を物語という視点で描き出す。
ある機能の不足は、果たして単なる喪失なのか、それとも別の理由があるのか。
興味深いテーマです。
<読後>
オリヴァー・サックスの『妻を帽子とまちがえた男』を読んだ。
表題は、視力には何の異常もないのに、見たものを全体として捉える能力が欠落しているがために、妻を帽子とまちがえた男から来ている。この他に、知的障害があるにもかかわらず20桁の素数を言い当てる双子や、自閉症にも関わらず素晴らしい絵を描く子供などが登場する。
著者は脳神経科医で、登場する人々は実在する彼の患者だ。著者は彼らの障害を興味本位で見せびらかすのではなく、また同情するのでもなく、彼ら一人一人の物語として著していく。
数多くある人間の能力の一部が欠落するとはどういうことなのか。また、その逆で一部が異常に発達するとどうなるのか。さらに、その両方が混在する場合もある(冒頭の双子は床に散らばったマッチ棒が111本あると瞬時に把握し、一瞬で因数分解までやってしまうが、彼らは四則計算ができない)。
人間の能力、主に脳に起因する様々な...不思議な現象に驚く。
これまで、霊感の一種かと思っていた第六感なるものが科学的に証明されていることにも驚いた。つまり、自分の肢体がどの位置にあるか目をつむっていてもわかる感覚だそうだ。この第六感を失った人は、目で体の各部分を見ていないと歩くことも物をつかむこともできない。
人間の不思議な世界の扉を開けてくれる本だった。













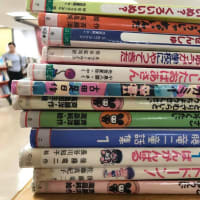






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます