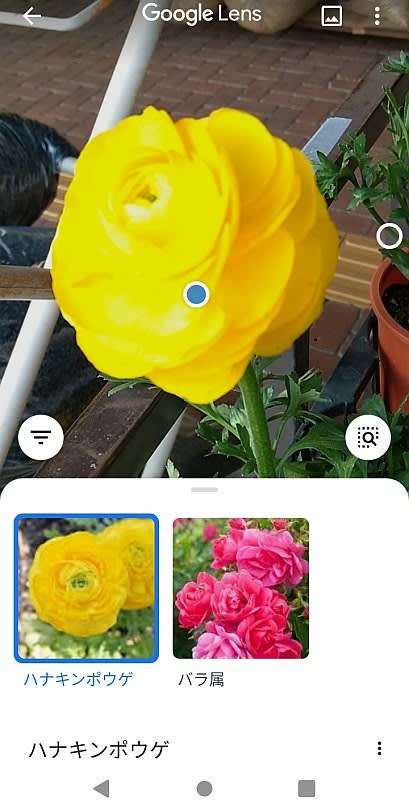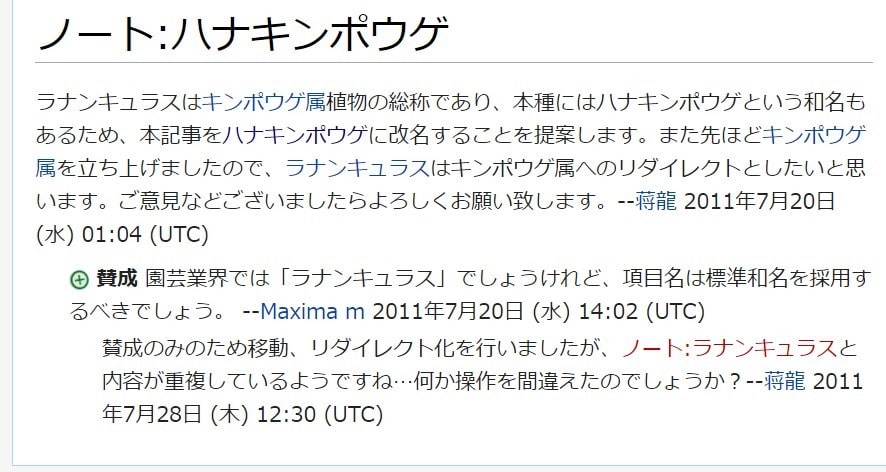2,3日前にやった 「樹形クイズ」のつづきになりますが、これは なんでしょう? (^^)/

これは 樹名板によると「コブシ」 です。確かに 花芽がたくさんついています。

こういう去年できた果実が枝に残っていれば、これはまちがいなく コブシ ですね 。
でも いつも 果実が残っているとは限りません。
花芽を見て コブシか、モクレンか、分かるんでしょうか?
コブシ

やはり コブシですが、先ほどのこぶしと比べ、かなり樹形が異なります。

枝がまっすぐ上に伸びています。

花芽は こんなふうです。
コブシの特徴は 花芽のときは その毛皮のコートを剥がしてみないと分からないところに隠されています。花芽といっしょに 葉を一枚だけ一緒につけているのです。(画像は 毛皮のコードを剥がしてないので よく分かりませんが m(_ _)m)
ハクモクレン

これは ハクモクレンの花芽です。(デンパーク(安城市)にて撮影)
どうです? 先ほどのコブシの花芽とのちがい、分かりますか?

これが上の花芽の樹形です。モクレン科(マグノリア)なので よく似ています。
第一、モクレンを増やすのに 「コブシ」の苗を台木として選び、モクレンの枝を接ぎ木する方法がポピュラーというくらいですから (^_-)-☆
シデコブシ

芝生広場にいっぱい植わってるのは シデコブシ です。
コブシとシデコブシの違い、分かりますか?
そういわれると、私もよく分からないのですが・・・
コブシのほうは幹が太く10mを超えるほど樹高が高くなります。
そして、上方の枝にたくさんの花を咲かせます。

たいして、シデコブシの樹高は5mぐらいまでで、まれに根の際からたくさんの幹が出ているものもあります。
シデコブシは大きくなりすぎないということから、庭木としても用いられています。

シデコブシは 日本の固有種で、しかも岐阜と三重と愛知の特定に地域にしか自生がありません。絶滅危惧種です。
花弁の数が多く そのかたちが 紙垂(しで)のようなので シデコブシ と呼ばれるようになりました。
これは コブシ? モクレン?

安城市の とある神社にあるモクレン科ですが、これはコブシでしょうか? それとも モクレンでしょうか?
実は コブシとモクレンの花の咲き方には もうひとつ違いがあって、ハクモクレンはみな首を持ち上げ上を向くが、コブシは枝の方向に沿って咲くので、上向きだけでなく、横向き(右向き・左向き)や斜め下向きなど咲く方向がバラバラになる、という違いがあります。
そういう目で見ると、これはみな上を向いているようなので ハクモクレンでしょうか?

蕾の外側に さらに厚い毛の殻がついているんですね

毛皮のコート?

毛皮のコート 2枚重ね?
スズメバチの巣

となりのやはりハクモクレンと思われる木の枝についていたスズメバチの巣です。

匠(たくみ)の技ですね (^^♪