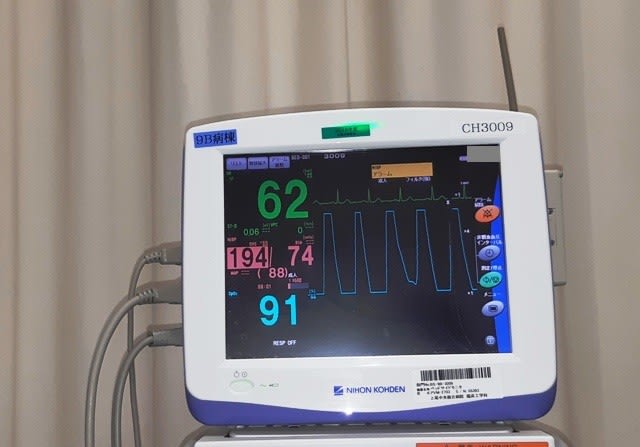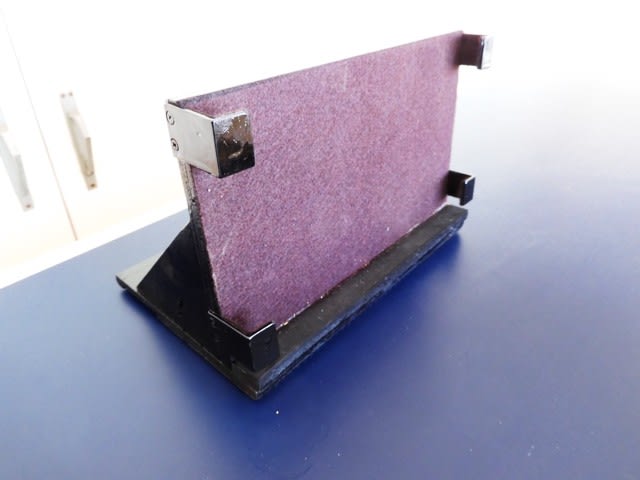キャンピングカーは狭い空間を如何に便利に使うか工夫されている。
特に収納庫は食器や食料品や調理器具など、生活に必要な物の保管に欠かせない。
収納庫から物を取り出すたびに扉の開け閉めを行うが、取り付けたガスダンパーで開けた扉を静止させている。
ダンパーは走行中の振動で扉が開かない役目も持っている。
そのダンパーがヘタって扉を開けた時に静止出来なくなり、手で押さえながら取り出していた。
その為、両手が使えなく不便していた。
旅に出る前に新しいダンパーと取り換える事にした。
取り外した古い物と取り寄せた新しいダンパーだが、見た目は変わらない。

ここはベッドで、この下が収納庫になっている。
ベッドのマットを持ち上げると、そこは大きな収納庫になっている。
沢山の物が収納でき重宝しており、開け閉めの回数も多い。

開けるとこの様になっていて、このダンパーを取り換えた。

椅子の下も収納庫になっている。

これも静止できなくて不便していた。
取り換えるとこの様にマットが持ち上がった状態で停まる。

左右両側に天袋が付いているが、こちら側の扉が停まらなくなっていた。

新しいダンパーに取り換えた。

気なっていた所が一つ減った。
まだ気になるところが有り、出掛ける前に直しておきたい。
この車も後期高齢(車)である。
色々な所が弱ってきても不思議ではない。
労わりながら乗っている。