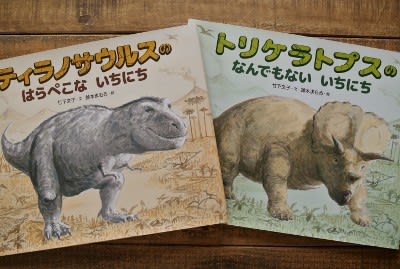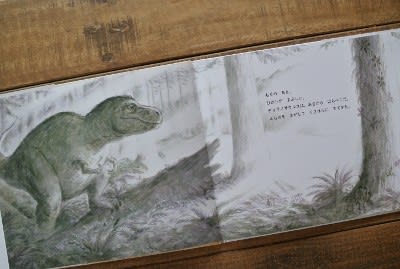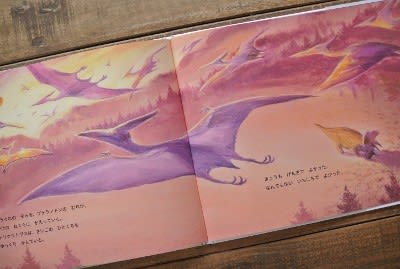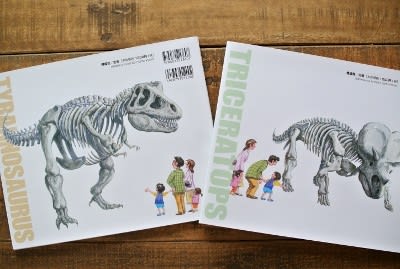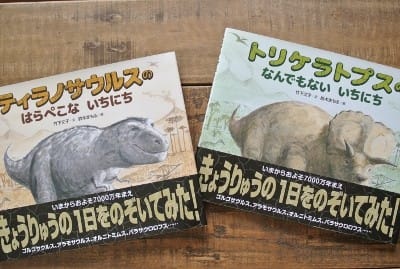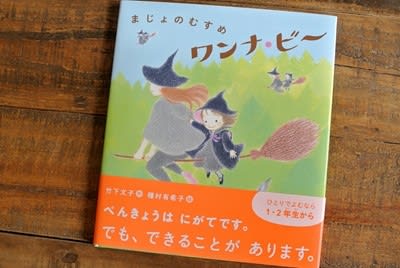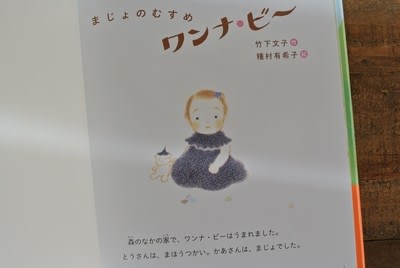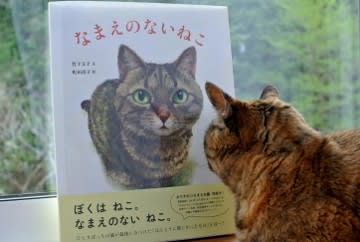新刊のお知らせです。
グリム童話『ねこのおひめさま』(あかね書房 2021年11月刊)
絵は林なつこさんです。
え~、グリムにそんな話あったっけ? とお思いの方、ごもっとも。「ねこのおひめさま」というのは、わたしが勝手につけたタイトルです。
原題は「かわいそうな粉ひきの若いものと小猫」(金田鬼一訳 岩波文庫#KHM106)という、長い上にまことにぱっとしないもので、これは絶対タイトルで損をしている…ということを、2年くらい前のブログ(ここの後半)に書きました。
たまたまそれを目にした編集者KTさんが「面白いです!」と反応してくださったのが始まりで、こちらも凝り性だもんで、原典を読むためにドイツ語辞書まで買い、しばらくはグリムの沼にはまりっぱなし。
そこからあれやこれやありましたが、最終的に、1話読み切り80ページの幼年童話シリーズ、という形に落ち着きました。
粉ひきの親方に「いちばんいい馬をみつけてきた者に水車小屋をゆずる」と言われ、旅に出た三人の若者。
年下のハンスは、上のふたりに置いて行かれてしまい、森の中で出会った三毛猫にさそわれて、猫のお城で働くことに…。
簡単にまとめて言えば「猫だらけ」で「逆玉の輿」のお話。グリム童話の中で、猫がこれだけたくさん出てくる話は他にありません。
発端は、昔話によくある「三人旅」のパターン。三人いれば三番目が成功する、というのがお約束。森の中で助力者に出会うのも、これまたお約束。
編集のKTさんは、ご自身が三人きょうだいの長女ということもあり、どうしていつもいつも末っ子ばかり幸せになるのかと、つねづね不満に思っていたそうですが、これは決して上の子がダメという意味ではなく、長子相続制度の下では、立場の弱い末っ子が家を出てチャンスをつかむ話が喜ばれた、ということ。また、一度目、二度目は失敗しても、三度目で成功する、というたとえでもあります。
そうそう、「家を出る」も大切なポイント。成長した子どもが、親と家(この話では親方と水車小屋)から離れ、広い世界に出て、知らない人に会い、さまざまな経験をして、幸せをつかむ…という筋書きは、昔のドイツだけのことではなく、現代の日本の子どもたちにもきっと通じるものがあるはずです。
最初はいかにも頼りなげなハンス君が、お城で七年間働くうちに鍛えられて、いつのまにかしっかりした若者に成長していく。そんなハンスを「拾って」きた三毛猫って、先見の明があるのか、それとも人材育成能力にすぐれているのか、いずれにしてもただの(大事に守られているだけの)お姫様じゃないわけで、そのあたり、いろいろと深読みしていくのも面白い。

イラストの林なつこさんは、ハンスとお姫様、それにお城の召使い猫たちを、それぞれ魅力的に描きわけてくださっただけでなく、衣装から持ち道具までこまかく時代考証もしていただき、たいへん見ごたえのある絵になりました。
幼年童話はイラストの点数が多くて画家さんは大変なのですが、楽しんで描いていただくことができて嬉しいです。ありがとうございました。
グリムといえば、白雪姫とか、赤ずきんとか、ヘンゼルとグレーテルとか、オオカミと7匹の子ヤギとか…昔からよく知られている話が思い浮かぶでしょう。一方、それほどメジャーでないけれど面白い話もまだまだいっぱいあるのですが、それらはたいていぶあつい「グリム童話集」でしか読むことができず、字も小さいし挿絵も少なく、わたしみたいな超本好きの昭和の子どもならともかく、いまどきの小学生は手に取る機会も少ないと思います。
そこで、200篇以上あるグリム童話の中から、あえてマイナーな話を発掘し、原典をわかりやすい言葉や表現で語り直し、カラーのイラストも多めにいれて、低学年からひとりで読める本にしてみましょう…というのが、この <グリムの本だな>というシリーズのコンセプト。
いまのところ、あと2冊はすでに決まっているものの、全3巻では「本棚」というより「本立て」なので(笑)…もうちょっと続くといいなあ、と思っているところ。
グリム童話は「本当は怖い」とか「残酷」とか…ことさらダークな面が注目されることもありますけれど、日本でいえば江戸時代後期に出版された本ですから、現代の人の感覚と多少ずれがあるのはしかたがない。本質はポジティブで、善悪のはっきりした健全なもの。いつの時代も、聴き手である子どもたちを応援し、勇気づけ、背中を押してやるのが、昔話本来の役割であり、力であると、わたしは思っています。