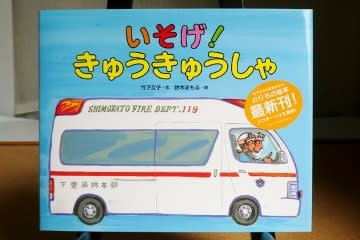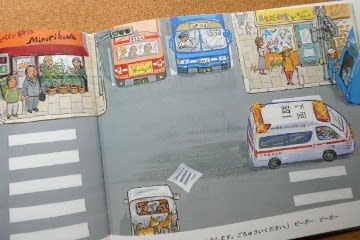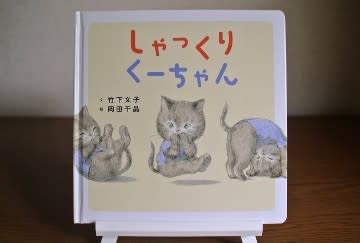『風町通信』が文庫になりました!
ポプラ文庫ピュアフルから、9月1日発売です。
これはね、なつかしい本です。
ポプラ社の編集者さんが「子どもの頃から大好きな作品」とのことで、つまり、それくらい古い!
書いたのは、1980年から1982年にかけて。
えーと…37年前??
月刊誌の連載で、毎月4枚、1600字前後の掌篇連作。
そう、原稿用紙にペンでちまちまと書いていた時代でした。
わたしは学生の頃から「おしごと」として童話や絵本のテキストを書いていて、それなりにまとまった作品はできたし満足感も得られたけれど、このスタイルではじきに行き詰まるだろうな、ということが、20歳くらいでなんとなく見えてしまっていた。
「風町」を思いついて書き出したとき、目の前に誰も歩いていないまっさらな道がひらけたようで、ああ、そっちへ行っていいんだ!と、ものすごく嬉しくてわくわくしたのを覚えています。

連載当時のイラストは飯野和好さんでした。
いまはすっかり時代劇のヒトになっておられる飯野さんだけど、かつては「anan」みたいなファッション誌にペン画で無国籍風の不思議でおしゃれなイラストを描いていらしたのです。
その頃わたしは、東京で私鉄沿線の変なアパート(鉄筋コンクリートだけどマンションと呼べるほど立派ではない)に住んでいて、そこがときには「風町」だったり、そうじゃなかったり…
話の中に出てくるのも、実在の人や物や場所だったり、そうじゃなかったり…
野外音楽堂や、彫刻のある橋や、植物園などは、はっきりしたモデルがあったけれど、夜中に柵を乗り越えて侵入したなんてエピソードは、はたして事実だったのかどうか。
フィクションとして書いたのに、いつのまにか、まるで本当にあったことのように記憶のほうが変化してしまったのかもしれません。
連載をまとめたものが、1986年に偕成社から単行本として出版されました。
その後、1990年にデザインを変えた新装改訂版が出ましたが、それだって27年も前の話…
子どもの頃に読んだ人が大人になっていても当然ですよね。

初版本(右)と、ひとまわり小さい改訂版。
まったくテイストの異なるデザインになったのは、他の2冊(『星占い師のいた街』の改訂版と『窓のそばで』)と揃えたから、だったかな。
とにかく、いろいろ思い出の尽きない本であります。
今回、あらためて読み返したら、音楽はレコードだし、コーヒーは手回しミルでひいてるし、電話は携帯どころかコードレスでさえなく、駅の改札口には駅員さんが立っている。(切符にはさみを入れる、なんて言葉、もうみんな知らないでしょう?)
まあ若いうちからレトロ趣味ではあったけれど、それにしても、ずいぶんいろんなことが変わったのねえ…と感慨深いものがありました。
だけど、同時に、全然変わってないじゃないか! とも思う。
いまのわたしの好きなものは、あの頃から好きだったもので、苦手なものは相変わらず苦手なままで、たぶんそれはこの先もずっと変わらないでしょう。
文庫にしていただくことが決まって、すこし手を入れました。
全体に表記を見直したほか、以前から気持ちの中でどうしてもひっかかる点のあった1篇については、ちょっと思い切った修正をしました。
それと、連載終了後に書いた作品(単行本未収録)を3つ、後半部分に追加しました。
これから初めて読んでくださる方もいることだし、たぶん修正できる最後のチャンスなので、過去ではなく現在のわたしの感覚で、納得のいく形にしようと思いました。
前のほうがよかった! と思われたら、ごめんなさいです。
偕成社版はもう中古でしか手に入らず、この先も重版はありませんので、お持ちの方は、どうぞ大事にしてください。
文庫版カバーと本文イラストは、初見寧(はつみ・ねい)さんです。
きわめて繊細な、ミニチュア細工のような趣のある絵は、風町を描くというより、風町のどこかにひっそり飾られているのにふさわしく、この世界にまだ作者の知らない小路や店があることを教えてくれます。
厳しいスケジュールにもかかわらずこころよく応じてくださった初見さん。
「ほんとは自分だけの秘密の部屋にしまっておきたい」と言いつつ、文庫化をすすめてくださった編集者さん。
そして、37年前のわたしにこの作品を書かせてくれた<ゴーシュのモトコさん>にも、心からの感謝を。
ありがとうございました。
ポプラ文庫ピュアフル9月の新刊4冊のうち、2冊ぶんの応募券をあつめると、ポストカード4枚セット(うち1枚は『風町通信』の扉絵です!)を応募者全員にプレゼント! という特典があります。
ほかの3冊も、それぞれに個性的で素敵な作品ですので、ぜひぜひご応募くださいませ。

詳しくは帯をみてね。
東京・池袋のジュンク堂3Fで、カバーイラストのパネル展開催中。9月30日まで。
著者サイン本も置いていただけるそうです。
文庫本って、余白があまりないし、サインすると開き癖がついちゃうのが困るけど…
1冊ずつぜんぶ違う言葉を書いたので、おみくじみたいになってしまいました。
そして…
もう10年以上前からたくさんの復刊リクエストをいただいている『木苺通信』。
諸々の事情から、写真の入った単行本という方向の復刊は望みなしの状態が続いており、申し訳ありません。
『木苺』は『風町』の続編ではありませんが、この2冊は兄弟か姉妹のような本なので、これを機に『木苺』も文庫で復活できたら、いいなあ!
というのが、七夕の短冊に書いたおねがいごと。
サンタさんへの手紙にも書こうっと。
いつか良いお知らせのできる日が来ますように。
<追記>
この記事のみ、コメント欄の書き込みができるようにしておきます!
<さらに追記>
『木苺通信』文庫版できました!