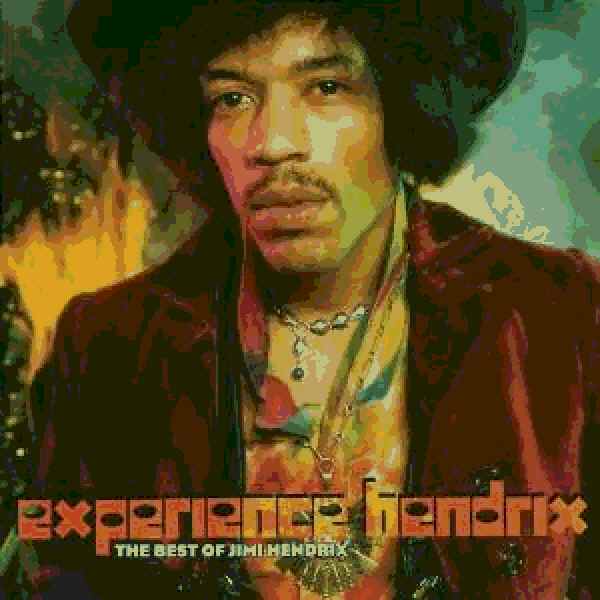前回、アップした音源が好評だったようで1位を獲得したのだ

本日、帰宅後もブログの更新などの為に何度かチェックしていたのだ
1位と2位を行ったり来たりしているようだ
「ブログランキングってどんな構造になってるのかな?」
非常に流動的なのだ
先日もお話したように気楽に楽しみたいと思っているのだ
話は変わるが・・
常連読者の方は私がzoom MS-50Gを所有している事をご存じだと思う
実は少し前に壊れてしまったのだ
この手のデジモノの修理は想像以上に高額なのだ
○万円・・という請求も有り得る
1年保証は常識だが期間内に壊れる事は皆無だといえる
過去にあらゆる機器を使ってきたが保証期間内に壊れた製品はなかった
当然ながら保証期間を過ぎれば『有償』になる
実売で1万円を切る価格なので新品を購入した方がお得なのだ
普通の人は壊れた時点で同じ製品は買わない
買うにしても他社の製品を選ぶと思う
読者の皆さんは如何だろうか?
私の持論としては・・
”気に入れば何度でも買い替える・・・”
なのだ
少し前に無償でバージョンアップが可能になったのだ
これによってより魅力が増したのだ

以前は自分自身でバージョンアップの作業を行う必要があった
すでに店頭に並んでいる製品は更新済みという事になるのだ

100個のエフェクトが使用できるようになったのだ
自宅遊びや宅録にも十分に対応できるレベルだといえる

私もスタジオ利用や友人とのセッションに参加する時にはこれを1個持参する事も多いのだ
「ディストーションも持ってくれば良かったなぁ・・」
という後悔もない
近年のzoomの音色は中級者でも満足できるレベルになった気がする
価格的にも良心的だと思う
しかしながら、本格的な音作りや用途においては改良の余地も感じられる
BossのGT-100のような上級機種に触れてしまうと物足りなさも否めない
上級機種を購入したものの持て余してしまうという人にも丁度良い
ギターを良く分かっていない人に限ってアンプの生音とライン録りの音を比較する傾向が見られる
賢明な読者の方には今さら説明は要らないと思うが・・・
今回はzoom同士を『結合』してみたのだ

本機のアウトプットはモノ×2という仕様になっているのだ
つまりヘッドフォンの直挿しは出来ないのだ
片側だけしか鳴らないという事になってしまう
用途が限定されるのだ
オーディオインターフェイスなどの入力端子に接続してモニターする方法
あるいは本機のモノからアンプに直結する方法が挙げられる
以前に同社のG3を使っていたのだ

モノ×2端子、ステレオ端子が用意されていたのだ
ヘッドフォンでの使用も可能なのだ
簡易リズムマシーンとルーパーも内蔵されていた
これ一台でかなり遊べるマシンだった
自宅で使うか?
外に持ち出すか?
練習用なのか?
宅録の音源用か?
など、色々なアプローチが考えられる
単純に価格だけで上位、下位という決めつけはできない
この辺りの考え方もzoomらしいのだ
そもそも、このサイズのマルチをリリースする発想は斬新だと思う
まったくもってマルチらしからぬ風貌なのだ
外観がロボット的だといって嫌う人もいるが・・
個人的にはツボにハマっているのだ
問題はない
今回はファンク風にカッティングを録音してみたのだ
イメージ的にはナイルロジャースなのだ

大好きなギタリストの一人なのだ
ほとんどカッティングしかしない
まぁ、ファンク系のギタリストに多い傾向ではあるが・・・
カッティングだけですべてを手に入れた天才なのだ
グラミー賞も受賞しているのだ
凄い人なのだ
今回はストラトを使用しているのだ

アリアでも問題ないが・・
やはりストラトの方が雰囲気が出るのだ

何かと重宝しているマシンなのだ
「DAWソフトは不要なんじゃない?」
と思っている読者の方もいると思う
個人的にはどちらも必要なのだ
実はこの手のマシンで複雑なドラムトラックを組み立てるには手間と時間がかかるのだ
経験がある人はお分かりだと思うが・・・・
今回はDAWソフトでサクサクっとドラムトラックを作ったのだ
それをUSB経由で本機に送るという流れなのだ
本体で修正はできないが作業時間は半分なのだ
むしろパソコン側でテンポやフレーズを練っておけば良いだけの話なのだ
気に入らなければ、改めて作り直す事も簡単なのだ
『マイナスワン』のオケを作っておくという事も可能なのだ
MTRでギターのフレーズを練習したり徹底的に録音を煮詰めるという発想もありなのだ
つまりは色々なアイディアやアプローチが可能だという事なのだ
私の場合、BR-80も含め3方向のアプローチが可能なのだ
録音データを相互にやり取りする事も出来るのだ
「何だか訳が分からなくなってきたけど・・・」
という方も多いと思うのでこの辺りで止めておくのだ

いろいろと遊べるという事なのだ
何度も言っているが・・
素人ギター弾きはもっと自分のギターを客観視すべきなのだ
つまりは録音してみるという事なのだ
これは究極の練習方法なのだ
自分のレベル(リズムやチョーキングの音程感など)を知る事が上達の近道なのだ

今回の音源もヘッドフォン環境でお楽しみいただきたい
気に入った方は投票をお願いしたい
次なる音源を思案中なのだ

本日、帰宅後もブログの更新などの為に何度かチェックしていたのだ
1位と2位を行ったり来たりしているようだ
「ブログランキングってどんな構造になってるのかな?」
非常に流動的なのだ

先日もお話したように気楽に楽しみたいと思っているのだ
話は変わるが・・
常連読者の方は私がzoom MS-50Gを所有している事をご存じだと思う
実は少し前に壊れてしまったのだ
この手のデジモノの修理は想像以上に高額なのだ
○万円・・という請求も有り得る
1年保証は常識だが期間内に壊れる事は皆無だといえる
過去にあらゆる機器を使ってきたが保証期間内に壊れた製品はなかった
当然ながら保証期間を過ぎれば『有償』になる
実売で1万円を切る価格なので新品を購入した方がお得なのだ
普通の人は壊れた時点で同じ製品は買わない
買うにしても他社の製品を選ぶと思う
読者の皆さんは如何だろうか?
私の持論としては・・
”気に入れば何度でも買い替える・・・”
なのだ
少し前に無償でバージョンアップが可能になったのだ
これによってより魅力が増したのだ

以前は自分自身でバージョンアップの作業を行う必要があった
すでに店頭に並んでいる製品は更新済みという事になるのだ

100個のエフェクトが使用できるようになったのだ
自宅遊びや宅録にも十分に対応できるレベルだといえる

私もスタジオ利用や友人とのセッションに参加する時にはこれを1個持参する事も多いのだ
「ディストーションも持ってくれば良かったなぁ・・」
という後悔もない
近年のzoomの音色は中級者でも満足できるレベルになった気がする
価格的にも良心的だと思う
しかしながら、本格的な音作りや用途においては改良の余地も感じられる
BossのGT-100のような上級機種に触れてしまうと物足りなさも否めない
上級機種を購入したものの持て余してしまうという人にも丁度良い
ギターを良く分かっていない人に限ってアンプの生音とライン録りの音を比較する傾向が見られる
賢明な読者の方には今さら説明は要らないと思うが・・・
今回はzoom同士を『結合』してみたのだ

本機のアウトプットはモノ×2という仕様になっているのだ
つまりヘッドフォンの直挿しは出来ないのだ
片側だけしか鳴らないという事になってしまう
用途が限定されるのだ
オーディオインターフェイスなどの入力端子に接続してモニターする方法
あるいは本機のモノからアンプに直結する方法が挙げられる
以前に同社のG3を使っていたのだ

モノ×2端子、ステレオ端子が用意されていたのだ
ヘッドフォンでの使用も可能なのだ
簡易リズムマシーンとルーパーも内蔵されていた
これ一台でかなり遊べるマシンだった
自宅で使うか?
外に持ち出すか?
練習用なのか?
宅録の音源用か?
など、色々なアプローチが考えられる
単純に価格だけで上位、下位という決めつけはできない
この辺りの考え方もzoomらしいのだ
そもそも、このサイズのマルチをリリースする発想は斬新だと思う
まったくもってマルチらしからぬ風貌なのだ
外観がロボット的だといって嫌う人もいるが・・
個人的にはツボにハマっているのだ
問題はない
今回はファンク風にカッティングを録音してみたのだ
イメージ的にはナイルロジャースなのだ

大好きなギタリストの一人なのだ
ほとんどカッティングしかしない
まぁ、ファンク系のギタリストに多い傾向ではあるが・・・
カッティングだけですべてを手に入れた天才なのだ
グラミー賞も受賞しているのだ
凄い人なのだ
今回はストラトを使用しているのだ

アリアでも問題ないが・・
やはりストラトの方が雰囲気が出るのだ

何かと重宝しているマシンなのだ
「DAWソフトは不要なんじゃない?」
と思っている読者の方もいると思う
個人的にはどちらも必要なのだ
実はこの手のマシンで複雑なドラムトラックを組み立てるには手間と時間がかかるのだ
経験がある人はお分かりだと思うが・・・・
今回はDAWソフトでサクサクっとドラムトラックを作ったのだ
それをUSB経由で本機に送るという流れなのだ
本体で修正はできないが作業時間は半分なのだ
むしろパソコン側でテンポやフレーズを練っておけば良いだけの話なのだ
気に入らなければ、改めて作り直す事も簡単なのだ
『マイナスワン』のオケを作っておくという事も可能なのだ
MTRでギターのフレーズを練習したり徹底的に録音を煮詰めるという発想もありなのだ
つまりは色々なアイディアやアプローチが可能だという事なのだ
私の場合、BR-80も含め3方向のアプローチが可能なのだ
録音データを相互にやり取りする事も出来るのだ
「何だか訳が分からなくなってきたけど・・・」
という方も多いと思うのでこの辺りで止めておくのだ


いろいろと遊べるという事なのだ
何度も言っているが・・
素人ギター弾きはもっと自分のギターを客観視すべきなのだ
つまりは録音してみるという事なのだ
これは究極の練習方法なのだ
自分のレベル(リズムやチョーキングの音程感など)を知る事が上達の近道なのだ

今回の音源もヘッドフォン環境でお楽しみいただきたい
気に入った方は投票をお願いしたい

次なる音源を思案中なのだ