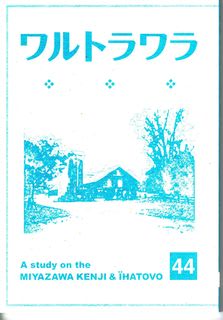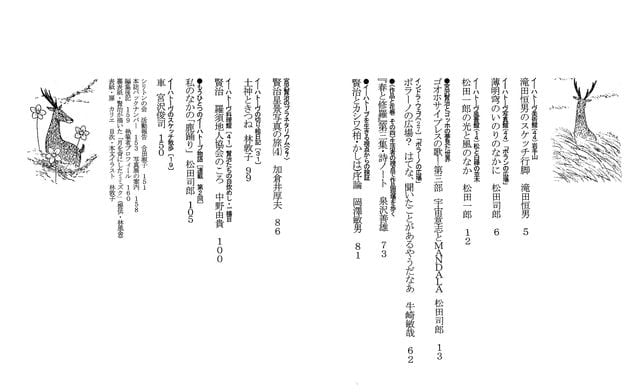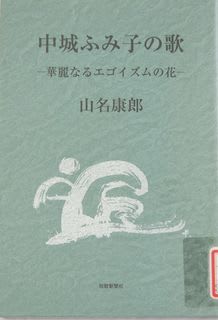晴れ時々曇り。最低気温6.4℃、最高気温15.8℃。

今日は『砂漠でみつけた一冊の絵本』のプロローグから一部を引用しつつ、続きを書いてみたいと思います。
60歳を迎えた年に「フランダースの犬」を読み返した時、今までとは全く違った意味が迫ってきたと感じた柳田氏はこういうことを綴っています。
〈誰の人生にも春夏秋冬が〉
思いどおりにならない人生、辛いことの多い人生、数々の悔いの残る人生、そんな中にあっても、振り返ってみれば、やさしいおじいさんとの日々はあったし、心の通い合った愛犬パトラッシェとのたのしい想い出もたくさんあった、そして、死ぬ前にせめて一度だけでも見たいと思っていたルーベンスの大作を、一瞬射しこんできた月の光によって見ることができた。
「ああ、神さま、これで、じゅうぶんでございます」というネルロの言葉は、まさに自らの人生とその終結への納得を意味しているに違いない。
それゆえにこそ、「よろこびのなみだ」が頬をつたったのだ。
今までとは全く違った読み方に至った背景には、その三年前に、氏のご子息・洋二郎さんが二十五歳の若さで自ら命を絶ったということがありました。
追悼記『犠牲(サクリファイス)わが息子・脳死の日々』(文芸春秋)を司馬遼太郎氏に送ったところ、悔やみ状が柳田氏のもとに届けられました。
その中に吉田松陰が死の直前にしたためたという「留魂録」の「人は、たとえ六十、七十であろうと、二十五、六であろうと、春夏秋冬というのがあるのだ。悔ゆることはない」という一節があり、「この言葉ほど、息子を喪った後の私の胸の奥に深く落ちてきたものはなかった。」と書いています。
二十歳代で斃(たお)れた吉田松陰の言葉からご子息にも「春夏秋冬」があったことを思い起こしたのです。
洋二郎さんが心を病んだ最後の五年半に書き残した短編文集や日記には、この世に生きた意味が物語れるだけの文脈があり、悔いのない人生を生き切ったと思える要素があったからでしょう。
とはいえ、
ご子息の死後、しばらくの間、心が乾ききった砂漠のようになり、呆然とした日々を送っていた柳田氏。そのようなときに児童書コーナーで絵本に目が留まり、手に取って読むことになります。
そこで、すぐれた絵本や物語は実に深い語りかけをしていること、具体的には「人間のやさしさ、すばらしさ、残酷さ、よろこびと悲しみ、生と死などついて実に平易に、しかも密度濃く表現している」ことに気づいていくのです。
とりわけ、氏の心を直撃したのが、「よだかの星」だったとありました。
よだかが孤独の河をさまよう物語は、カフカの世界に通じると感じたと綴られています。
そして、
「人は人生において三度、絵本や物語を読み返すべきではないか」という思いに至るのです。
三度とは、自分が幼い時、親になって子どもを育てる時、そして、人生後半になってからか厳しい病気を背負うようになった時。
死の受容に欠かすことのできない「自らの人生への納得」という問題について、自分の生き方にまで結びつけて読み取るということは、人生後半になってからか厳しい病気を背負うようになった時こそではないかと自身の体験と結び付けて結論を導き出していました。
🍁 🍁 🍁
ネットで調べると、吉田松陰が処刑直前に江戸・小伝馬町牢屋敷の中で書き上げた「留魂録」は全十六節からなるもので、ここで取り上げられているのは第八節の一部と思われます。
ネットから現代語訳を引用します。
「人の寿命には定まりがない。農事が四季を巡って営まれるようなものではないのだ。
人間にもそれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。十歳にして死ぬものには、その十歳の中に自ずから四季がある。二十歳には自ずから二十歳の四季が、三十歳には自ずから三十歳の四季が、五十、百歳にも自ずから四季がある。
十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことだ。百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするような事で、いずれも天寿に達することにはならない。(参考文献:古川薫著「吉田松陰 留魂録」)
これを二十代で著したとは、吉田松陰という人は類まれな人材だったのだと改めて思いました。
また、優れた絵本は「人間のやさしさ、すばらしさ、残酷さ、よろこびと悲しみ、生と死などついて実に平易に、しかも密度濃く表現している」との分析になるほどと思いました。語りかけてくるような絵と言葉に心をゆだねるひとときをこれからも持ち続けたいものだと思っています。