アメリカの食糧配給拠点に並ぶ車列とされる写真を見た。
英語に一丁字もないため、現在のアメリカの食糧配給の現状は判らないが、写真を見る限りではアメリカの一部の州で生活困窮者に対する無料配給を含めて何らかの食糧配給が行われているものと推測する。アメリカでは3月4.4%であった失業率が4月には14.7%に悪化し、世界恐慌時の25%を超えるとの悲観的な見方もある。日本の失業率は3月2.5%であるが、現在は2桁になっているのは確実ではなかろうか。これに農業生産の停滞や物流の滞りが加われば食糧の需給バランスは崩れ食料品は品薄・高騰し、我々が歴史としてしか知らないヤミ米列車や買い出し列車も絵空事ではなくなるだろう。こうなれば、政府は何らかの需給統制を行う必要が生じるが、2か月近くなるのに未だアベノマスクが届かない現状から考えてタイムリーな配給が実施できないだろうことは確実である。戦時中には食糧切符に依る配給制度があったとされるが、現在よりも通信・交通が遥かに劣っていた時代に、タイムリーな配給を如何にして行ったのだろうか。日本の人口は1920(昭和15)年に7200万人、2019(令和元)年は1億2500万人とされる。配給実施の基本単位は世帯であろうと考えて調べてみたが、現在の世帯数は5000万世帯と分かったものの戦前の世帯数は知ることができなかったが、戦前の子沢山や親子同居を考えて1世帯4人と仮定すると2000万世帯程度ではなかろうか。配給切符は隣組の組長が各戸に配布していたと聞いているので、仮に一人の組長が20戸を担当すれば100万人の組長をコントロールすることでスムーズな配給が可能となる。既にマスクが市場に出回り始めた状況にも拘らずアベノマスクが届かないのは、5000万世帯に戸別配給するとしたことも一因ではと考える。しかしながら、戸別配給に変えて戦前の隣組制度に似通った自治会を活用できるかと云えば、自治会は任意加入であるために未加入の世帯も少なくないとされるので、配給制度には活用できない。また自治会とオーバーラップする形で民生委員も置かれているが、個人情報の壁を思えば民生委員も全世帯の実状に通じてはいないだろうし、食糧配給の拠点と考えることは出来ないように思う。
先日「中国コロナは真実を暴くウィルス」という社会学者の言葉を引用・紹介したが、わが国では国民の命を守る最後の砦であるべき「食糧の配給機能」が未整備の状態であるように思える。江戸時代では「お救い米」制度があった一方で「打ち壊し」や大塩平八郎の乱が起き、明治期にも富山県で起きた米騒動が瞬く間に全国に拡大したと習った。医療崩壊を懸念して「治に居て乱を忘れず」と平時からの医療体制整備の必要性が叫ばれているが、配給制度についても設計図を描いておく必要があるのではないだろうか。まして個人責任を本分とする強国アメリカでも、食糧の配給が済々と行われているらしいと思えば・・・。















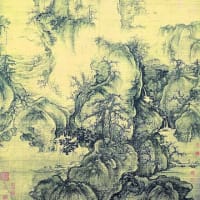




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます