米価高騰の抑制策として、凶作を条件としていた政府備蓄米の放出が行なわれる。
”タイ米騒動”があったなとWikipediaで調べると、《1993(平成5)年の記録的冷夏に起因する米不足現象で、平成のコメ騒動とも呼ばれている》とあった。自分と我が家限定の記憶であるが、当初は国産米〇㎏購入しようとすれば、タイ米〇㎏を同時購入しなければならないという販売形式であったが、何時しか国産米が出回り始めて何の制約も無く国産米を購入できたように思うので、流通経路のどこかで。作為的な操作があったのかも知れない。
今回のコメ不足では、平成のコメ騒動とは異なり令和6年のコメ収穫量は前年を上回ったものの、JAを始めとする大手集荷業者の集荷量が前年を下回る、すなわち農家の売り惜しみが原因の一つとして挙げられるらしい。都市伝説であろうが「八十八の手間がかかることから「米」という字が出来た」ことを考えれば、農家が高値を期待して米を保有していることは、株の値上がりを期待する投資家と同じであり、非難することはできない。
今回のコメ不足では、平成のコメ騒動とは異なり令和6年のコメ収穫量は前年を上回ったものの、JAを始めとする大手集荷業者の集荷量が前年を下回る、すなわち農家の売り惜しみが原因の一つとして挙げられるらしい。都市伝説であろうが「八十八の手間がかかることから「米」という字が出来た」ことを考えれば、農家が高値を期待して米を保有していることは、株の値上がりを期待する投資家と同じであり、非難することはできない。
江戸時代における米騒動は、不作・飢饉時を除いて消費者が「打ち壊し」に奔るのは、米問屋がカルテルを結んで売り惜しみした例も多いとされるが、現在のコメ騒動が農業者の売り惜しみであるとするならば、農業従事者の育成や保護によって農家の地位が向上したことの表れとも観ることができるように思える。
報道では、コメ離れが進むとの観測・警鐘もあるが、米飯愛好者が底値に到達した今では、これ以上のコメ離れは起きないように思う。育ち盛りではそうもいかないだろうが、成人・老人が腹八分で済ませば20%の値上がりには対処できて、健康増進にもつながるので、米価上昇も良い一面があるのでは(笑)と思っている。閑話休題。
先日何かの拍子で戦後の「芋メシ」を思い出し、反発必至の妻子の外出時を狙って幼児の記憶とクックパッドを拠り所に作ってみた。さらに、今ではB級グルメ化した「団子汁」も作って、意気揚々ながら叱責覚悟で妻子の御帰還を待ったが、案に相違して妻は「懐かしい」と云い、娘も「毎日食べたいとは思わないが、たまには」で全否定では無かった。戦後に比べれば芋は「紅ほっぺ」、団子汁には豚肉、季節感の無い数種類の野菜、練り物も入り幼少期のそれとは別物ではあるが。
夏目漱石の「坊ちゃん」には、東京育ちの坊ちゃん先生がが、語尾に「・・・なもし」を付ける伊予弁に「菜メシ、菜メシと云うな」と癇癪を起こす場面があるので菜っ葉だけを炊き込んだ「菜メシ」も芋メシと同じ位に都市生活者を含めて市民権を持っていたことが窺える。
昭和40年代頃は、戦後の食料事情を忘れないために終戦の日前後には「雑穀ご飯」を伝えようという運動もあったが、飽食の時代に入ると耐えて聞かなくなった。
大凶作・震災等で米が潤沢に入手できなくなった場合の非常手段として、雑穀入りご飯でカサを増す、「食い延ばし術」は伝承する必要があるのではないだろうか。















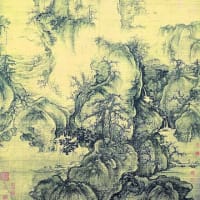




米不足はてっきり農協の仕業と思っていましたが、農家の出し渋りという考えがありましたか。
豊作なのに異常な高値では、食べ盛りの子供がいる家庭は大変だろうと思います。
こんな時こそ備蓄米を放出すればと思いますのに、農水大臣の説明が分かりにくくて不信感を呼びます。
出し渋る農家のせいなら、国民を安心させるため政府が備蓄米を放出すれば良いと、考える自分がおかしいのでしょうか。
かっては、余分なコメを備蓄するため、余分な保管料がかかるので、国民はもっとコメを食べてほしいと言っていたのに、農水省の本意はどこにあるのでしょうね。