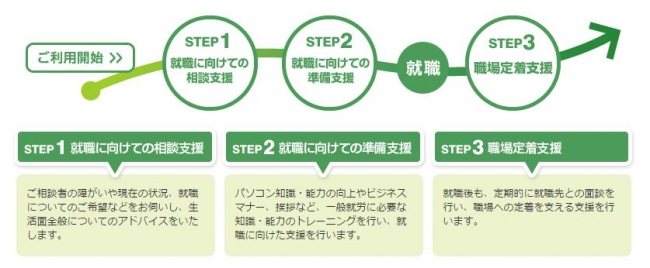福祉では高齢や子育て世代のことがまず話題になりますが、実はさらなる弱者は、病気や後遺症を抱える人たちです。
その弱者の中でも厳しい立場に置かれる視覚障害者が利用可能な制度は、身体障害者、障害年金、難病制度、介護保険などです。
前2者は視機能障害の程度で決まり、身体障害者が市区町村の役所の福祉課、障害年金は社会保険庁が扱います。
難病制度は疾患名で決まる制度で、保健所が扱います。
介護保険は65歳以上なら介護が必要と認められれば原因は問いませんが、40歳から64歳の間で介護保険サービスを受けられるのは16種類の特定疾患の場合です。このうち視機能と関連するのは糖尿病性網膜症と、一部の脳血管疾患などに限られます。
介護保険は各市区町村に担当者がいますが、以前本コラムでも述べたように視覚障害者を想定した制度ではありません。
このように福祉制度は一体化しておらず、担当部署もまちまちです。
しかも前回話題にした障害年金を含めて、当事者が申請しやすい状況にはなっていません。
当事者周辺に支援者がいればよいですが、病気や障害を持っている当事者が自分で制度を見つけることは容易でなく、福祉サービスを得る機会を失している例もあるでしょう。
日本の制度を、英国のそれと比較調査した甲府共立病院眼科の加茂純子医師は、日本の制度は複雑で、当事者にとっては大きな問題があると指摘しています。
医師もよく勉強しておかないと、制度利用について患者に的確な情報提供ができません。ただし、いったん情報を提供すると、今度は制度が複雑なために、診断と治療に時間を大きく割いて何種類もの書類を作らねばなりませんから、医師は積極的な姿勢になりにくいのです。
つまり、病者にも医師にも複雑すぎる制度なのです。
英国にはサイトロス(視力喪失)アドバイザーなるものが、眼科外来のチームにいて心理的支援や福祉サービスにつなげる役割を担っています。医師は、該当者をその人にバトンタッチすればよく、患者もあちこちに相談に行くなど右往左往する必要がないわけです。
サイトロスアドバイザーはすでに15年の歴史があり、NHS(英国国民保健サービス)によって支えられています。
加茂医師は、日本の中途失明者が幸福かどうかという視点で調査をし、その結果に応じての戦略を立てるのが国の姿勢として望ましいと述べています。
今、国は医療や福祉予算を抑制的に考えています。これに対し、国民は自分が本当にニーズに合った医療や福祉を受けているだろうかと、現実の空気や報道とは独立して自身の実感に基づいて考えてみるべきだと思います。
 |
若倉雅登(わかくら まさと)
井上眼科病院(東京・御茶ノ水)名誉院長
1949年東京生まれ。北里大学医学研究科博士課程修了。グラスゴー大学シニア研究員、北里大学助教授、井上眼科病院副院長を経て、2002年から同病院院長。12年4月から現職。北里大学医学部客員教授、日本神経眼科学会理事長などを兼務し、15年4月にNPO法人「目と心の健康相談室」を立ち上げ、副理事長に就任。「医者で苦労する人、しない人---心療眼科医が本音で伝える患者学」(春秋社)、「健康は眼に聞け」(同)、「目の異常、そのとき」(人間と歴史社)、医療小説「高津川 日本初の女性眼科医 右田アサ」(青志社)など著書多数。専門は、神経眼科、心療眼科。予約数を制限して1人あたりの診療時間を確保する特別外来を週前半に担当し、週後半には講演・執筆活動のほか、NPO法人などのボランティア活動に取り組む。
|
|
|
(2016年2月4日 読売新聞)