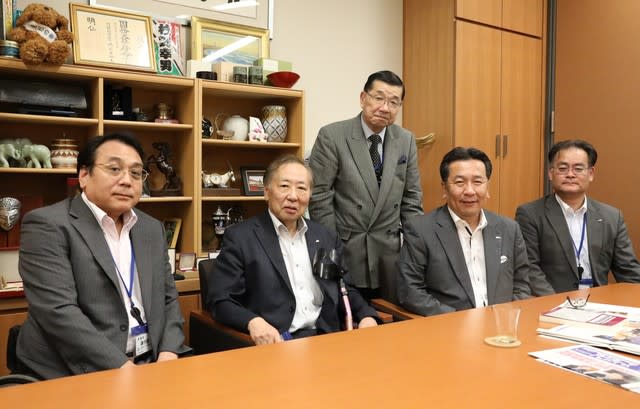生きていくには、「人」と関わりながら生活する必要があります。人には感情があり、悲しければ涙が流れること、嬉しさで笑顔になること、悩みを支えてくれる優しさで穏やかになることも、やっぱり人からもらう “贈り物” です。
精神を患った兄は、ひとりではありません。友だちは家に訪ねてこなくなりましたが、“家族” は今でも変わらず支えています。これは、四六時中つきっきりで兄と過ごすという意味ではなく、両親も私も、私と交際中の彼も、自分の時間を持ち「生きること」の楽しさを見出し、そして、それを兄に伝える。これが、人から人へ伝える喜びに変わると確信しています。私は、大学卒業後進路で迷っていましたが、今では情報発信する立場として、執筆活動をしています。実家と距離が離れていますが、冷静に兄と接する距離感を掴むことができたおかげで、兄を交えてビデオ電話で会話をしたり、定期的に実家に顔を出したりと、積極的なコミュニケーションを心がけるようになりました。
前は挨拶すらしていなかった兄ですが、「心音、おはよう」「今日は、何していたの?」と聞いてくることに対し、情報収集した「最近あった楽しかったこと」「今行っている活動」など、メディアのライターだからこそ手に入る新しい情報や価値観などを伝えています。自分が停滞することなく、「生きること」に前向きである姿を見せることで、やりがいや楽しさを兄が見つけるヒントになるかもしれないからです。
そして、兄がどんな精神状態でも否定せずにありのままを受け止めることも学びの場でした。精神の病に関して「気持ちの問題じゃないか?」「病は気から」などと、目に見えない病状に理解が得られないことがあります。
ですが、テレビやパソコンを見ていてもすぐに集中力が切れてしまって立ち上がったり、外出先ではお店の店員や病院の患者に用事がないのに話しかけてしまったり、感情を抑えられずに大きな声を突然出して周囲に迷惑をかけたり。このような状態を目の当たりにすれば、「病は気から」が通用するとは到底思えないはずです。“場の空気” を読むことができないのですから、健常者と同じような生活はやはり難しいのです。そのため、本人が興味のないことを無理に押し付けることや、同年代の健常者と同じような生活を求めるのは、兄にとってプレッシャーでしかないと思っています。
所得に応じて保険料や税金が異なるように、障害の有無にあわせて働く場所や収入源を区別をすることも大切です。兄は基本的に働くことができないので、病院の診断結果をもとに障害者年金をもらっていますし、以前工場で1か月働いた職場は、障害者手帳2級の兄に理解がある雇用先でした。障害者手帳を取得したばかりの頃は、両親も「まだ諦めたくなかった……」と苦渋状態でしたが、病や事故などでやむを得ず働くことができない人に対してハンディキャップを作る必要性を私たちが受け止めることで、おおらかな気持ちで兄を見守ることができています。障害者手帳や障害者年金、障害者雇用は強い味方になり、活用すべきサポートなのです。
また、大人になるほど頑なになる固定概念を柔軟に戻すことや、抱えている悩みを素直に打ち明けることも人生のターニングポイントでした。兄を守ろうとするがゆえに、周りからの声を遮断したり、アドバイスをいただいても取り入れなかったりする時期が長く続きましたが、交際中の彼が教えてくれたメッセージをきっかけに新しいアイデアの扉が開きました。「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがありますが、ひとりより二人、三人より四人のほうが自分にない閃きが訪れます。
「これを言ったら、どんな反応になるのか」と相手を探りすぎて、自分の知恵の中で作られた条件ばかりに縛られていては、良い情報も入ってこない。それを学んでからは、本当に信頼できる人に対して気持ちをオープンにすることを心がけるようになりました。
小学生だった私が、あの時より少しだけ強くなって今ここにいます。20年近くの月日の中で兄と共に成長したことは、どんな時でも手を離さない「絆」と、人生を前向きに生きるための「心」。兄を穏やかに見守る居場所は、今日も明日も変わらずにあります。
またいつか、兄に“元気な心” が戻ると願って——。 【完】