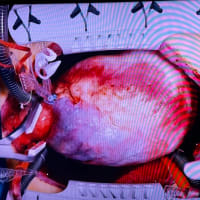後輩医師から今まで実施していない手術術式の導入についての相談を受けました。具体的には、昨年から保険適応とされた右小開胸の弁膜症手術です。
小開胸手術自体はアプローチが違うだけで、実際に弁置換だったり、弁形成だったり、その弁の修復の方法は従来となんら変わることはありません。人工心肺装置にしても、送血、脱血、大動脈遮断、心筋保護、どれも同じです。違うのは皮膚切開部位、それに伴う見える角度、深さ、ワーキングスペースの大きさなどです。アプローチが違っても慣れた方法と同じクオリティで安全・確実に治療できるのであれば、アプローチを変えることは、その手術の応用にすぎません。
いろいろとそろえる道具が必要だったりしますが、実はその道具だったり、内視鏡下に行う手技だったりとか、そういうところに抵抗感を感じて、新しい手技を実施するのに躊躇してしまう傾向、これはだれでもあることで、筆者もそう感じたことが何度もあります。
最初は他施設に見学に行ったり、経験なる医師に指導に来てもらったり、道具を借りたり、など、けっこう億劫にも思える前準備があったりします。誰でも最初はそうです。最初はその壁を越えていくしか次のステップにはいけません。
安全・確実にできると確信が持てるようになったら、それを標準術式として導入する、執刀医のマインドをそのようにリセットすることが重要です。これはある意味、新しい治療法を導入していくというチャレンジングスピリットであり、このスピリットなくては、医療も衰退します。
億劫に思っている段階では、その新しい方法を実施しないで済む理由を何となく探すような気持ちもありましたが、基本的に新しい術式を標準の方法として考え、それができない、リスクがあるかどうかを考えるという、思考回路の変更が必要です。そうすることで、思考回路の整理も進み、新たな段階にステップアップできるように思います。
要は、失敗なく、安全、確実にできるかどうか、ということにかかっています。特に低侵襲手術といわれているように、低侵襲=短時間に確実に、できるということが大前提です。新しい技術とはいっても、長時間かかったり、出血が多くなったり、弁の修復が不十分になってしまうのでは実施する意味がありません。その意味で、確実に成功する症例を適応にする、ということが重要です。
当たり前のような内容を記載してしまいましたが、実際に執刀を責任をもって行うということは、こうしたマインドが意外に重要である、ということを、年齢を重ねるたびに思う、今日この頃です。
小開胸手術自体はアプローチが違うだけで、実際に弁置換だったり、弁形成だったり、その弁の修復の方法は従来となんら変わることはありません。人工心肺装置にしても、送血、脱血、大動脈遮断、心筋保護、どれも同じです。違うのは皮膚切開部位、それに伴う見える角度、深さ、ワーキングスペースの大きさなどです。アプローチが違っても慣れた方法と同じクオリティで安全・確実に治療できるのであれば、アプローチを変えることは、その手術の応用にすぎません。
いろいろとそろえる道具が必要だったりしますが、実はその道具だったり、内視鏡下に行う手技だったりとか、そういうところに抵抗感を感じて、新しい手技を実施するのに躊躇してしまう傾向、これはだれでもあることで、筆者もそう感じたことが何度もあります。
最初は他施設に見学に行ったり、経験なる医師に指導に来てもらったり、道具を借りたり、など、けっこう億劫にも思える前準備があったりします。誰でも最初はそうです。最初はその壁を越えていくしか次のステップにはいけません。
安全・確実にできると確信が持てるようになったら、それを標準術式として導入する、執刀医のマインドをそのようにリセットすることが重要です。これはある意味、新しい治療法を導入していくというチャレンジングスピリットであり、このスピリットなくては、医療も衰退します。
億劫に思っている段階では、その新しい方法を実施しないで済む理由を何となく探すような気持ちもありましたが、基本的に新しい術式を標準の方法として考え、それができない、リスクがあるかどうかを考えるという、思考回路の変更が必要です。そうすることで、思考回路の整理も進み、新たな段階にステップアップできるように思います。
要は、失敗なく、安全、確実にできるかどうか、ということにかかっています。特に低侵襲手術といわれているように、低侵襲=短時間に確実に、できるということが大前提です。新しい技術とはいっても、長時間かかったり、出血が多くなったり、弁の修復が不十分になってしまうのでは実施する意味がありません。その意味で、確実に成功する症例を適応にする、ということが重要です。
当たり前のような内容を記載してしまいましたが、実際に執刀を責任をもって行うということは、こうしたマインドが意外に重要である、ということを、年齢を重ねるたびに思う、今日この頃です。