京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。
京都観光では最も詳しいです!
Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)
kobaさまへ
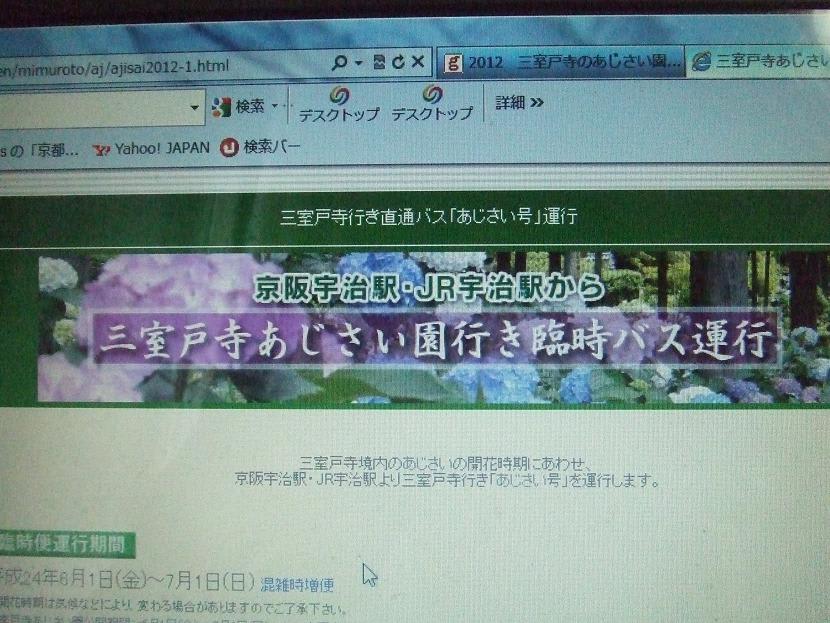
最初の文面の意味が、正確に把握できていませんでした。
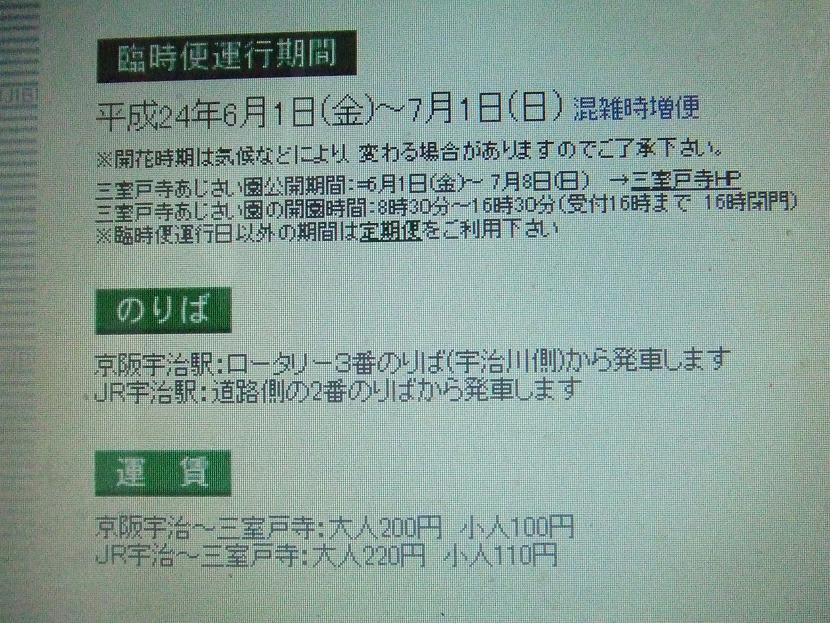


これでどうでしょう!
世話のかかる人だ(笑)!!
特別ですよ!!!
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
流れ橋(山城散策2)

写真は、流れ橋
八幡東ICで高速道路を降りた1つ目の信号が、八幡内里東の交差点です(簡易地図)。
合流した道が3車線で交通量も多く、さらにこの交差点までの距離が短いので、最内から大外へ車線変更が必要なので要注意です。
八幡内里東の交差点を左折して、2つ目の信号を左折します(北に戻る恰好)。
すると府道22号線との交差点になります。
これを右折します。
最初の信号を左折すると“四季彩館”という施設が右手にあります。
高速を降りてからここまでは、ガッチリ案内板があるので、迷うことはないでしょう。
ここに駐車してもいいようですが、ここは10:00からです。
四季彩館の左手奥に石田神社があるので、この境内を通過すると河川敷に出ます。
この河川敷の階段を登ると、目の前に「流れ橋」こと「上津屋橋」があります。
10:00より早く来た場合、無料駐車場があるので案内します。
府道22号線を四季彩館も通過して直進すると、道なりに右にカーブします。
45度ぐらい道がカーブした左手に、ちょっとだけ“流れ橋無料駐車場”の案内が見えます。
ここに左折します。工場しかないように見えますが、大丈夫です。
少し進んだ右手に無料駐車場があります。案内板もあります。
車を降りて河川敷に向かいます。
河川敷への登り道は、途中で道が交差し“イ”の字のようになります。
見通しが悪く流れ橋のある方向が分からないですが、これは左後方の道に進んでください。
登りきった先に“流れ橋”が現れます。
一般的に流れ橋は、川が増水した際にしっかりと固定していない橋桁が流されることを前提とした橋です。
数ある流れ橋の中で、356mあるこの木製の上津屋橋は日本最長のものです。
2011年の台風15号の後は見事に流されていました。
ちゃんと架かっている時は渡れて、風情もあるので面白いでしょう。
山城散策3へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 5 ) | Trackback ( )
2012 京都迎賓館一般参観の申し込みは6/23で終了と、正倉院正倉整備工事第2回現場公開の見学

写真は、一昨年の当選はがきのコピー(左)と、昨年の落選はがき(右)
さて、2012年の京都迎賓館一般参観の申し込みも、6/23で終了です。
皆さん、もう投函されたでしょうか。
最後の最後ですが、試算を再度掲載しておきます。
返信は約1か月後にあります。
複数枚投函されている場合には、1つにまとめて返信されます。
また1月後に僕も結果を掲載しますので、よろしければ皆様の結果もその時にコメントしてください。
投函がまだの方は急いで、もうお済の方は当たるといいですね!
一応リンクしておきます。
詳細は、
京都迎賓館の参観予約
を参照してください。
参観内容の概要は、
京都迎賓館
です。
内閣府の後は、宮内庁です。
さて第1回もご案内したので、奈良ですがご案内します。
現在整備工事中の正倉院の現場が公開されます。
通常は外観を遠くからしか見ることができませんが、かなり近くまで案内されるようです。
ハガキで申し込み、抽選に当選すれば参観できます。
公開日
9/21(金)、9/22(土)、9/23(日)の計3日間。
見学開始時間
9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00の計7回
各回の定員は200名。
申込期間
6/19から7/18までの消印有効です。
今回は第2回目ですが、最終的には第5回まであります。
第1回が2012年3月でしたので、第3回は2013年3月、第4回は2013年9月、第5回は2014年3月なのかもしれません。
詳しくは、宮内庁のホームページまで。
応募は1人1通までですが、前回の結果では倍率が2.6倍程度なので、それ程狭き門ではないようです。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 4 ) | Trackback ( )
山城散策の概要 アクセス 八幡東ICまで (山城散策1)

写真は、簡易地図
山城エリアは、京都府と奈良県の県境に近い木津市の周辺を指します。
かつて聖武天皇が恭仁宮を造営した場所でもあります。
この木津市や京田辺市にも国宝を持つ有名寺院がいくつかあります。
これらを順に散策していきます。
具体的には
「流れ橋(上津屋橋)」→「一休寺」→「海住山寺」→「岩船寺」→「浄瑠璃寺」です。
今回は散策といっても、個々が非常に遠いため車での案内になります。
レンタカーにもナビが付いているご時世ですが、道は詳細に紹介します(笑)。
公共の交通機関(電車とバス)でも行けますが、そのバスが1時間に1本が当たり前の地域ですので、個人的にはおすすめしかねます。
アクセス(八幡東ICまで)
堀川通を南下して、京都駅西横の高架下をくぐると、道の名前が油小路通(あぶらのこうじ)に変わります。
これを九条通、十条通を越えて進むと、右手に阪神高速8号京都線の上鳥羽入口があり、この高架に上がり直進します。
途中の巨椋池(おぐらいけ)料金所から第二京阪道路に名前が変わりますが、そのまま直進です。
そして八幡東ICで高速道路を降ります。
山城散策2へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 4 ) | Trackback ( )
2012 6/17の拝観3(徳迎山 正法寺)

写真は、開山堂
ここから大移動です。
「妙心寺」から丸太町通を西へ進み、「太秦映画村」の前の道に左折します。
道なりに南下し「広隆寺」の横を通過。
さらに南下し、梅津段町で四条通を横切り(右折した先に「梅宮大社」)、桂川を渡ります。
桂上野で左折し、桂川街道を南下します。
途中で「桂離宮」の前を通過し、上久世で171号線に合流します。
この辺りの道は結構拝観でも使えるので、車で行かれる方はチェックしておいてもいいでしょう。
171号線をさらに南下し、国道五条本で左折、さらに京守で府道13号線に右折します。
御幸橋を渡って石清水八幡宮を通過したさらに南にある「徳迎山 正法寺」に到着です。
6月はこの週末が特別拝観日でしたので、すべてはココのためにこの週末の予定になりました。
詳細は昨日と一昨日の本編の通りです。
マイナーですが、非常に見ごたえがあります。
9月、10月、11月にも特別拝観がありますので、「八幡散策」を是非御一考ください。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
松花堂庭園1 通常拝観(八幡散策13)

写真は、松花堂(右)と泉坊書院(左) 2016年秋の非公開文化財特別公開時は撮影可
松花堂弁当はご存じでしょう。
あの中が十字に仕切られたお弁当です。
あれは元々石清水八幡宮の社僧であった松花堂昭乗が、農家の種入れをヒントに絵具箱など雑貨として使っていたそうです。
それを昭和初期に吉兆の創始者である湯木貞一がお弁当箱として使ったのが始まりだそうです。
ここは前日までに予約しておくと付設の京都吉兆「松花堂店」で松花堂弁当4000円や松花堂弁当会席7800円を頂くことも出来ます。
門を入って右手に美術館(入館料400円)が、正面に庭園の受付があります。
庭園の入園料は400円で、月曜日は閉園です。
最初は“外園”からです。
右手は竹林、左手は苔、松、もみじに小川の池泉式庭園になっており、散策路にそって歩きます。
結構広いです。
このあたりも竹林と苔がきれいです。
竹隠は金明孟宗竹の竹林を借景に取り込んだ現代風の茶室。
梅隠は千宗旦好みの茶室を再現しています。
松隠は松花堂昭乗が住んでいた滝本坊の書院に小堀遠州と相談して建てたと伝わる茶室閑雲軒を再現したものです。
いずれも通常は閉まっており、外観だけの見学です。
お茶室の周辺を抜けると、一面が芝生になり右手に美術館別館が建っています。
この前には紅枝垂れ桜が春には咲きます。
芝生の左手をさらに進んだ奥に“内園”があります。
内園は撮影禁止です。
内園を入ると右手に泉坊書院の唐破風の玄関(京都府登録文化財)があります。
玄関の屋根上の唐破風瓦に”福禄寿”の文字が掘ってあります。
これらは“寛永の三筆”が筆を執ったもので、「福」は近衛信尹、「禄」は本阿弥光悦、「寿」は松花堂昭乗の筆と伝えられています。
さらに露地庭園を進むと右手にお茶室であり持仏堂でもある松花堂(京都府指定文化財)があります。
2畳の茶室で、付書院は仏檀にもなります。
天井画は土佐光武筆です。
さらに奥に進んだ庭園の左手に泉坊書院(京都府登録文化財)があります。
右が8畳の次の間、左が9畳と2畳半の上段の間がある座敷です。
次の間の腰高障子の月次絵も土佐光武の筆です。
書院の庭園の大きな松、苔、秋は紅葉のコントラストが非常にきれいです。
コメント ( 5 ) | Trackback ( )
2012 6/17の拝観2(妙心寺 東林院)

写真は、沙羅双樹の前庭
法金剛院から徒歩圏に妙心寺があります(車でしたが)。
妙心寺の東林院は9:30から、沙羅の花を愛でる会”です。
昨年に続き2回目です。
昨年は午後に来たらいっぱいだったので、1番乗りです(笑)。
抹茶付きで1580円と拝観料としては高めですが、そこは覚悟の上です。
本来はこの縁側に拝観者が鈴なりに座るので、こんな写真は撮れません。
1番乗りの特権です(笑)。
ここで先日コメントのあった”ひろ&きょん”さまとお話した訳です。
”袖触れ合うも他生の縁”ですので、今後ともよろしくお願いします。
昨年はご住職の面白い法話も聞きましたが、今年は何しろ1番乗りでしたので、なかなか始まりそうにありませんでした。
次の予定もあったので、今回法話はお預けでした。
7/1まで公開しています。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 10 ) | Trackback ( )
徳迎山 正法寺2 法徳殿、小方丈、書院(八幡散策12)

写真は、書院の庭園
一旦本堂から備え付けのスリッパで外へ出て、宝物館の法徳殿に移動します。
ここには重要文化財の“丈六阿弥陀如来像”があります。
丈六ですから約5mあります。
鎌倉時代の作風だそうで、製作者が分かっていません。
むろんガラスケースもないので、至近距離で見ることができます。
また洛中洛外図屏風もあり、現在の土地勘があれば面白いです。
本堂に戻り本堂奥の開山堂へ。
本堂と開山堂、さらに隣の小方丈に囲まれて中庭があります。
大方丈横の廊下から裏手にある小方丈と書院に向かいます。
小方丈は最奥に上段の間と床の間がある9畳と、10畳の次の間からなります。
小方丈と書院に囲まれて池泉式の庭園があります(書院前)。
書院はまずは付書院のある一の間、そして奥の二の間はお茶室になっています。
栗の木を使った梁には栗の釘隠しを使ったり、様々な意匠が凝らされており、丁寧に説明してくださいます。
書院を進むと、大方丈の玄関に1周して戻ってきて終了です。
伽藍内の広さや庭園の美しさ、さらに仏像も間近で見られるので、特別拝観時は非常に満足度が高いと思います。
ものすごくおすすめです。
八幡散策13へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
2012 6/17の拝観1(法金剛院)

写真は、礼堂とアジサイ
この日は朝から拝観日(いわゆる”お寺の日”)。
アジサイには少し早いですが、特別拝観がらみでどうしてもこの日でないといけませんでした。
アジサイを見に行くので、虫よけゲルを前腕、上腕、首筋さらには顔にも塗ります。
おかげさまで蚊には刺されずに済んだのですが、帰宅後に思わぬことになりました。
梅雨の晴れ間で午後からは結構晴れたので”日焼け”してしまい、日焼けでかゆくなりました(笑)。
日焼け止めは忘れていました。
さて車で丸太町通を西進し、9:00前に法金剛院に到着です。
今年の大河ドラマに出てきていた待賢門院(配役は檀れいさん)ゆかりのお寺です。
開門前に10人ぐらい来ておられました。
門前には沙羅の花が咲いていました。
アジサイはやはり少し早かったですね。
蓮が既に1輪きれいに咲いていました。
7月は蓮ですね。
ここも四季折々に花が咲くので、通年で楽しむことができます。
アジサイは6/23、6/24がいい頃でしょう。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
徳迎山 正法寺1 大方丈、本堂(八幡散策11)

写真は、桜の咲く本堂と大方丈の前庭
大原野の正法寺(しょうほうじ)はある程度有名ですが、八幡の徳迎山 正法寺(とっこうさん しょうぼうじ)を知る人は少ないのではないでしょうか。
浄土宗の寺院です。
当地の出身である“お亀の方”が徳川家康の側室となり、九男義直を産みます。
この義直が尾張徳川家初代藩主です。
以降尾張家によって厚く庇護されてきました。
通常拝観では正門から入って、正面の唐門を外部から見られるだけです。
右手には宝物館の“法徳殿”あります。
この左手に伽藍内への入口がありますが、通常は非公開です。
しかし年に6回の週末は伽藍内が公開されます。
4月、5月、6月、9月、10月、11月の1週末です。
玄関で拝観料700円を納めます。
八幡市観光協会の方の案内で拝観します。
まずは大方丈です。
襖絵は狩野派のもので、奥には上段の間があります。
右手前方の本堂との間は、唐門や鐘楼を背景にしたきれいな枯山水庭園です。
本堂内部には本尊の阿弥陀如来像と観音勢至菩薩を従えた三尊像です。
三千院の往生極楽院と同じ“大和座り”を間近いで見られます。
また長らく公開されていなかったので、内部の極彩色の装飾もきれいに保存されています。
八幡散策12へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 1 ) | Trackback ( )
2012 6/16の拝観2(梅宮大社)

写真は、神苑のアジサイ
長男を幼児教室に迎えに行って、一旦帰宅しました。
昼食後、降りしきる雨をものともせず、長男を連れて車で出かけます。
四条通を西進し辿り着いたのは、梅宮大社です。
神苑のアヤメやアジサイがきれいです。
翌日は拝観日でしたが、敢えて本日行っておきました。
翌日の梅宮大社は、檀林皇后祭・あじさい祭だったからです。
多分混むのでしょう。
しかしアジサイが神苑の裏側などに多く、僕の好きな”社殿背景の花の写真”が撮れないのが残念です。
おかげでこのようにどこかもわからないただのアジサイの写真になりました(笑)。
アジサイは来週もきれいでしょう。
アクセスが悪くもないものの良くもないのが微妙ですが、神苑自体は四季折々の花が咲きおすすめです。
詳細は、
梅宮大社1 アクセス 本殿
梅宮大社2 神苑
です。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
善法律寺(八幡散策10)

写真は、本堂前
善法律寺(ぜんぽうりつじ)は律宗の寺院ですので、奈良の唐招提寺の末寺です。
足利義満の母は善法律寺へ紅葉の樹をたくさん寄進したため、別名「紅葉寺」と呼ばれています。
寺領は非常にこじんまりとしています。
拝観は無料です。
表門を入ると石畳があり、やがて左に折れます。
右手前には庫裏と書院、右手奥に本堂、左手奥には池があります。
本堂に安置されている八幡大菩薩は、明治元年に神仏分離が行われるまで石清水八幡宮の殿内に安置されていたそうです。
この表門から本堂まで紅葉があります。
恐らく室町時代は寺領ももっと大きかったのでしょうけれど、今はこじんまりしたお寺です。
表門の参道を進むと突き当りに庫裏があります。
参道は庫裏の手前で左に折れます。
左手に書院、さらに奥に本堂があります。
右手には金剛庵という座敷があり、その奥は弁天堂のある池になっています。
事前に予約しておくと、本堂内を拝観出来ます。
また2016年11/26(土)と11/27(日)には本堂内の特別公開がありました。
拝観料は500円です。
庫裏で声をかけて本堂に上がり、右手から中に入ります。
本堂中央の内陣の高御座に本尊の八幡大菩薩がお祀りされています。
本堂の左手奥には大きな愛染明王像と吉祥天像が、右手奥には釈迦如来像と不動明王像がお祀りされています。
また本堂の後方は阿弥陀堂に繋がっています。
阿弥陀堂の中央には宝冠阿弥陀如来像が、左手には十一面千手観音像、右手には地蔵菩薩像がお祀りされていました。
2016年の特別公開では本堂の右手から書院の縁まで入れたので、書院の前庭も拝見出来ました。
2017年の特別公開では本堂の公開の他に、別途500円で金剛庵で碾茶と亥の子餅の呈茶がありました。
結構人気で12:00の公開開始、1時間ぐらいで売り切れたようです。
金剛庵からは池越しに本堂と紅葉が見えます。
また床の間には橋本関雪の仙境図の掛け軸が掛かっていました。
八幡散策11へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2012 6/16の拝観1(建仁寺 両足院)

写真は、両足院の池周囲の半夏生と水月亭
この日は朝からあいにくの雨。
降ったり止んだりです。
長男を幼児教室に送った後、迎えに行くまでの2時間を利用して、この時期お約束の半夏生です。
通常は非公開の塔頭です。
池の周囲に白いのがそうなのですが、これは花ではなく葉が白くなるのです。
遠くから見ると花にしか見えないですね。
しかし雨が降っている分、苔がきれいです。
また水月亭は国宝、如庵の写しで有名です。
建仁寺ですので祇園からも近いですし、庭園も大きくてきれいですのでおすすめです。
7/8まで公開しています。
またこの日と翌日は、京都大学の書道部が西来院と禅居庵で書道展をしておられました。
誰でも入場可能で無料でしたので、チャッカリ行ってきました。
共に内部は初でしたので、思わぬ成果でした(笑)。
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 6 ) | Trackback ( )
単伝庵(八幡散策9)

写真は、大黒堂と前庭
単伝庵(たんでんあん)は、“らくがき寺”として有名です。
公共の交通機関でのアクセスは、こちらです(簡易地図)。
正門から入ります。
車の場合のアクセスは、
木津川に架かる御幸橋を渡り、府道22号線へ左折します。
道なりに右にカーブし、京阪の高架下をくぐった次の信号を左折します。
再度道なりに右にカーブし、カーブが終わった右手に単伝庵の北門があります。
拝観
正門からの場合、左手に本堂、左手奥にお茶室、正面に本堂の大黒堂があり、前庭は苔がきれいです。
この大黒堂が“らくがき寺”といわれる所以です。
拝観料は100円ですが、なにも言われないのでお賽銭箱に100円入れておきました。
大黒堂の内部の白壁には無数の“らくがき”があり、これは公式に認められています。
サインペンも置いてあります。
ただし“1らくがき300円”です。
大黒堂の内陣中央には”走り大黒天像”が、右手には高野大師像、左手には八臂弁天像がお祀りされています。
また大黒堂は土、日、月曜日しか公開していないそうなので、要注意です。
なおこのらくがきは、大晦日にすべて白く塗り替えられるそうです。
お茶室
特別公開の際に、大黒堂の左隣にあるお茶室が公開されます。
内部の壁に沿ってイスが設えてあり、立礼席のようになっています。
中央は1段くぼんでおり、枯山水庭園のようになっています。
もとは囲炉裏だったのでしょうか。
側壁には円窓に加えて、三日月の窓があります。
箸供養
2/3、5/3、8/3、11/3の11:00から箸供養(はしくよう)が行われます。
本堂の1階で受付をします。
予約なしでも大丈夫です。
箸納め代として1人300円です。
1階は庭園に臨む書院です。
2階に上ると本堂です。
本堂の中央には五大釈迦像が、その後方の内陣中央には救苦観音像、左手には阿弥陀三尊像がお祀りされています。
11:05頃から太鼓の音と共に法要が開始。
11:35頃までです。
11:50頃まで御住職の法話があります。
終了後、内陣に御焼香をして、1階の書院に降ります。
そちらで精進料理のお膳を頂きます。
食事後、個々に解散ですので、早ければ12:00過ぎには終わります。
八幡散策10へ
洛南の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
2012 6/14 下鴨神社 糺の森でホタル観賞

写真は、19:30頃の楼門
昨年、一昨年と7月第1週に貴船へホタル観賞に出かけていました。
今年は次男もホタルデビューということで、近場にしました。
家族4人で自転車で下鴨神社へ。
先週土曜日に蛍火の茶会が開催され、600匹ものホタルが放たれました。
しかしその日は「人が多いやん」の妻のひとことで却下。
諸々の事情もあり、この日になりました。
夏至が近いこともあり、19:30でもまだ明るいです。
さすがに20:00頃にはすっかり暗くなりました。
問題は鑑賞ポイントです。
奈良の小川や瀬見の小川は、街灯があって明るくホタルもいません。
糺の森の参道を奈良の小川に向かって進む左手に瀬見の小川がありますが、参道の右手の茂みの中に”泉川”があります。
この泉川の上流辺りには結構いました。
奈良の小川の少し南側です。
他にも結構来られていました。
ホタルは貴船の約半分で、多いところで一視野5匹ぐらいです。
子供たちも大喜び。
こちらも貴船より遥かに近かったので楽でした(笑)。
しかし次男がもう少し歩けるであろう来年は、再度貴船に挑戦しようと思います!
アンケートを実施中です。
左サイドバーにあります。
是非ご参加を!
携帯の方はこちら
特別拝観・予約拝観の索引へ
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 12 ) | Trackback ( )
| « 前ページ | 次ページ » |
 -泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
 -火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。
-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。