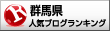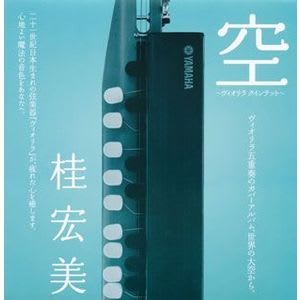昭和20年(1945)8月15日の終戦を境に日本の社会は新たな胎動が感じられた。『須永好日記』を引き続きのぞいてみましょう。
8月19日 人心動揺、軍人は尚、戦うべしと言い、弱きは死なんと言う。そのうち目覚めたものは慾心、軍人は官給品を持ち出し、工員は工具を持ち出す。
8月21日 敗戦処理が始まる。大中島(工場)及び生品飛行場は人の渦が巻いて物品が持ち出される。世は挙げてかっぱらい次第と言うことになった。ラジオは天気予報を始める。連合軍が来ても怖くないと頻りに放送する。
9月7日 言論、集会、結社の自由となりで政治運動も活発となるだろう。
9月16日 前橋に行く。中央前橋駅をはじめ前橋中央部は大部分焼けていた。戦争の惨禍、今更言うまでもないことだが、終戦後初めて見る前橋の敗惨な姿に驚く
さらに先、10月10日の日記には、太田駅前で旧太田署長が社会運動の演説をしているのを須永好は見て、改めて時勢の変化に驚いている。
読書2時間、できないことはない
同志の一人神垣積善は、「須永さんはつねに社会運動をするものは、まず信頼される人間であること、農民運動をするからには、よき農民であり村人であれ。それが出発点だと青年に説いていた」と話す。「須永さん自身がりっぱな精農家であったのはだれでも知っている。股引きを高くまくりあげ、真っ白いすねを出して田植えをする百姓姿が目に残る」また、どんなに忙しい中でも1日最低2時間の読書を皆にすすめたという。朝1時間、夜1時間できないことはないというのだった。実際、神垣が須永家に泊まると、翌朝はいつも「須永さんはきちんと火鉢の前に座って、本を読んでいるのだ、なんのことはない、無言の教えである」と。
【写真】米軍の空襲で戦禍も痛々しい前橋の市街地(共愛学園提供)
【須永好、すながこう】1894-1946 群馬県旧強戸村生。旧制太田中を中退後農業に従事するかたわら農民運動に携わる。郷里強戸村を理想郷へと農民組合を組織し革新自治体“無産村強戸”を実現。戦後は日本社会党結成に奔走、日本農民組合初代会長 衆議2期。
 |
須永好日記 (1968年) |
| 編者 石井繁丸(元前橋市長)他 | |
| 光風社書店 |