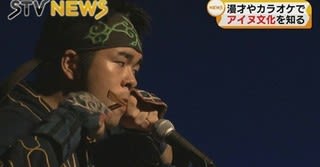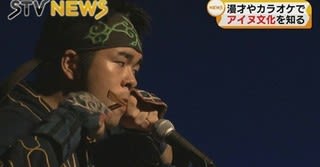北海道新聞 08/24 10:29



アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけたアイヌ施策推進法の施行から24日で3カ月を迎えた。アイヌ文化の保存・継承や観光振興につながる地域計画を策定した市町村は国から交付金を支給され、施策の拡充が期待される。ただ、計画を策定するかや、どういう施策を実施するかは自治体の裁量次第で、地域によってはアイヌ民族の意向が十分に反映されていないとの批判も出ている。同法がうたうアイヌ民族の「誇り」とどう向き合うか自治体の姿勢が問われる。
日高管内平取町は推進法施行をにらんで昨春から計画策定の準備を進めてきた。計画内容や交付金の使い道は、町や平取アイヌ協会、経済団体でつくるアイヌ文化振興推進協議会の会議などで議論を重ね、アイヌ文化を体験する滞在型観光やアイヌ工芸の商品開発を計画に盛り込む方向だ。
7月には文化保存会や民芸組合などアイヌ民族の各団体にも計画案を示して意見交換し、川上満町長は「観光客誘致はもちろん、アイヌ文化を次世代に引き継ぐ事業にしたい」と力を込める。協会の木村英彦会長も「さまざまな団体と協議し、要望を広く反映させることが大切だ」と、今後もアイヌ民族を尊重した施策推進を求める考えだ。
■40市町村が関心
内閣官房によると、交付金制度には道内を中心に約40市町村が関心を寄せている。一部は早期の施策展開のため年度内の計画策定を目指すが、短期間でアイヌ民族の要望をどう反映するか苦慮する自治体もある。
来年4月にアイヌ文化復興拠点となる民族共生象徴空間(ウポポイ)開業を控える胆振管内白老町は、波及効果で町全体の観光客が増えることを期待し、本年度はウポポイと町内の観光施設を結ぶ循環バスの導入など総事業費4700万円の5事業を計画案に盛った。
町は5月から5回行った白老アイヌ協会幹部との意見交換を踏まえ、文化伝承の人材育成やアイヌ文化を生かした商品開発も計画案に盛り込んだ。協会の山丸和幸理事長は「町の発展とアイヌ民族の双方に有意義となるよう、今後も協議を継続してほしい」と期待する。
ただ協会内では「幹部にしか意見を聴いていない」と不満がくすぶる。今月の町議会全員協議会でも町議から「町内のアイヌ民族全体に向けた説明会を開くべきだ」との声が出たが、町は対応を留保したままだ。
合意形成は他の自治体にも課題で、「各部局と調整が必要」(帯広市)、「アイヌ民族関係団体との意見交換に時間をかけたい」(旭川市)と本年度中の策定を見送る自治体もある。
■「腫れ物」扱いも
一方、十勝管内のアイヌ協会会長の1人は地元自治体に計画策定を求めたが、「担当できる部署がない」と難色を示され、知り合いの職員から「『腫れ物には触りたくない』と敬遠する職員もいる」と言われたと明かす。
会長は「門前払いのような対応で、検討する気すら感じなかった。アイヌ民族の権利を保障するはずの施策が、自治体の裁量に左右されるのはおかしい」と訴え、「腫れ物」発言は差別だと憤慨する。
神奈川大の山崎公士名誉教授(人権政策論)は国や自治体の責任を明記する推進法を踏まえ、「各自治体はアイヌ民族を多数加えた審議会や、有識者として採用する専門部署を設けるなど当事者が参画できる枠組みを早急に整えるべきだ」と促している。(金子文太郎、川崎博之、斉藤千絵)
■北大大学院・小田教授に聞く 差別撲滅へ具体的措置を
アイヌ施策推進法はアイヌ民族の「誇り」を尊重すると明記し、差別や権利侵害を禁じた。だが、今でもアイヌ民族の先住性や存在を否定する差別発言がネットにあふれている。北大大学院の小田博志教授(人類学)に先住民族の概念や法が抱える課題を聞いた。
先住民族に厳密な定義はありませんが、国際労働機関の「独立国における原住民及び種族民に関する条約」(1989年)や「先住民族の権利に関する国連宣言」(2007年)を踏まえ、近代以降の植民地化などで不利な状況に置かれた人々というのが国際的な共通認識になっています。
単に「先に住んでいた人々」ではなく、独自の文化や言語などを否定され、土地や資源を奪われるなど抑圧された人々を指す概念です。日本で言えば、明治時代の開拓使事業報告など複数の通達や書状が示す通り、アイヌ民族が土人と差別的に呼ばれ、日本語教育を強いられ、強制移住などで不利な状況に置かれたことは疑いようがありません。
アイヌ民族は混血や同化が進み、民族と呼べないとの言説もありますが、アイヌ民族も和人を含む他の民族も生物学的に一つの種に属しつつ、歴史の中で民族として分かれてきたのです。民族を血統や遺伝子で区別するのは不可能で、「純血」の定義は存在しません。民族は固有の文化や言語、(どの民族に属するかという)自認など複合的な要素で形成されるものです。
そもそもアイヌ民族の文化や言語が危機に追いやられた原因は同化政策にあります。同化が進んでいるからアイヌ政策は必要ないという論理は本末転倒です。日本人は着物や刀を身に着けなくても日本人です。伝統的な暮らしをしていないことは民族の存在を否定する根拠にはなりません。
法はアイヌ民族への差別は違法だと明確にしました。差別された人を救済し、今ある差別を撲滅する具体的な措置が求められます。(聞き手・斉藤千絵)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/337727