北海道新聞 2024/02/11

アイヌ民族の少女が活躍する人気アニメ「ゴールデンカムイ」の大雪像前で披露されたアイヌ民族舞踊=11日午後2時10分、札幌市中央区大通西4(伊丹恒撮影)(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
第74回さっぽろ雪まつり(札幌市、札幌観光協会など主催)は最終日の11日も大勢の家族連れや観光客でにぎわい、雪像を名残惜しそうに撮影する人の姿も目立った。大通会場ではアイヌ民族の古式舞踊が披露され、会場は熱気を帯びた。
北海道新聞 2024/02/11

アイヌ民族の少女が活躍する人気アニメ「ゴールデンカムイ」の大雪像前で披露されたアイヌ民族舞踊=11日午後2時10分、札幌市中央区大通西4(伊丹恒撮影)(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
第74回さっぽろ雪まつり(札幌市、札幌観光協会など主催)は最終日の11日も大勢の家族連れや観光客でにぎわい、雪像を名残惜しそうに撮影する人の姿も目立った。大通会場ではアイヌ民族の古式舞踊が披露され、会場は熱気を帯びた。
北海道新聞 2025年2月11日 20:57(2月11日 21:33更新)

出演者全員で演奏したフィナーレ
【白老】町内のアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」で行われてきた、アイヌ民族の伝統楽器ムックリなど世界の口琴に触れる「ウポポイ・ミュージックフェスティバル2025 ムックリざんまい」は最終日の11日、トンコリ奏者の第一人者オキさんのユニットが演奏したほか、8日間の期間中に出演した全アーティストによる特別公演が行われた。
最終日はまず、「Oki and Rekpo(オキアンドレクポ)」が出演。オキさんはトンコリ3台を曲によって入れ替えながら、レクポさんの歌やムックリ、バンドメンバーのベースやドラムとともに幻想的な演奏を披露した。
オキさんは、曲の合間にチューニングしながら「チューニングはパンツを着替えてるみたいであんまり見せたくないんだよな」などとつぶやくなど、リラックスしたムードを演出。観客も次第に手拍子したり、リズムに合わせて体を揺らすなどしてステージを盛り上げた。
・・・・・・
※「オキアンドレクポ」、「レクポさん」の「ク」はともに小さい字
MonoMaxWEB2/11(火)16:00

「知る」から「感じる」へ。“アイヌ文化”が息づく『ウポポイ』で心に響く特別なひとときを。旅好きライターの体験レポートの画像一覧
北海道といえば、国内旅行の定番スポット。その中でも、次の旅先候補として注目したいのが白老町ポロト湖畔に広がる「ウポポイ(民族共生象徴空間)」。観光地のイメージとは少し異なりながらも、訪れてみれば先住民族アイヌの人々の文化や歴史が驚くほど身近に感じられ、時間を忘れて学びと癒しに没頭できる特別な空間でした。
ここでは、ただ知識を得るだけでなく、「触れて」「体験する」ことで、アイヌ文化の奥深さを肌で感じることができます。伝統的な住まいの再現や舞踊、楽器の音色が紡ぎ出す豊かな世界観は、心を静かに癒し、自然と調和して生きてきたアイヌ民族の思想へと引き込んでくれるものばかり。難しく思えるテーマも、実際に体験してみるとぐっと親しみやすく、魅力的に映ります。
何か新しいことに挑戦したい、自分をリフレッシュさせたいという方にもぴったり。知的好奇心を刺激し、自分自身をアップデートできる体験が待っています。今回は、プレスツアーで体感したその魅力をたっぷりとお届け!
アイヌ民族の歴史と文化を伝える「ウポポイ」とは?
白老町ポロト湖畔に位置する「ウポポイ(民族共生象徴空間)」は、アイヌ文化の復興と創造の拠点として2020年にオープンしました。東京ドーム約2個分の広大な敷地内には、道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、五感で体験する「国立民族共生公園」、そして「慰霊施設」などが揃っています。「ウポポイ」とは、アイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味する愛称です。
園内ではアイヌ語が第一言語として使われており、施設名や展示解説にはアイヌ語が先頭に表示されていました。スタッフ同士もアイヌ語のニックネームで呼び合い、訪れる人々を親しみのある挨拶で迎えてくれるのも印象的。また、園内を循環する無料の電動バスは、アイヌ文様をモチーフにしたデザインが特徴的。足の悪い方や小さなお子さん連れの方にも優しい設備が整っています。
幻想的な「いざないの回廊」から訪問スタート!
新千歳空港から車で約40分で到着するウポポイ。駐車場からエントランスまでは「いざないの回廊」と呼ばれる幻想的な通路を通ります。壁面には自然や動物のデザインが描かれており、まるで森の中を歩いているかのような感覚になります。これから始まるアイヌ文化との出会いに、自然と期待が高まります。
回廊を抜けるとお土産ショップや軽食が楽しめるカフェがある「歓迎の広場」が広がり、その後には円形のエントランス棟が待っています。ここまでは無料エリアのため、お散歩だけでも気軽に立ち寄れます。正面にはウポポイPRキャラクター「トゥレッポん」が出迎えてくれます。「トゥレッポん」はアイヌ語でユリ科ウバユリ属の多年草「オオウバユリ」を意味するturep(トゥレㇷ゚)から名付けられたそう。可愛らしいキャラクターグッズも園内で多数販売されています。
弓矢体験「アㇰシノッ」で狩猟の心に触れる
館内の説明を聞いたあと、早速体験学習館へ向かいました。最初に挑戦したのは、弓矢体験「アㇰシノッ」。これは、アイヌ民族の子どもたちが楽しんでいた弓矢遊びを再現したもので、狩猟の作法や技術を学ぶ目的があったそうです。使用する矢は安全のため先端が尖っておらず、熊やホタテの貝殻を模した的を狙います。
実際に挑戦してみると、弓を引くには意外と力が必要で、3本トライしましたが的にはかすりもしませんでした(笑)。それでも、スタッフの丁寧な指導のおかげで楽しく体験することができました。雨の日でも室内で楽しめるところも魅力的です。
アイヌ民族の伝統料理「オハウ」に舌鼓
「オハウ」は具だくさんの汁物で、アイヌ民族の食生活の中心にあった料理。地域で採れた野菜や肉・魚などを塩や油でシンプルに煮込んだもので、素材の味を存分に楽しめます。試食体験では、園内で作られた「サッチェㇷ゚」(干した鮭)や野草茶「エント茶」もいただきました。
「オハウ」のあっさりとした塩味は驚くほど美味しく、素材の味が引き立っていました。干した鮭は、鮭の旨味がギュッと凝縮されていて、パサパサしてないしっとり感にも感動!どちらもアイヌ文化の知恵が詰まった逸品です。「エント茶」は、シソ科のナギナタコウジュをアイヌ語でエントと呼ぶそうで、こちらも園内の畑で栽培されています。ハーブティーのような独特の風味でクセがなく飲みやすく、心も体も温まりました。
また、「歓迎の広場」にある『スイーツカフェ ななかまどイレンカ』では、「パピㇼカパイ(アップルパイ他季節のパイ)」も試食しました。「パピㇼカ」はアイヌ語で「豊作」などを意味する言葉です。自家製のサクサク生地と大きめにカットされたりんごのジューシーさが絶妙にマッチし、甘さも控えめで食べ応え抜群でした。このパイもぜひ試していただきたい一品です。
アイヌ語発音体験「イタㇰ トマリ」でことばに触れる
アイヌ文化の根幹をなす“ことば”を、聞いて、話して、体感できる「イタㇰ トマリ」。ここでは、インスタレーションアートを通じてアイヌ語を“生きたことば”として学べます。
アイヌ語の音声と連動した映像パネルでは、地域によって異なる挨拶の表現や、発音が似ていても異なる意味を持つ単語などを学習できます。また、大型モニターに映し出されるアイヌ語を声に出して読むと、その言葉が示す動物や楽器などの映像が現れる仕掛けも。耳で聞き、口で発音することで、自然とアイヌ語への理解が深まりました。
アイヌ語が他の言語と系統関係が認められていない「孤立言語」であることを知ると、その独自性にさらに興味が湧きます。発音が難しいカタカナ表記に最初は戸惑いましたが、体験を通して言葉を覚える楽しさを実感しました。
民族衣装「アミㇷ゚」や民族楽器「ムックリ」を体験
チセ(家屋)群が再現され、アイヌ民族の伝統的な生活空間を体感できるコタン(集落)エリアでは、室内の見学や儀礼の見学、民族衣装を着用して写真撮影が可能。衣装は子ども用から大人用まで20着ほど用意されており、気軽に体験できます。
アイヌの民族の衣装は地域によって異なるパターンがあるそうです。まず、シナノキ科の樹皮など木の繊維を布にして作った「アットゥㇱ」があり、その後布が手に入るようになると刺繍文化が発展。地域ごとの文様や技法の違いにより、「チカㇽカㇽペ」、「ルウンペ」、「カパラミㇷ゚」、「チヂリ」に分けられるそうです。刺繍部分に見られる尖ったツノのようなデザインが印象的です。美しく力強い結界のようなデザインに惚れ惚れ♡
その後、アイヌ民族に伝わる竹製の口琴の一種「ムックリ」も体験させてもらいました。竹製の薄い板(弁)に紐がついており、この紐を引っ張ることで弁が振動し音が発生。その音を口腔内で共鳴させ、口の形を変えたり、息を吸ったり吐いたりすることで、さまざまな音色を演奏できる楽器。体験では、スタッフの方からムックリの持ち方、鳴らし方、そして音色を変化させるコツを丁寧に教えていただきました。しかし、実際に音を鳴らしてみるとこれがなかなか難しい!竹の弁を振動させるタイミングや口の動きの調整が思った以上に繊細で、音を出すだけでも苦労しました。
伝統芸能上演「イメル」で感じる魂の響き
ウポポイを訪れたら見逃せないのが、伝統芸能「イメル」・「シノッ」の鑑賞。儀礼や日常生活で親しまれてきた歌や踊り、口承文芸、楽器演奏を一度に堪能できる貴重な機会。中でも、重要無形民俗文化財に指定される「アイヌ古式舞踊」は、その圧倒的な美しさと迫力で見る者を魅了します。
演じるのは、ウポポイの職員であり、アイヌ文化を受け継ぐ伝承者たち。喉を駆使した独特の発声や掛け声、巻き舌を用いた旋律は、力強くも心に染みわたる響きでした。複数人の声が織りなすハーモニーは、五線譜では表しきれない奥深い音楽の世界を感じさせ、初めて聞く音色に引き込まれました。
鑑賞中は自然との一体感を感じさせる表現力に心が震え、思わず涙が込み上げてきました。この素晴らしい体験が約25分、しかも無料で楽しめるのは驚きです。ぜひ一人でも多くの人に、この感動を味わってほしいなと思いました。
国立アイヌ民族博物館で学ぶアイヌ民族のスピリッツ
高床式を模した建物は斬新なデザインで、1階にはシアターやライブラリー、ミュージアムショップ、2階にはポロト湖を一望できるパノラミックロビーと展示室があります。
基本展示室は「私たちのことば」「私たちの世界」「私たちのくらし」「私たちの歴史」「私たちのしごと」「私たちの交流」の6つのテーマで構成されており、多角的にアイヌ文化を紹介しています。
特に心に響いたのは、アイヌ民族が大切にしてきた「カムイ(いわゆる神)」という価値観です。アイヌの人々は、火や水、太陽、月、動植物など、自然界のあらゆるものに魂が宿ると考え、これらの中でも人間の役に立ったり、強い影響力を持ったりするものを「カムイ」として敬ってきました。こうした自然との共生を重んじる姿勢は、現代を生きるすべての人々にとって、大切な学びがあるように思いました。
アイヌ民族の重要な儀式である「イオマンテ」も紹介されていました。「キムンカムイ」(山の神)として崇められるクマを神の国へ送り帰す儀式には、自然への感謝と再訪を願う祈りが込められており、アイヌ文化の奥深さに触れることができました。
ミュージアムショップでお土産探し
ミュージアムショップには、各地の作家が手がけたアイヌ工芸品やウポポイ限定のお菓子やグッズ、関連書籍が並びます。オンラインショップもあるので、遠方の方でもアイヌ文様の商品を手に入れることができます。気になる方はぜひチェックを!ウポポイ公式オンラインショップ
いろいろ欲しいものがあったのですが、私はエント茶とアイヌ文様がデザインされた鉢巻きを購入しました。鉢巻きは柄や色の種類が豊富で迷いましたが、普段使いしやすそうなデザインをセレクト。とても気に入っています♡
「ウポポイ」から帰ってきても、アイヌ文化の工芸や織物が気になってしまい、ネットオークションでこちらの太めの鉢巻きと壁掛けを買ってしまいました。
さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感できる「ウポポイ」。今回ご紹介したもの以外にも、木彫りや刺繍の体験、口承文芸の実演など、多彩なプログラムが用意されています。新たな発見をする楽しさを存分に味わえる施設で、1日中いても飽きることはありません。むしろ時間が足りないくらいなので、あらかじめ軽くスケジュールを立てて訪れるとスムーズだと思いました。
私も次回は友人や家族を連れて、改めてゆっくりと訪れたいと思います。ウポポイで得た感動を共有しながら、アイヌ文化の奥深さに再び触れる機会を楽しみにしています。
【ウポポイ(民族共生象徴空間)】
所在地:北海道白老郡白老町若草町2丁目3
TEL:0144-82-3914
アクセス:JR白老駅(北口)から徒歩約10分、
札幌から約1時間、 新千歳空港から約40分
閉園日:月曜および3月1日〜10日(令和6年度)
※祝日または休日の場合は翌日以降の平日休み
※但し2月10日は開園
変則的な閉園日や開園日があります。詳しくは公式ウェブサイトで確認を。
公式サイトhttps://ainu-upopoy.jp/
文・撮影/鈴木恵理子
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/monomax/trend/monomax-261586
バチカンニュース 10 2月 2025, 18:26

教皇フランシスコと先住民族の代表者たち 教皇一般謁見で (写真資料) (Vatican Media)
教皇フランシスコは、国際農業開発基金が開催した「先住民族グローバルフォーラム」にメッセージをおくられた。
国際農業開発基金(IFAD、本部:ローマ)で、2月10日、11日の両日、「先住民族グローバルフォーラム」が開催されている。
「先住民族の自主決定権:食糧上の安全保障と主権への道のり」をテーマにした今回のフォーラムに、教皇フランシスコはメッセージを寄せられた。
その中で教皇は、このテーマは先住民族とその古くから伝えられてきた遺産を人類家族を豊かにするものとして認識するようにわたしたちを招いている、と述べられた。
そして、先住民族とその伝統遺産は、複雑な挑戦と少なからぬ緊張を帯びた現代に、希望の地平を切り開くもの、と記している。
先住民族の独自の文化とアイデンティティーを守りぬく権利を擁護することは、先住民族の人々の社会貢献の価値を認め、その存在と、その生活に不可欠な天然資源を保護する必要につながると教皇は指摘。
また、さらなる脅威として、多国籍企業や大口投資家、国家による耕作可能な土地の収奪の拡大を挙げ、これらの行為は、尊厳ある生活を営むべき共同体の権利を脅かし、害をもたらすものと警告している。
教皇は、土地、水、食料は単なる商品ではなく、人々の生活、人と自然の絆の基盤そのもの、と強調。先住民族の権利を擁護することは、正義の問題であるのみならず、すべての人にとって持続可能な未来を保証することでもある、と述べている。
会議の実りが各国の指導者に適切な対応を促すことに役立ち、人類家族が誰一人排除され、取り残されることなく、皆が共通善の追求のために一致して歩めるようにと教皇は神に祈られた。
株式会社STARBASE 2025年2月11日 12時00分
GOMA 「ひかりの世界」アートワーク
2024年表参道GYRE GALLERY(ジャイルギャラリー)で開催された、画家・ディジュリドゥ奏者GOMAの大規模な展覧会『ひかりの世界』。その広い会場を包み込むように流され、絵画作品への没入度を高める一助になっていたアンビエント作品が、配信でもリリースされることとなった。
昨年6月から連続配信が行われた「GOMA & The Jungle Rhythm Section」、「GOMA Homeworks」を「動」と「快楽」のサウンドとするなら、GOMAの心象風景、及び彼が描き出す絵画作品と密接に結びついた「静」と「慈しみ」のサウンドとなっている。
一筆書きのようなディジュリドゥの深く潜るような倍音と、フィールドレコーディングも敢行された環境音・自然音のみで構成されたその世界は、全4曲の中で緩やかに変容を遂げつつ、聴く者を安寧へと誘う。また、各曲20分バージョンに加え、禅の世界に影響を受け、より長い瞑想や作業に対応した40分バージョンも今後配信予定。
さらに、リリース同日の2月17日月曜よる11時15分から放送予定の「激レアさんを連れてきた。」にも出演することが発表された。
●リリース情報
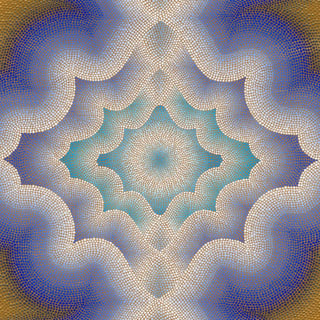
アーティスト: GOMA
タイトル: ひかりの世界
発売日:2025年2月17日(月)
収録曲:
1. 内観
2. 水鈴浴
3. 月光浴
4. 森林浴
作曲: GOMA
レーベル:JUNGLE MUSIC
配信URL: https://lnk.to/GOMA_HNS
Recorded,mixed by Tamotsu Ooya at Fujiyama Recordings 音泉
Mastered by OH SOKKUN at Fujiyama Recordings 音泉
Cover Art :GOMA
A&R :Sumie Morimoto (JUNGLE MUSIC)
●GOMAプロフィール
オーストラリア先住民族の伝統楽器「ディジュリドゥ」の奏者・画家
現在までに15枚のオリジナルアルバムを発表
年に一回のペースで個展を開催
Official Website : https://gomaweb.net
Instagram: https://www.instagram.com/goma_official/
X: https://x.com/goma_didgeridoo
日刊スポーツ 2/11(火) 7:00

<番記者プロデュース>
日本ハム新庄剛志監督(53)は今季、新たに「投手2人の野手3人。5人の“スター候補”がつくれたら。イメージは投手8人、野手7人の中から」と若手の台頭を待つ。昨季は田宮、水谷、水野らが全国のプロ野球ファンにも名前が知られるほどの活躍でチームは2位躍進を遂げた。日本一を目指す中で次に飛び出てくるのは誰か。番記者が選んだ日本ハムの「ネクストブレーク・フィフティーン」を紹介する。【取材・構成=木下大輔】
◆名前
孫易磊(スン・イーレイ)
◆出身地
台湾
◆誕生日
2005年(平17)2月10日(20歳)
◆ドラフト、年数
中国文化大へ進学した23年9月に日本ハムと4年契約。今季で2年目
◆通算成績(2軍)
15試合、2勝2敗、防御率3・86
◆投打
右投げ左打ち
◆サイズ
身長183センチ、体重93キロ
◆今季推定年俸
600万円
◆寸評
育成2年目を迎えた台湾出身の最速157キロ右腕。球団OBの陽岱鋼と同じく、身体能力に優れる台湾先住民族のアミ族出身。高校1年までは一塁手や外野手で投手歴は4年ほど。昨季は体づくりをしながら経験を積んだ伸びしろたっぷりな“台湾の至宝”。
https://news.yahoo.co.jp/articles/50258eba8892b4ecedc4b7d46f8c7151eead79ed
Motociclismo February 11, 2025

本来であればもう一つのスリリングなラリー・スウェーデンの版であるべきところが、代わりにモータースポーツと先住民族サーミの人々との間の優先順位の戦いに変わってしまった。
イベントがウメオでの4年目に入る中、2022年にさらに北へ移動したことにより、長年の本拠地であるヴェールムラントで悩まされていた雪不足の問題が解決された。しかし、その結果、異なる種類の対立の扉が開かれた—それは、ラリーカーの高オクタンの轟音と数世代にわたるトナカイの飼育の伝統との対立である。
現在、ラリーが始まるまであと数日のところで、緊張はこれまで以上に高まっている.
トナカイの飼育 vs. ラリー競技—微妙なバランスの取り方
核心の問題は?ヴェステルボッテンはトナカイの放牧に最適な土地であり、サーミの人々—ヨーロッパで唯一認められた先住民族—は、ウメオへの移動以来、ラリーの影響についての懸念を表明している。
2022年には、予期しないトナカイの移動によりÖrträskテストが中止された。今年は、地元のサーミグループが少なくとも4つのステージのキャンセルを求めている:
最近の論争の焦点は?ラリーの数日前にウメオ近くで発生した三頭のトナカイの不審な死であり、一部のサーミの指導者たちはこれをイベントに関連したヘイトクライムだと考えています。
スウェーデンにおけるサーミの権利のための長い闘い
サーミは長い間、より大きな認識と権利を求めて闘っており、ラリー・スウェーデンによる混乱に対する彼らの闘いは、土地を巡る長い歴史の最新の章に過ぎません。
最初から、サーミコミュニティは、自分たちの領土でのラリーイベントを問題視していることを明確にしました。スウェーデンサーミ連盟は、政府に対してラリー許可の取り扱いと、トナカイの放牧村への影響について再考するよう求めています。
「県庁は、私たちの放牧地域の一部でトナカイの飼育を不可能にしています。私たちは移住を余儀なくされており、これはトナカイの飼育者にとって壊滅的な結果をもたらします。」
—シルヤ・ヨンソン・マークルンド、ランサーミ村の議長
これらの強い反対にもかかわらず、ヴェステルボッテン県政府は1月24日にラリー許可を承認しました。この動きは緊張をさらに高めるだけの結果となりました。
当局は懸念を退ける—安全リスクのみがステージをキャンセルする
スウェーデンの公式は引き下がるつもりはありません。ペール・ルンドストローム、ヴェステルボッテン県の最高法務責任者によると、ラリーステージはレースの時間にトナカイが道路にいる場合のみキャンセルされるとのことです—放牧地への長期的な影響によってではありません。
「交通安全が確保できない場合、その区間は実施されるべきではありません。」
この立場はサーミの指導者たちを苛立たせている。彼らは全体のプロセスが集会の主催者に有利であり、先住民の懸念を無視していると主張している。
トナカイの死後に緊張が爆発—サーミの指導者たちはヘイトクライムを疑う
論争は暗い展開を見せ、2月2日にウメオ近くで3頭のトナカイが死んでいるのが見つかった。集会の数日前のことである。地元警察は直ちに捜査を開始し、死体に銃弾の傷が見つかったことを確認した。
「私は自分の目で銃弾の穴の証拠を見ています。彼らは自然死ではなく、捕食者によっても死んでいないと私の判断では言えます。」
—ヨハン・アンデルソン、サーミのトナカイ飼育者
一部のサーミの指導者たちは、殺害のタイミングは偶然ではないと考えており、集会を巡る緊張の高まりが影響を与えた可能性があると述べている。
「集会のようなイベントが、人々をこんなことをさせるなんて恐ろしいことです。私はランサーミ村に対するこのようなヘイトクライムを経験したことがありません。」
—マイディ・エイラ・アンデルソン、ランサーミ理事会メンバー
スウェーデン警察が依然として調査を行っているため、ラリー・スウェーデンの支持者や主催者との公式な関連性は確認されていません。しかし、この事件はステージのキャンセルを求める声を強めています。
時計は刻々と進んでいる: ラリー・スウェーデンは重要なステージを失うのか?
ラン・サーミ村は公式に許可を不服申し立てを行い、ヴェンナス、ヴェステルビーク、ウメオについて、ステージ自体と輸送ルートが重要な放牧地を妨げていると主張しています。
スウェーデンの交通機関、Transportstyrelsenは、2月14日にラリーが始まる前に判断を下すよう圧力を受けています。
「何とも言えませんが、私たちはこの問題を最優先で対処し、緊急に対応します。」
—マーティン・アンデルソン、Transportstyrelsenプレスマネージャー
もし不服申し立てが時間内に審査されない場合、ラリーは予定通り進行しますが、予期しないトナカイの出現があれば、最後の瞬間にキャンセルを余儀なくされる可能性があります。
ラリー・スウェーデンの主催者がイベントを擁護: “私たちは受け入れられなければならない”
状況がエスカレートする中で、ラリー・スウェーデンのイベントディレクター、エリック・オーストロムは緊張を和らげるために努めており、イベントの前後を通じて土地所有者やトナカイの飼育者と密接に協力していることを強調しています。
「私たちは毎年1週間、ウメオを訪れ、実際の競技日は4日間です。私たちは土地を借りる人々に受け入れられなければなりません。」
しかし、サーミの指導者たちにとって、協力だけでは不十分です—彼らはラリーの許可がどのように与えられるかに実質的な変化を求めています。
判決:ラリー・スウェーデンは変わらざるを得ないのか?
ラリーカーが雪に覆われた森林に向かう準備を進める中で、このスポーツはこれまでで最大の文化的および環境的ジレンマの一つに直面しています。
一つのことは明らかです:ラリー・スウェーデンを巡る戦いはまだ終わっていません。
現時点では、このイベントは時間との戦いです—モータースポーツファンを楽しませるだけでなく、その未来を定義する可能性のある文化的および環境的な交差点を乗り越えるために。
ATLAS 2025年2月11日 / 2025年2月11日

オーストラリアには「マリーマン」と呼ばれる巨大な地上絵が存在する。
1998年6月28日、マリーの町から南オーストラリア州クーパーペディの町へ飛んでいたチャーター機のパイロットであったトレック・スミス氏がフィニス・スプリングスの高原に巨大な人の絵が描かれているのを発見。
手にはオーストラリアの先住民族であるアボリジニが狩りに用いる投げ棒を持ち、胸には傷がある姿が描かれていた。地上絵の規模は縦4.2 キロ 、幅28キロに及び、線の太さは35メートル、深さは25~30センチほど。現在確認されている中では世界で2番目に大きい地上絵だという。
この地上絵については、謎も多いが「製作者は現代人である」可能性が有力視されている。中でも2002年に亡くなったオーストラリアの芸術家Bardius Goldberg氏の作品だった可能性が高く、彼はかねてより「宇宙から見える作品」を作ることに興味があったこと、地上絵の近くからアボリジニの歴史を称える銘板が発見されたこと等の状況証拠が複数存在している。
しかし、中にはマリーマンが現代人の作品ではなく、非常に古いものである可能性があると述べる人たちもいるようだ。
海外のオカルト系YouTubeチャンネルの「MrMBB333 」は自身の動画にて、チリに存在する地上絵の「アタカマ・ジャイアント」と比較し「アタカマ砂漠に作品を作った古代の人々はGPSの助けを借りていなかった」と指摘。マリーマンも古代のアボリジニの人々が作る事ができたはず、と語っている。
この動画は2月18日に公開されてから68,000回以上視聴され、様々な感想が寄せられていた。中には「巨人が大地に描いたものではないか」「宇宙人へ送るメッセージでは」というコメントもされていた。
だが、実際のところマリーマンの姿は1946年に記されたアボリジニの文化を紹介する本に掲載されていた内用や写真と類似する点が多い。その事実を踏まえると、やはりマリーマンは現代人の手によるものだと考えた方が良さそうだ。
山口敏太郎タートルカンパニー ミステリーニュースステーションATLAS編集部)
鐙麻樹北欧・国際比較文化ジャーナリスト|ノルウェー国際報道協会理事 2/11(火) 11:01
1月末、ノルウェー最北端の都市トロムソで「北極圏ユース・カンファレンス」(Arctic Youth Conference)が開催された。
北極圏の急速な変化がもたらす課題や機会について、若者たちが話し合うためのプラットフォームとして誕生したこの会議は、北極評議会が主催する。
北極評議会は、カナダ、デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島を含む)、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、米国の8カ国と6つの先住民グループによって構成されている。
北極圏の共通課題について協力・調整を促進する政府間フォーラムである。
大人が集まる北極圏会議Arctic Frontiersの直前に開催されたユース会議。両方参加する人もいて、「北極圏の課題解決にユースは絶対に欠かせない」という意識が共有されていた 筆者撮影
北極評議会の議長国のもとで開催される、初の若者主導の会議
北極評議会の広報チーフ、クリスティナ・バーさんは、「これまでも若者を巻き込んだ会議はありましたが、このような形式は初めてです。現在の北極評議会の議長国であるノルウェーが、若者が自ら創設し主導する会議として設計することを決定しました」と取材で語った。
このカンファレンスでは、軍事や地政学の議題を除き、環境保護、ウェルビーイング、汚染、社会的課題、アートなどが主要なトピックとして取り上げられる。形だけの取り組みに終わらないよう、若者たちが実際に会議の企画や運営に参加できる仕組みが整えられている。

北欧やアラスカなどの「北極圏の先住民ユースたち」が、対話する場所も特設されていた。筆者撮影
世代を超えた対話
「18歳から30歳までの参加者を主に歓迎」とされているが、実際には年長者の姿も多く見られた。これは、若いリーダーと上級職員や専門家が関与し、世代間の対話を促進することが目的だからだ。
「私はもう若くないが、若者を応援したい」と熱意溢れる参加者もおり、彼らは自らを「シニア・ユース」と表現していた。
「シニア・ユース」という初めて聞く英語に筆者は驚いて、「それって何!?」と聞くと、大人たちは照れながら、「……応援したい気持ちの表れだ」と説明した。筆者撮影
先住民としてのアイデンティティ
会場で筆者が出会ったのは、グリーンランド出身のダオラナ美雪さん(1999年生まれ)。日本人の母を持ち、ノルウェーのトロムソ大学で先住民学を専攻している。彼女にとって、このような場は非常に貴重だ。
「先住民として生まれることは、政治の中に生まれるということです。自分の権利が侵害されているから闘うという選択肢しかない。これは単なる趣味や仕事ではなく、私の人生そのものです」と語る。
グリーンランドを巡る緊張
近年、トランプ元大統領の「グリーンランド買収」発言が世界的に注目を集めた。これについて美雪さんは、「米国は採掘や軍事支配を通じて他国を搾取し、より多くの権力と富を得ようとしている。私たちは売り物ではありません。私たちは物ではなく、感情を持つ人間でし」と話した。
デンマークとの交渉も人間性を奪うものです。どうして人を買うという発想が出てくるのか。私たちは奴隷ではないし、土地を明け渡すつもりもありません。
米国はすでに先住民を搾取しており、現在も、過去も、そして現在も、パレスチナの人々や、アラスカの北極圏先住民など、アメリカ大陸の先住民を搾取しています。ですから、私たちは何に対しても抵抗します。
私たちはコラボレーションにはオープンです。自分たちで話し合い、未来を決定します。ですから、私たちを人間として見てください、と言いたいですね。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b179fe831ed5f8da941abb835adb1ec5f683808f
ねとらぼ 2025/02/11 18:50(公開)
本州の最北端に位置する「青森県」。東は太平洋、西は日本海、北は津軽海峡に面し、豊かな自然と美しい景観に恵まれた場所です。三内丸山遺跡や弘前城など、歴史を感じさせるスポットも多くありますよね。
今回ねとらぼでは、「『地元民しか読めない!』と思う青森県の市町村名は?」というアンケートを実施します。地元民以外は読み方に悩んでしまいそうな市町村名にご投票ください。まずは、青森県の市町村から3つの町をピックアップして紹介しましょう!
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
大鰐町
「大鰐(おおわに)町」は青森県津軽地方の南端に位置する自然豊かな町です。800年以上の歴史を持つ「大鰐温泉」があり、古くから津軽の奥座敷として親しまれてきました。
大鰐という地名は、はるか昔に大きな阿弥陀如来像があることから、「大阿弥陀」と呼ばれていたものが徐々に変化したと考えられています。大阿弥(おおあみ)が大阿子(おおあね)と変化し、大浦為信の津軽統一以降は、大きなサンショウウオ(鰐)が棲んでいたという伝説から、「大鰐」と記されるようになったといわれています。
田子町
青森県の最南端にあり、岩手県・秋田県との県境に位置する「田子(たっこ)町」。田子と書いて「たっこ」と読む地名の由来には諸説ありますが、先住民であるアイヌ民族の言葉で「小高い山」を意味する「タプコプ」とする説が有力です。
田子町には獅々内(シシナイ)や佐羽内(サバナイ)など、アイヌ語が起源だとされる地名がいくつも残っています。
階上町
「階上(はしかみ)町」は青森県の最東端に位置する、県内で最も早く朝日が昇る町です。「はしかみ」という地名は、かつてこの地域が「階上郡」と呼ばれていたことに由来します。
奈良時代から平安時代にかけて行われた蝦夷征討の際に、陸奥の国は北に向かって拡大を続けるにあたり、作戦のたびに新たな郡を6つずつ設けました。6つの郡のうち北端の郡は軍事拠点とされ、「はしかみ」や「かみ」の名が付けられたと考えられています。「はし」とは北・北端、「かみ」は行政府・最前線・根拠地などの意味だとされています。
「地元民しか読めない!」と思う青森県の市町村名は?
ここで紹介した3つの町以外にも、青森県には地元に住んでいる人でなければ読み方がわからないような地名が数多くありますよね。
なお、選択肢は青森県内にある自治体(10市22町8村)のうち、ひらがな名である「むつ市」「つがる市」「おいらせ町」を除いた37の自治体となります。この中から、あなたが地元民しか読めないと思う自治体名にご投票ください。
また、各自治体の地名にまつわる雑学や、その地域のおすすめスポットの情報なども、コメント欄にぜひお寄せください。たくさんの投票をお待ちしています!
STV 2025/02/11
応援したい自治体に住民税を納め、返礼品を受け取る「ふるさと納税」。
自治体にとっては貴重な財源の1つですが、寄付金を増やそうと自治体では様々な取り組みが始まっています。
室内に響き渡る太鼓の音色。
迫力満載の体験です。
北海道妹背牛町で1月、町内を回るバスツアーが開かれました。
マチの魅力を知ってもらうことが目的ですが、案内している人は・・・
(妹背牛町 田中一典町長)「みなさん札幌からですか?妹背牛町長の田中でございます。おはようございます」
「町長」自らガイドをしていました。
まずは町長室。
広い会議室で妹背牛町について熱く語ったりー
昼ご飯も参加者に混じって一緒に食べます。
なかなか体験できないツアーに参加者も大盛り上がりでした。
(ツアー参加者)「普段お目にかからない方とお話できたり。このツアー大好き」
(ツアー参加者)「マチのトップの方が案内してくれるのはないので、とても勉強になります」
でも、なぜ町長自らがガイドをしているのか?
企画したツアー会社はこう語ります。
(北海道中央バス 戎谷侑男さん)「(ツアーを通して)実際に納税をする方もいますし、移住する方もいる。(ツアーで)地域の元気をつくれているような気がします」
妹背牛町は人口2500人ほどの小さな町。
その魅力を知ってもらい「ふるさと納税」などで応援してもらために、町長自らが発信しているのです。
(妹背牛町 田中一典町長)「どういうものを都会が求めているのか。それによってふるさと納税が持っているパワーの磨きをかけていくことが、これからの時代の大きな力になると思います」
一方、胆振の白老町では気軽にマチを応援してもらおうと、アイヌ文化を伝える「ウポポイ」に設置したのが…
ふるさと納税の「自動販売機」です。
寄付した人は返礼品として、ウポポイの入場券や食事券などを貰うことができます。
(白老町 大黒克己副町長)「旅行先で気軽に寄付行為が出来るというのがポイント。ここでふるさと納税を考えていただいて、返礼品を使って楽しんでいただければと思います」
自分のマチを「ふるさと納税」などで応援してもらおうと、自治体では様々な知恵を絞っているようです。
SPICE 2025/02/11 17:00
この春、国立科学博物館にて特別展『古代DNA―日本人のきた道―』が開催される。会期は2025年3月15日(土)から6月15日(日)まで。
特別展『古代DNA―日本人のきた道―』報道発表会の様子
開幕に先駆けて開かれた報道発表会では、総合監修者である国立科学博物館長・篠田謙一氏、国立歴史民族博物館名誉教授・藤尾慎一郎氏による開催趣旨や見どころの解説が行われた。さらに、本展の公式サポーター・音声ガイドナビゲーターを務める井上咲楽もゲストとして登場し、笑顔と大胆な質問で発表会を明るく盛り上げた。本記事ではそのトークセッションの様子を交えつつ、特別展『古代DNA―日本人のきた道―』が一体どんな展覧会なのかをお伝えする。
ゲノム解析で読み解く古代人の歴史
遺跡から発掘された古代人の骨に残るごくわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる「古代DNA研究」。本展はその古代DNA研究と、日本各地の貴重な考古遺物、超高精細の頭骨CG映像などを展示し、古代人の知られざる姿に迫るものだ。彼ら一人一人はどのようなヒトだったのか、そして私たち “日本人” はどのように成り立ってきたのか? ゲノムデータ解析と考古学の、ともに最新の研究成果に触れる貴重な機会となるだろう。

DNA情報に基づいて作成された船泊23号 (北海道の縄文人)復顏 国立科学博物館蔵
まず資料として示された一枚の写真は、「DNA情報に基づいて作成された船泊23号(北海道の縄文人)復顔」。古代DNA研究は2006年の新技術開発によって飛躍的な進歩を遂げ、今では現代人と同じレベルでの解析も可能になっているという。たとえ縄文人であっても、髪の太さや瞳の色など、「骨のかけらがあれば、これだけのことがわかります」と篠田館長は力強く語る。
展覧会は全6章+2つのトピックで構成され、はじめの4章でそれぞれ旧石器時代(1章)、縄文時代(2章)、弥生時代(3章)、古墳時代(4章)の人々や社会について掘り下げていく。そして5章では南の島で琉球列島集団が形成されていくさまを、6章では北の大地におけるアイヌ文化の成り立ちについて紐解くという。
4号人骨 旧石器時代 沖縄・白保竿根田原洞穴遺跡 沖縄県立埋蔵文化財センター蔵
旧石器時代(およそ2万7000年前)の人骨「4号人骨」は、日本国内で発見された全身骨格としては最も古いもののひとつ。いわば現時点での“最古の日本人”である。国立科学博物館では、2022年に古代ゲノム解析でノーベル生理学・医学賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士のグループと共同でそれらの人骨の研究を進めており、本展ではその最新の研究成果を見ることができるそう。
大陸から稲作技術を携えてやってきた「朝鮮半島青銅器文化人」は、縄文人とは異なるDNAを持ち、見た目や考え方も異なっていたという。会場で頭骨を見比べて、それぞれの特徴を実感するのが楽しみである。篠田館長曰く、歯の大きさや眼窩の丸み、全体のタテヨコ比率などに違いが見られるそうだ。
上の画像の頭骨は鳥取県の青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡から発掘されたもの。会場では、その頭骨やDNA分析をもとに制作されたおよそ1800年前の弥生人男性の復顔像にも会える。ちなみにこの復顔像には鳥取県が実施した公募コンテストで「青谷 上寺朗(あおや かみじろう)」との名前が付けられている。見た目だけでなく、働きぶりにも親近感を覚える存在である。
貴重な考古資料の数々を展示
一方、考古学的に貴重な遺物の数々も見逃せない。縄文時代の草創期のものとみられる「日本最古の土偶」には注目だ。「土偶は祈りの道具であると同時に、定住生活に伴って発生しだしたストレスを発散・昇華させるための文化装置だった」という藤尾名誉教授の解説は非常に興味深い。会場でさらに詳しく知りたいポイントである。
さらに、生命を生み出す女性の像だけではなく、狩りの成功や豊穣を祈るための、動物の土偶とも言えるモノも造られていた。クマはその危険性や力強さから特別な動物としてもあがめられていたようで、特に東北地方の遺跡からは写真のようなクマ型の土製品が出土するのだそうだ。
古墳時代になると大陸から馬を飼育する技術などがもたらされ、馬をかたどった埴輪(はにわ)が制作される。なんとも愛らしいこの馬形埴輪は、出土した大阪以外では初のお披露目となるそう。
筆者は古代人というと、「大昔に縄文人がいて、そこへ弥生時代に渡来人がやって来て置き換わったのかな?」と大雑把に考えていたが、実際のところ古墳時代になってからも継続的に渡来人はやって来ていて、まだ列島に住む人々は均質ではなかった……と聞いてびっくり。古墳時代人は、現代日本人に近いDNAを持つ人と縄文人のDNAを色濃く残す人との集合体だったのだそうだ。解説中には篠田館長から「(これまで〇〇と考えられていたが、)実はそんな単純な話ではないと分かってきました」との表現が何度も飛び出し、それだけ近年の研究の進歩によって、古代人に関する解像度が上がっているのだとしみじみ感じた。
第6章で展示される、アイヌの男性の副葬品とみられるエムシ(太刀)。裏側の装飾が極端に粗雑な点から、戦いで実用するためのものではなく、壁に飾るためのものだと考えられているそうだ。「壁に付けたら裏側は見えないからこんなものでいっか」なんて声が聞こえてきそうだ。
人間の愛すべき隣人、イヌとイエネコ
古代日本人の成り立ちや実態に迫るほか、章の間に挟まるトピックでは「イヌのきた道」「イエネコの歴史」にもスポットが当てられる。写真は、日本でおそらく最古と考えられる縄文時代のイヌの頭骨。イヌという人間と関わりの深い動物の起源を知る手がかりとなるだろう。
個人的に最も楽しみな展示物のひとつが、古墳時代の「動物足跡付須恵器」である。左側に、肉球の跡が付いている。土器の乾燥中に踏まれ、そのまま完成したと思われる逸品だ。この足跡の犯人がタヌキなのかイエネコなのかは議論が続いているそう。ぜひともこの目で確認したい。
井上咲楽、音声ガイドナビゲーターに初挑戦
本展の公式サポーター・音声ガイドナビゲーターを務めるのは、NHK『サイエンスZERO』のMCなど多方面で活躍中の井上咲楽だ。記者発表会には、ピンク×水色の配色と、何重にも折り畳まれたフリルをあしらった“DNAコーデ”で登場。会場をパッと華やかに彩った。
「『サイエンスZERO』のナビゲーターを務めるなかで、研究者の皆さんのお話を聞いたり現場に行かせてもらったりして、どんどん科学に興味を持つようになりました。今回は、初の音声ガイドナビゲーターということで。お話をいただいたときは驚いたんですけれど、この展覧会で最新の研究成果を知ることができるのがとっても楽しみです」(井上)
人に暮らしに、想いを馳せて
井上と監修の篠田館長・藤尾名誉教授とのトークセッションでは、井上から「私の眉毛が、豆苗のようなすごいスピードで伸びるんですけど……。これもDNAを調べると原因が分かったりするんでしょうか?」と、ちょっとしたお悩み相談のようなひとコマも。篠田館長の「僕たちの体の2万2千の遺伝子すべての働きがわかっているわけではなく、DNAは複合的に作用しあうものなので……。眉毛を伸ばすスピードが実際何で決まっているのかは、本当のところはまだわからないんです」との真摯な回答とのアンバランスさに、場内にふふっと笑いが巻き起こった。
さらに料理好きという井上から“古代人のお料理事情”について質問を受けた藤尾名誉教授は、「どんぐりのシチューとか」「調味料は、煮詰めた海水や、干した貝など」と答えると、「わあ、食べてみたくなりますね! 私も今夜はシチューにします(笑)!」と目を輝かせる井上。「縄文人もよく焦がしちゃっていたみたいで、土器の内側にお焦げが残っているんですよ」と教授が続けると、「こうやって古代人の姿を想像するのが、すごく楽しいです」と明るい笑顔を見せた。
「いろんな視点から、古代の人がどんなふうに生活していたのかな? とか、今に至るまでどんなふうに歴史が紡がれてきたのかな? とか、そういうことに思いを馳せながら、一生懸命語りたいと思います。みなさん、ぜひ、目で、耳で、この展覧会を楽しんでください」(井上)
締めくくりのフォトセッションにて、展覧会オリジナルグッズと一緒にカメラマンに応える3名。井上が手にしているのは頭骨のぬいぐるみ(なんと蓄光とか!)。グッズの販売価格など詳細は未定だが、来場の記念やお土産として心くすぐるアイテムが揃いそうで期待である。
特別展『古代DNA―日本人のきた道―』は、2025年3月15日(土)から6月15日(日)まで、国立科学博物館にて開催。これまで想像されていたよりもはるかに複雑であったことが分かってきた、私たち日本人の道のり。最新の研究成果とロマンを、この春はぜひ国立科学博物館で体感してみてほしい。
文・写真(発表会の様子)=小杉 美香、広報画像=オフィシャル提供
https://news.goo.ne.jp/article/spice/entertainment/spice-335250.html