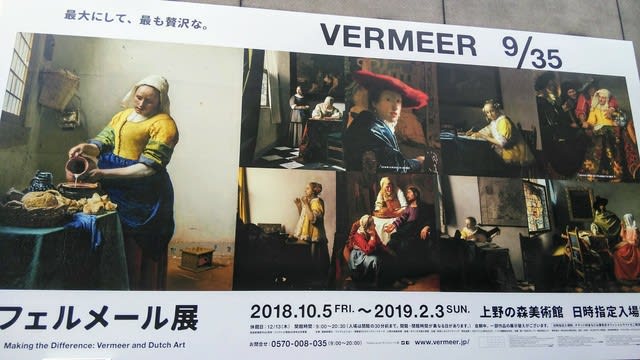今日は紀元祭です。
本来ならば何処かの神社に詣でようか…とも思ったのですが、昨年の紀元祭に寒川神社に参詣していることと、別に用事があったので今年は御遠慮しました。その『用事』というのが、先日私が愛川町在住のシンガソングライターみらいあいこさんにプレゼントした新曲《I love you》の練習をしようということでした。
お昼前に彼女のお宅に伺って軽く打ち合わせを兼ねた軽食を摂ってから、楽譜を突き合わせての練習が始まりました。今回の楽曲のコンセプトは、みらいあいこさんが駆使できるギターコードの範疇で作曲するということでしたので、極力彼女にギターを弾いてもらうことを念頭に置いていました。しかし、今日はとりあえずメロディラインを確認したいということで、私がピアノで伴奏して彼女には歌に専念してもらうことにしました。
自分の詞ではないため何回も歌詞の読み間違いがありましたが、その都度修復しながらどうにか一巡できるようにはなってきました。ただ、極力彼女が弾けるコードを使ったつもりでいたのですが、いくつか難しいコードがあったようなので、それについては午後にギターの名手であるオサギさんが参加された時に練習することにしました。
オサギさんがみえてからは、特にこの週末に出演するライブのセットリストの練習に時間を割かれました。その後、
「さっきのコード教わらなくていいの?」
と聞いてようやく思い出したようで、あれこれと確認をしていました。その時、
「実際にどうなるのかを簡単に録音したい。」
という要望に応えて録音してみることにしたのです。
私が想定しているのはみらいあいこさんがギター弾き語りをして私がヴァイオリンでオブリガートを付けるという形です。しかし、今回は特別にオサギさんにギターを弾いて頂き、私がヴァイオリンを弾いてみらいあいこさんは歌唱に専念する形にしてみました。
一応簡単な録音を済ませて聞いてみて、大体イメージと近いものが出来ました。するとみらいあいこさんが
「じゃあ、これからはこのスタイルでやりましょう。」
と言い出したので、
「このバージョンもいいけど、基本はちゃんと自分でもギター弾けるようにしておいてね。」
と釘を刺しておきました。そうでもしておかないと、ともすると彼女の都合のいいように話が転がってしまうので危険なのです。
プロフェッショナルとして、彼女にはこれからも精進してもらいたいことが沢山あります。その切欠の一つに私の作品が寄与することができるのなら、こんなに嬉しいことはありません。
本来ならば何処かの神社に詣でようか…とも思ったのですが、昨年の紀元祭に寒川神社に参詣していることと、別に用事があったので今年は御遠慮しました。その『用事』というのが、先日私が愛川町在住のシンガソングライターみらいあいこさんにプレゼントした新曲《I love you》の練習をしようということでした。
お昼前に彼女のお宅に伺って軽く打ち合わせを兼ねた軽食を摂ってから、楽譜を突き合わせての練習が始まりました。今回の楽曲のコンセプトは、みらいあいこさんが駆使できるギターコードの範疇で作曲するということでしたので、極力彼女にギターを弾いてもらうことを念頭に置いていました。しかし、今日はとりあえずメロディラインを確認したいということで、私がピアノで伴奏して彼女には歌に専念してもらうことにしました。
自分の詞ではないため何回も歌詞の読み間違いがありましたが、その都度修復しながらどうにか一巡できるようにはなってきました。ただ、極力彼女が弾けるコードを使ったつもりでいたのですが、いくつか難しいコードがあったようなので、それについては午後にギターの名手であるオサギさんが参加された時に練習することにしました。
オサギさんがみえてからは、特にこの週末に出演するライブのセットリストの練習に時間を割かれました。その後、
「さっきのコード教わらなくていいの?」
と聞いてようやく思い出したようで、あれこれと確認をしていました。その時、
「実際にどうなるのかを簡単に録音したい。」
という要望に応えて録音してみることにしたのです。
私が想定しているのはみらいあいこさんがギター弾き語りをして私がヴァイオリンでオブリガートを付けるという形です。しかし、今回は特別にオサギさんにギターを弾いて頂き、私がヴァイオリンを弾いてみらいあいこさんは歌唱に専念する形にしてみました。
一応簡単な録音を済ませて聞いてみて、大体イメージと近いものが出来ました。するとみらいあいこさんが
「じゃあ、これからはこのスタイルでやりましょう。」
と言い出したので、
「このバージョンもいいけど、基本はちゃんと自分でもギター弾けるようにしておいてね。」
と釘を刺しておきました。そうでもしておかないと、ともすると彼女の都合のいいように話が転がってしまうので危険なのです。
プロフェッショナルとして、彼女にはこれからも精進してもらいたいことが沢山あります。その切欠の一つに私の作品が寄与することができるのなら、こんなに嬉しいことはありません。