
古い友人宅に顔出ししたら、
新改築した家にすげーのを
入れてた。
ナンチャッテではなく車買え
るくらいのやつ。
排気も専用設計のスグレモノ。
施工は専門業者さん。


いや、やるね〜。
庭の広いウッドデッキではバー
ベキューもできる。
いつものように日曜庭先外めし
会とかやるんだろな。
引越して間もないけど、綺麗に
整っていて、とても素敵な新宅
でした。
お土産もろた。テンキュー。

うまい!


うまい!










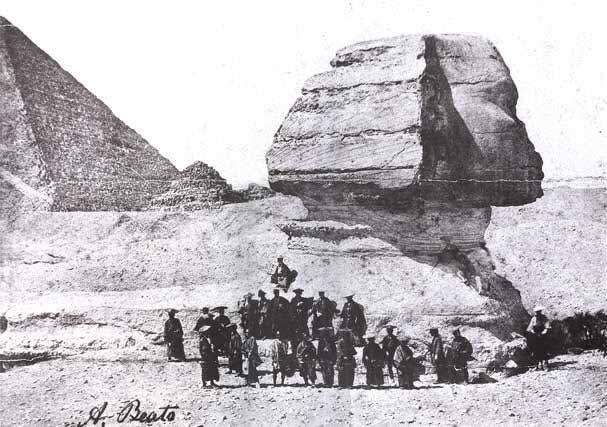

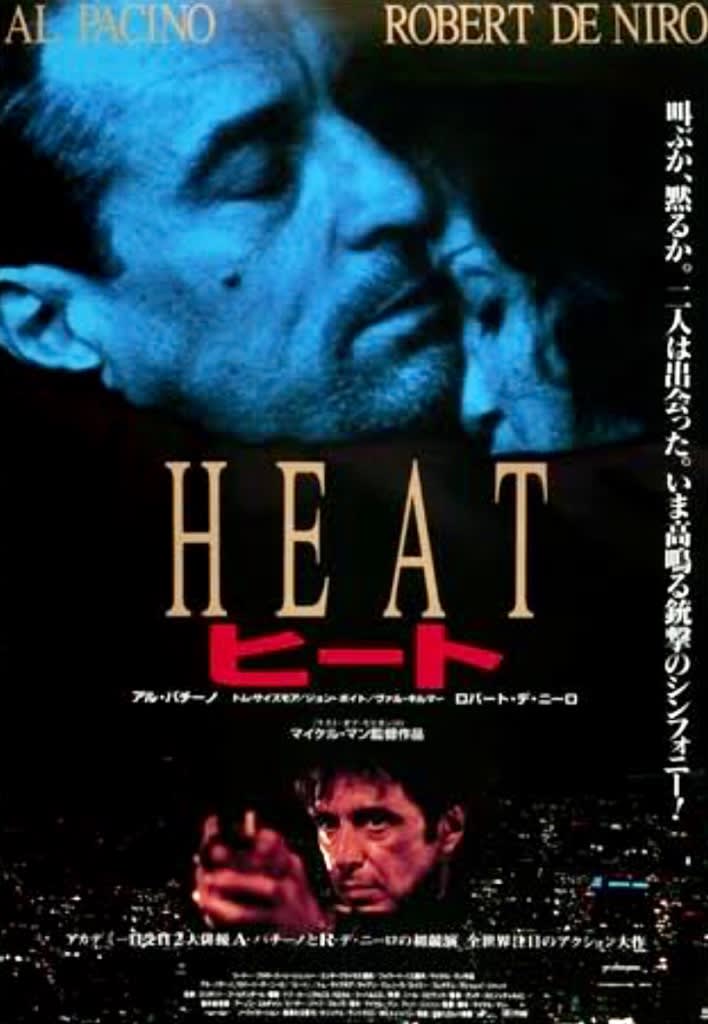
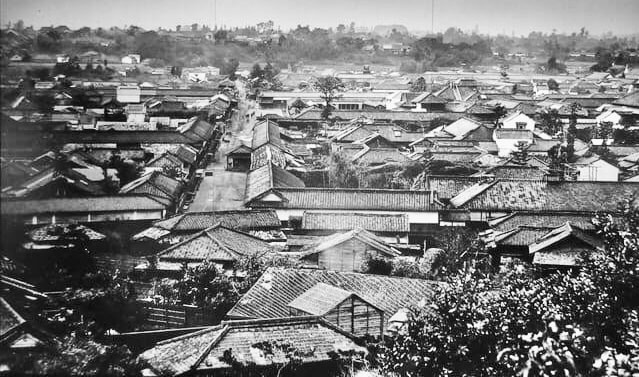










私の自作小太刀木剣。
長さは伸ばした腕の脇の下に当て
て丁度中指の付け根まで。
30数年の経年変化で真っ白だった
白樫がこの色。
非常に使い勝手が良い。
組太刀もこれを使う。
私が持っている木剣の中で一番
使っているのがこれ。ごんぶと。
組太刀での大刀は、やはり自作
木剣を使う。それは赤樫物。
家伝小太刀(大脇差)。江戸初期。
先祖の差料のうちの一つ。
重ね極めて厚い。匂い出来の眠
い作。上研ぎ前にかなり試斬し
た。めちゃくちゃ切れる。
上研ぎは鎌倉の田村慧氏。
下地研ぎが抜群に巧い。
ちなみに、この小型の刀掛けも
自作。