有川浩の本には最近はまっています。
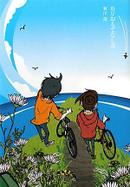
これは県庁だけでなくいわゆる官公署の観光に携わる人の必読書です。
著者自身が高知県出身で、観光特使を依頼されたところからこの小説を構想したみたいですが、そのせいかめちゃめちゃありそうな話になっています。
舞台は高知県のおもてなし課ですが、実際に高知県庁には観光振興部おもてなし課というところはあるそうですし、著者が講演に高知に来たときにそこの次長さんから観光特使を依頼されたそうです。ところが小説にも書いてあるとおり、そこから1月以上音沙汰なし。う~ん、このゆるい感じ、まさにお役所仕事・・
自分たちは営利で仕事をしているわけでなく、基本的にはいいことをしているんだという感覚に予算とか議会の制約という感覚が合わさると時間感覚が世間とは大きくずれてしまう。実際予算がなければできないので思考は年度単位になってしまう。いろいろ要望があっても予算を要求して実際にそれが予算化して契約までこぎつけ実現する頃には状況も変化しているというのはありそうなんですが。
いろいろ民間視点から指摘を受けても案をまとめて予算化するまでには山あり谷あり、いわゆる「県庁ルール」があって、いつの間にか妥協の産物にあっている・・・
それにしても高知の観光を考えると私自身は大学時代に行ったことがあるぐらいで、その時は足摺岬と高知市のはりやま橋に桂浜の竜馬像を見たぐらい。途中、四万十川を見てその清流にびっくりした記憶はあるのですが、まあベタな観光地しか知りませんでした。
高知市でも「日曜市」とか、ゆずで有名だけど山奥の「馬路村」、パラグライダーの「吾川スカイパーク」、さらには言うまでもないけど四万十川や仁淀川の清流、アウトドアやネイチャーツーリングのポイントは山ほどある。高知県民自身は当たり前に思っているので価値を感じていないけど、都会人から見たらうらやむようなところが一杯、それらを有機的につないで「高知県丸ごとレジャーランド」としてアッピールする。いつも普通にあるものが価値があるとはなかなか住んでいる人にはわからないものですが、そこに価値を見出すことが出来ればひとつステップアップしたことが出来ます。テレビの県民ショーではないですがそんなことってどこにでもあるのかとも思ってしまいます。
小説なので2組の男女の恋愛のはらはらどきどきもうまく盛り込まれていますし、民間感覚を持った優秀な若い女の子が臨時職員として都合よく現れたり(実際は正規の職員の若い女性が恋愛抜きのモデルみたいです)しますが、観光というものを如何に売り込んでいくかという視点は、なるほどと思わせ、それだけでこれは観光行政の教科書になるのでは… にしても観光の基本はオリンピック招致のスピーチですっかりメジャーになってしまいましたが「おもてなしマインド」、それをどうやって県民全体に育成していくのか、そして県が取り組んでいくことは、一番は「綺麗なトイレ」、役所的には観光地の偏差値はトイレって表に出しにくいですよね。大切なことはお客様=利用者のしてであり、役所は本来悪いことはしていないという感覚が強いこともあって供給者の視点から物事を見がちです。
高知県のガイドブックについて言えば、行政はありとあらゆるガイドマップを無料であちこちに配っているのですが、なかなか手にとられることもない。対して「るるぶ」は有料にもかかわらず旅行の必需品。内容自体は無料パンフでもかなりのことをフォローしているのにです。無料パンフは置いたら置きっ放しで、客が届きやすい場所にもおいていない。
お客が欲しがるような商品にして、流通まできちんとケアしたら垢抜けられる。情報は見せ方によって商品価値が変わる。たくさんの情報の中からお客の目に留めるためにはキャッチコピーがうまくはまることが必要。キャッチコピーがうまくはまるということは、その商品のセールスポイントを的確に把握していることだから。
ところでそうして知恵を絞った高知県公式ガイドブック、「土佐がまるごとパビリオン」のキャッチはともかく写真が30枚近くごちゃごちゃしている表紙に。県庁内の関係部署の顔を立てていくといろいろ干渉がある。「県庁ルール」に折り合うとこういう結果になる。
それと限られた紙面で資料を作ろうとすると、情報の詰め込みに走りがちになるのですが、空いた隙間がもったいないといってあれこれ詰め込んで緻密にした画面は読む側にとって単なる黒っぽい模様になってしまう。目を通す気にならない。読ませようとするなら実は空間の処理が大切なのです。空白の中にぽんとひとつ置いた言葉は見ただけで脳に届く。百書きこむと読んでくれるかどうかはその人の意欲任せになる。う~ん、そのとおり。どうしてもいろいろ書き込みたくなるんですよね。これはお役所だけのことではないでしょう。
ちなみにこの本に出てくるキャッチコピーは、本当に高知県観光ビジョンの裏表紙にのっています。役所のパンフによく載せたと思いますが、紹介すると
新幹線はない
地下鉄はない
モノレールも走ってない
ジェットコースターがない
スケートリンクがない
ディズニーランドもUSJもない
フードテーマパークもない
Jリーグチームがない
ドーム球場がない
プロ野球公式戦のナイターが出来ない
寄席がない
2千人以上の屋内コンサートができん
中華街はない
地下街もない
温泉街もない
金もない
・・・けんど、光はある。
巻末に著者と高知県おもてなし課の職員の対談も載っていて、実際のガイドブックも紹介されていて、本当にこれは教科書です。
映画にもなっているのですが、映画は見ていないので、今度見てみます。






















 のですが、暖かい日になりました。
のですが、暖かい日になりました。 で行ってそこから歩いて
で行ってそこから歩いて 瑞穂公園テニスコートへ。
瑞穂公園テニスコートへ。 。5人になりました。
。5人になりました。


 して試合に。何故かじゃんけんではいつもタケちゃんマンと森の熊さんが負けるんですよね。
して試合に。何故かじゃんけんではいつもタケちゃんマンと森の熊さんが負けるんですよね。 。隣のコートの影響か力が入りすぎ?
。隣のコートの影響か力が入りすぎ? 。
。 2:2の引き分け。よく盛り返しました。
2:2の引き分け。よく盛り返しました。 で乾杯。
で乾杯。




 。
。 をしているとか。年末年始は千葉へテニス合宿まで行ったとかでオリンピックでも行くつもり?
をしているとか。年末年始は千葉へテニス合宿まで行ったとかでオリンピックでも行くつもり? が出てきて、休んでいると北風がに吹かれ結構寒さが身に沁みます。それでもビール
が出てきて、休んでいると北風がに吹かれ結構寒さが身に沁みます。それでもビール をちびちび飲んで、この日は350缶で5本。
をちびちび飲んで、この日は350缶で5本。 落とし、2:2の引き分け。
落とし、2:2の引き分け。
 4と熱燗
4と熱燗 2合(これは当然タケちゃんマンです)とノンアルコールビール
2合(これは当然タケちゃんマンです)とノンアルコールビール



 なります。
なります。 。
。 。もう少し気を引き締めてちゃんとしたテニスをできるようにしないといけないと少し(大いにか)反省でした。
。もう少し気を引き締めてちゃんとしたテニスをできるようにしないといけないと少し(大いにか)反省でした。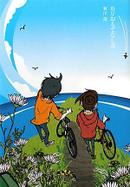



 。
。 に。
に。
 を連れたワッキー夫妻が登場。お久しぶりです。
を連れたワッキー夫妻が登場。お久しぶりです。






