第153回の直木賞受賞作です。

私の記憶では直木賞受賞した時の選評では、文句なしでの受賞だったはず。
作者の東山彰良は台湾生まれで9歳の時に日本に移ってきていますが、この作品では今中日新聞の夕刊に連載している小説と同じく台湾を舞台に台湾人を主人公にしています。
強引に要約すれば、1975年に17歳だった少年が祖父の殺人事件の謎を追いつつ青春を駆け抜けていく1988年までの物語、と言うと身も蓋もないのだが、テンポのいい疾走感は読みだすとやめられない止まらない。ミステリーで味付けした台湾版「青春の門」というところか。
しかし、舞台が台湾だけに人名がなかなかすっと頭に入ってこない。ルビの打ってある中国式発音では全く受け入れられない。背景にある台湾の政治状況とか社会状況も新聞やテレビで知った程度の上っ面の知識しかないので、イマイチ臨場感が出てこない。国共内戦の状況とか本省人と外省人の分断と差別の構造と支配被支配の関係とか、蒋介石の時代から戒厳令が敷かれていて徴兵制のよる兵役があったとか、暴力団がはびこり猥雑な夜市の喧騒とか、書物から読んだ知識で多少知っているつもりでも肌感覚では理解できない。
主人公は1975年に17歳なので私とは4歳の違いなのだが、感覚的には日本の昭和3~40年代の青春なのだろうか。今となっては忘れられてしまったのだが、高度成長期の日本のはち切れるばかりの猥雑なエネルギーと混沌と何事も何とかなっていくといういい加減さと希望が、台湾に場を移してこの小説の背景に見て取れるように思うのですが、私の勘違い?
ミステリーの鍵になるのは日中戦争から国共内戦、そして台湾への敗退(台湾本省人にとっては迷惑な侵略)の過程で中国人同士が争い殺し殺されと言う凄惨な事態に巻き込まれていったことなのですが、そのあたりの知識は最早現代史の一部でほとんど学んできていなかったので、原因の一端を担っている日本人として勉強不足ですというしかありません。
台湾が舞台なので細切れに読んでいると名前が分からなくなって戻って頭を整理しないといけないので暑気払いにエアコンを利かして一気に読んでください。
ついでに読んでいたのが新書本で日本史に関する2冊。

「奪われた三種の神器」は南北朝から室町幕府時代にかけて三種の神器が皇位継承の正当性の証として結構奪い奪われと言うことを繰り返してきたことを明らかにしています。安徳天皇とともに神剣は海に沈んだのですが、草薙剣はそもそも熱田神宮に鎮座しているので天皇家がもっているのは形代。それならばそんなにこだわる必要もない気がしますが、それでも由緒由来がないと神器とはならないのでしょうか。南北朝から室町にかけては皇族の系統の争いもあって権謀術策が渦巻き、何でもありの時代だったみたいです。
「古代史この7つの真実はなぜ塗り替えられたのか」は歴史作家の関裕二が大胆に古代史のなぞ解きをする。古代史は同時代の文献資料がなくて今現在発掘された考古学知見(今後まだまだ新しい発見があるかも?)とそこからの推理によるので歴史作家の推理もあながち間違いと言い切れない面があるし、それなりに面白い。神の名が付く皇族は神武天皇、崇神天皇、神功皇后、応神天皇と4人いるのだが、神功皇后は邪馬台国の卑弥呼の後を継いだ台与で、神武、崇神、応仁の3人の天皇は大和建国当時の歴史を3人に分けているものとか。8世紀に成立した日本書紀は勝者の記録であり、当時の政権を握っていたものの都合のいいように編集されているはず。この本では日本書紀は藤原氏が自らの正当性を記したものとし、都合の悪い事実は巧妙に消されている。作者の推理によれば、中臣鎌足は百済の王子豊璋であり、その正当性の邪魔になる蘇我氏を悪役にし、そのバックボーンとなっていた尾張氏、出雲,越の果たした役割を不当に消し去っている。山背大兄王の滅亡事件は蘇我入鹿を大悪人にするための虚構であり、そのため聖徳太子を必要以上に持ちあげている。通説から見れば荒唐無稽としか言いようがなく突っ込みどころはいろいろあって、古代史学者の見解を聞きたいところですが、梅原猛がほとんど学会から無視されたように、まともに取り上げられることはないでしょうね。猛暑で外出もままならぬ時はこういう頭の体操も刺激になります。関裕二、この本の後にもいろいろ本を出しているのでfollowしてみようと思います。

私の記憶では直木賞受賞した時の選評では、文句なしでの受賞だったはず。
作者の東山彰良は台湾生まれで9歳の時に日本に移ってきていますが、この作品では今中日新聞の夕刊に連載している小説と同じく台湾を舞台に台湾人を主人公にしています。
強引に要約すれば、1975年に17歳だった少年が祖父の殺人事件の謎を追いつつ青春を駆け抜けていく1988年までの物語、と言うと身も蓋もないのだが、テンポのいい疾走感は読みだすとやめられない止まらない。ミステリーで味付けした台湾版「青春の門」というところか。
しかし、舞台が台湾だけに人名がなかなかすっと頭に入ってこない。ルビの打ってある中国式発音では全く受け入れられない。背景にある台湾の政治状況とか社会状況も新聞やテレビで知った程度の上っ面の知識しかないので、イマイチ臨場感が出てこない。国共内戦の状況とか本省人と外省人の分断と差別の構造と支配被支配の関係とか、蒋介石の時代から戒厳令が敷かれていて徴兵制のよる兵役があったとか、暴力団がはびこり猥雑な夜市の喧騒とか、書物から読んだ知識で多少知っているつもりでも肌感覚では理解できない。
主人公は1975年に17歳なので私とは4歳の違いなのだが、感覚的には日本の昭和3~40年代の青春なのだろうか。今となっては忘れられてしまったのだが、高度成長期の日本のはち切れるばかりの猥雑なエネルギーと混沌と何事も何とかなっていくといういい加減さと希望が、台湾に場を移してこの小説の背景に見て取れるように思うのですが、私の勘違い?
ミステリーの鍵になるのは日中戦争から国共内戦、そして台湾への敗退(台湾本省人にとっては迷惑な侵略)の過程で中国人同士が争い殺し殺されと言う凄惨な事態に巻き込まれていったことなのですが、そのあたりの知識は最早現代史の一部でほとんど学んできていなかったので、原因の一端を担っている日本人として勉強不足ですというしかありません。
台湾が舞台なので細切れに読んでいると名前が分からなくなって戻って頭を整理しないといけないので暑気払いにエアコンを利かして一気に読んでください。
ついでに読んでいたのが新書本で日本史に関する2冊。

「奪われた三種の神器」は南北朝から室町幕府時代にかけて三種の神器が皇位継承の正当性の証として結構奪い奪われと言うことを繰り返してきたことを明らかにしています。安徳天皇とともに神剣は海に沈んだのですが、草薙剣はそもそも熱田神宮に鎮座しているので天皇家がもっているのは形代。それならばそんなにこだわる必要もない気がしますが、それでも由緒由来がないと神器とはならないのでしょうか。南北朝から室町にかけては皇族の系統の争いもあって権謀術策が渦巻き、何でもありの時代だったみたいです。
「古代史この7つの真実はなぜ塗り替えられたのか」は歴史作家の関裕二が大胆に古代史のなぞ解きをする。古代史は同時代の文献資料がなくて今現在発掘された考古学知見(今後まだまだ新しい発見があるかも?)とそこからの推理によるので歴史作家の推理もあながち間違いと言い切れない面があるし、それなりに面白い。神の名が付く皇族は神武天皇、崇神天皇、神功皇后、応神天皇と4人いるのだが、神功皇后は邪馬台国の卑弥呼の後を継いだ台与で、神武、崇神、応仁の3人の天皇は大和建国当時の歴史を3人に分けているものとか。8世紀に成立した日本書紀は勝者の記録であり、当時の政権を握っていたものの都合のいいように編集されているはず。この本では日本書紀は藤原氏が自らの正当性を記したものとし、都合の悪い事実は巧妙に消されている。作者の推理によれば、中臣鎌足は百済の王子豊璋であり、その正当性の邪魔になる蘇我氏を悪役にし、そのバックボーンとなっていた尾張氏、出雲,越の果たした役割を不当に消し去っている。山背大兄王の滅亡事件は蘇我入鹿を大悪人にするための虚構であり、そのため聖徳太子を必要以上に持ちあげている。通説から見れば荒唐無稽としか言いようがなく突っ込みどころはいろいろあって、古代史学者の見解を聞きたいところですが、梅原猛がほとんど学会から無視されたように、まともに取り上げられることはないでしょうね。猛暑で外出もままならぬ時はこういう頭の体操も刺激になります。関裕二、この本の後にもいろいろ本を出しているのでfollowしてみようと思います。










 で来たというはげ親父に頼んでタケちゃんマンと私は鶴舞まで送ってもらうことに。
で来たというはげ親父に頼んでタケちゃんマンと私は鶴舞まで送ってもらうことに。









 です。
です。 があるかもとか。
があるかもとか。 へ。バスは2分遅れで来たのですが、降りるまでの乗客は私を含めて8人。過密ではなく、マスクを外していてもいいくらい。
へ。バスは2分遅れで来たのですが、降りるまでの乗客は私を含めて8人。過密ではなく、マスクを外していてもいいくらい。 ます。
ます。
 。なんでも時間ができたので車で駆けつけてきたとか。君はえらい!
。なんでも時間ができたので車で駆けつけてきたとか。君はえらい! 。ストロークとボレーに分かれた5人での乱打
。ストロークとボレーに分かれた5人での乱打 にします。
にします。

 して試合にしましょう。
して試合にしましょう。

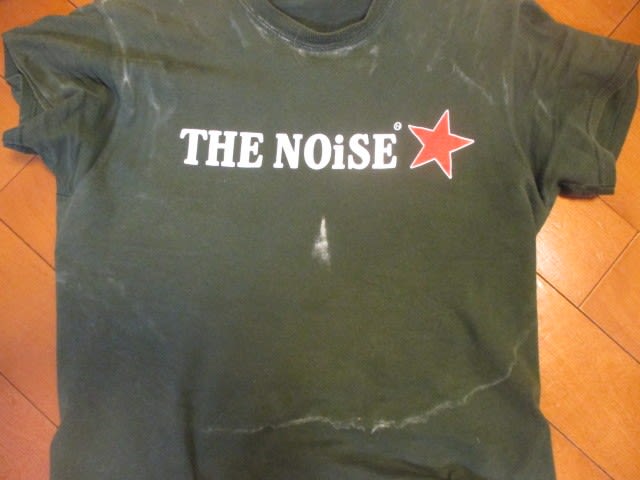





 。
。



 。結局一人相撲の自滅で勝てるはずの試合を2:2の引き分けにしてしまいました。
。結局一人相撲の自滅で勝てるはずの試合を2:2の引き分けにしてしまいました。











 をやっています。
をやっています。
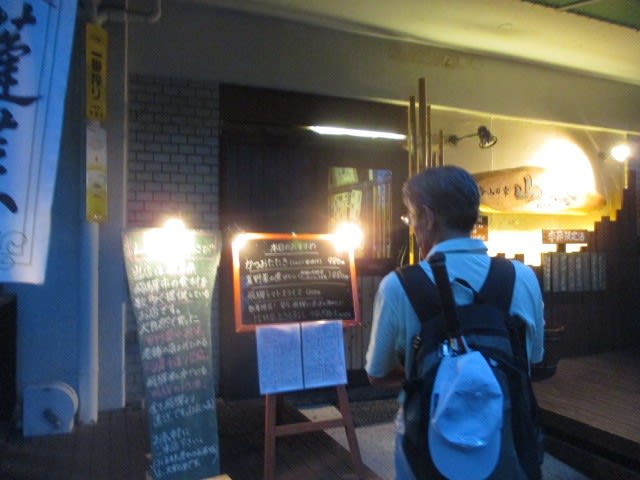
 。
。








 が続きます。
が続きます。

 をかいたので、1059さんと二人でビール
をかいたので、1059さんと二人でビール を飲みに行きましょう。
を飲みに行きましょう。





