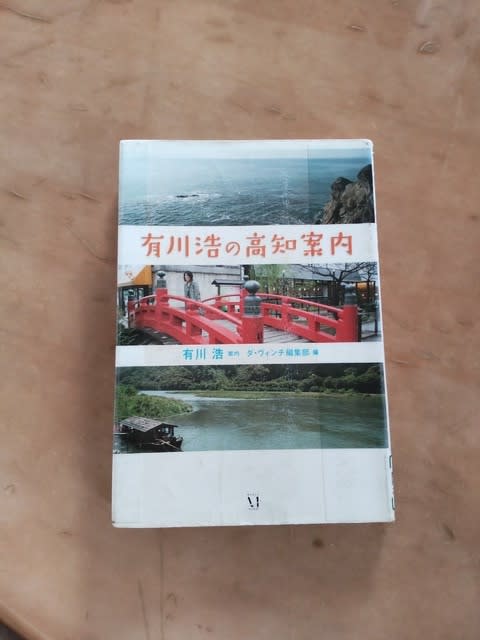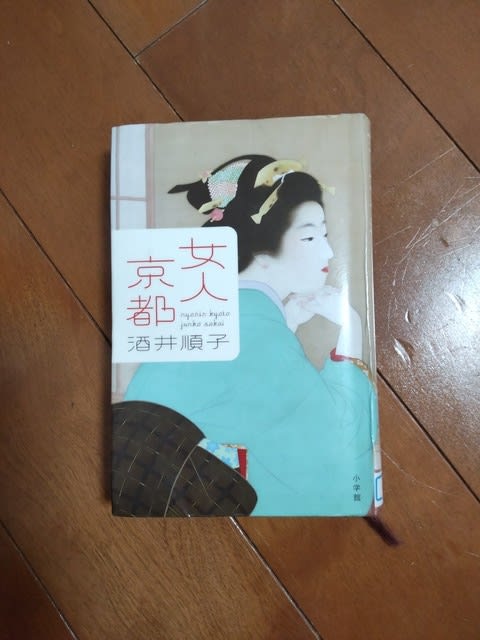以前は国税庁から毎年長者番付というのが発表され、大企業のオーナーだったり土地成金などが名を連ねていた。
ところが2005年は約100億稼いだ一介のサラリーマン投資運用者(肩書としてはタワー投資顧問運用部長)が日本一となる。それがこの本の著者の清原達郎さん。因みに長者番付はこの年を最後に発表されなくなったので、余計印象が残っている。
その清原さんは咽頭癌により声帯を失い、ヘッジファンドを運用するためには膨大なエネルギーとどん欲さが必要なのですが、もはやその限界を感じて2023年にファンドマネージャーを引退してしまった。
この本は清原さんが自身の半生と投資のやり方を成功例だけでなく失敗体験も含めてこんなに書いていいのかと思うほど書いたものです。かなり高度な投資手法も開陳されていますが、ほとんど投資経験もない素人でちょっと運用の世界をのぞいてみようかという人にも有意義な箴言が沢山出てきて、これから株式投資を始めようと言う人にも最適な指南書になっています。
因みにこれから始めようと言う個人投資家は、余裕資金の範囲内で信用取引に手を出さず現物投資のみ、半分はTOPIXか日経平均のインデックスなりETFに投資し、半分はスタンダード市場の小型成長株を長く持つこと。マザーズ市場の高PER株は何をやっているか分からないので手を出さない。金融機関の手数料には注意して頻繁に売買しない。情報収集にお金をかける必要はなくて、四季報だけで十分、そんな金があるのなら投資に回しなさい。実際清原さんもあまりお金をかけていないみたいです。

清原さんは東京大学卒業後、最初野村証券に入社していますが、当時の証券会社というのはお客を儲けさせようと言うよりは頻繁な売買を繰り返させて手数料を稼ぐと言う方針。今の野村證券は違うと言いつつ当時のあくどい手口も遠慮なく書いてあります。顧客に損をさせても会社の利益を得ようとするそんな会社の在り様に強烈な違和感を感じるのですが、スタンフォード大学に留学後、野村証券のニューヨーク支店に赴任。その後ゴールドマン・サックスの日本支店に転職します。そこからタワー投資顧問でヘッジファンドを運用するようになります。
清原さんの運用方針は、日本株の割安成長小型株を見つけてロングで投資していくこと。何が割安成長株価をスクリーニングするにはいろいろな指標を吟味する必要がありますが、そこらへんは難しい話もあるので取り合えずスルーしても大丈夫。もちろん勉強したい人には惜しみなく手法を開示し簡明に手ほどきしてあります。大型株はいろいろなアナリストが企業分析しているのですけど小型株まではなかなか手が回らない。結果として割安のまま放置されている企業が沢山ある。
では成長性をどうやって見極めるのか。列挙してあることを書き出すと
1 経営者がその企業を成長させる強い意志を持っているか
2 社長と目標を共有する優秀な部下がいるか
3 同じ業界内の競合に押しつぶされないか
4 その会社の強みは成長とともににさらに強くなっていくか
5 成長によって将来のマーケットを先食いし、潜在的マーケットを縮小させていないか
6 経営者の言動が一致しているかどうか
この中で圧倒的に大事なのが1だそうで、清原さんは投資を決める時には必ず社長と面談していたとか。そう思うと名証株式セミナーで社長が出席して話す会社は見込みありか。実際に会って酷かった会社を実名で出しています。いい会社ではニトリの社長は面談時に証券会社や投資家の接待は絶対受けないと言い何とか千円のスパゲッティを食べたとか。ゼンショーの小川社長はユニークで感心していましたが余り売り物の株がなく投資できなかったとか。大企業と違い中小型株の企業は社長の個性とか良しあしが大きく影響すると言うことでしょう。
基本的には中小型株のロングで運用していたのですが、明らかに割安と思われる時には大型株のショート(空売り)もやっていたのですが、ITバブル崩壊とかライブドアショック、リーマンショックとかには大きな損失を出しています。特にリーマンショック時にはファンドの危機に陥り自己資金をほぼ全財産(約30億‼)投入しなんとかしのいだそうです。
それやこれやで自分の投資の成功例、失敗例を第6章、第7章に具体的な企業名を挙げて出しています。オリンパス、プレサンスコーポレーション、ユニクロ、ファナック、イオン、ブラザーなどなどよく知っている企業も取り上げられていて、投資するつもりはなくても企業分析は違う観点からの視点で面白い。
最後にこれからの日本株市場の見通しを書いてありますけど、破滅的リスクもあるけれど日本株ショーテッジ(供給が絞られ買い手の需要を満たせない状態)時代が到来するとある意味楽観的です。
投資に興味がなくても清原さんの生きざまは読みごたえがあり経済のことを知ろうとする人にはお勧め本です。