先日、鈴木邦男のブログを読んでいたら、トップがこの本の紹介。鈴木邦男と三遊亭円丈というのは結び付くイメージがわかないのだが、二人とも快楽亭ブラックとは仲がいいみたいなので、意識はしていたのか…
三遊亭円丈というのは名古屋市瑞穂区は雁道の出身で、実家は商店街を上がった3丁目の大角写真館です。

同級生なども多くて、その縁で雁道七夕祭りに来たこともあり、テレビのリポーターで商店街を歩いたりしてうちの父親と一緒に写った写真もある。
そういう訳で親しみもあり、ひそかに応援もしているのですが、あまりテレビにも出ないし、正直に言えば円丈の新作落語はそれほど好きではない。
でもこの本は、落語家自身があまたの落語家の評価を実名でしているという稀有な本。落語マニアというのは世にたくさんいてそれこそ何の仕事をしているかわからないけど毎日のように寄席に通うなどして聞いている人もいる。そういう人が落語評論家などと称して数多の本を書いているのだが、彼らは当然ながら落語はできない。落語を生業としている人の書いた評論はまた違った観点があるのだが、業界人だからこそ狭い世界ではっきり点をつける通信簿を書いていいのかどうか、総スカンされる恐れも多々あり、結構勇気ある行為ですね。
ちなみに落語家は一門の人とか一緒に落語会をやる人以外の人の落語をあまり聞く機会はなくて、円丈自身はこの本を書くのに結構CDとかユーチューブを見聞きして改めて確認しています。
まあ、知っている人も知らない人もいて、円丈自身がもう70歳(この本を書くときは68歳)なので、どうしても世代的に上になりますけどね。
ところでこの本で円丈が絶対にかなわないと書かれた落語家は、圓生と志ん朝。圓生は円丈の師匠なので、そういうことなのでしょうが、やっぱり志ん朝か。志ん生の息子で36人抜きで真打昇進、まさに落語界のサラブレッドです。その芸もすごくて30代前半の志ん朝の高座を見たら客席全体が志ん朝ワールドになっていて、円丈自身が悔しいけど後にも先にも見たことがないと書いている。気配りのできるやさしかった志ん朝ですが、心の中には「志ん生の息子」「36人抜き真打昇進」の十字架を背負っていたのだろう。あんなにけいこする、そしてそれを人に見せないようにする落語家はいなかったとか。本当はもっと自由に新作落語でも語りたい時もあったかもしれないけれどサラブレッドには許されなかったんだよね。
関西ではなんといっても枝雀。でもあのオーバーアクションは古今亭圓菊をもとにしたとか。もっとも上方だからああいうオーバーアクションやって、なおかつそれをブラッシュアップして爆笑落語にできたんでしょうけど。東京落語から見ると枝雀の落語は受け入れられない。その枝雀も無類のけいこ好きで、頭もよくて記憶力抜群。ふつうに古典落語をやっても米朝直伝でうまい。円丈は例えるならスーパー志ん朝とさえ言っている。だけどうつを患てしまうことでわかるように枝雀も心に闇を抱えていたんですよね。本当に惜しい…
談志についても述べているのですが、談志はやっぱり天才なんです。人たらしで、会うとすっかり魅せられてしまう。宗教家とすると分かりやすいとか。強烈な魅力があるんだろう。弟子の立川談春が書いた「赤めだか」などは談春の見た談志論だし、談春はいつも談志という天才落語家がいた中で師匠のまねでないオリジナルな自分の落語はどうすればいいのか考えて古典落語のいまの境地に行きついている。でも「芸は砂の山」(これは師匠の圓生の言葉)でどんなに天才でもけいこしないで怠ければズルズル滑り落ちてしまう。談志と志ん朝を分けるのはそこなんかな。
談志の生き方やり方については辛口ですが家元立川流が真打昇進の基準をきちんとしたことについては評価しています。
新作落語については文枝の評価が高いですね。一緒にやってもウケが違うと正直です。まあ、総じて新作落語については点が甘いかも。
林家三平についても高い評価。でもあの芸はライブで見ないとわからない芸。CDではよさはわからない。となると同時代で見た人しかわからないだろうな~私はかろうじてテレビで見ていますが、落語というより漫談だったのですが、小学生にも面白かった記憶です。同時代を体験している人にはわかるのですが、CDとかビデオでしか見ていない人にはわからない。観客のドカンドカンという反応も含めての客席と一体になった面白さなんだよね。
まあ、こうはっきり書いていいのかということも含めていろいろな人が出てきますが、人生ここまでくると何を書いても怖くないのか。それだから面白く読むことができたんですけど…落語でもどこかに気づかないほどの毒があるとそれが薬味になるんです。まあ、この本は毒がすぐわかるほどいっぱいですけど。
円丈自身についていうと、この本に自分で書いているのですが、新作落語を作る創作力、構成力、観察力があり、芸の力もそこそこあるのですが、コセコセ仕事をするの嫌いな心の貴族。芸が好きでなくて噺のけいこも嫌い。人づきあいが下手でヨイショもできない。典型的な仕事が来ないタイプ。それなら落語家なんかしないで脚本家かなんかになればよかったかも。お笑い芸人でも「笑い」についてよく考えていて、芸人に対する批評も鋭いのですが、自分の芸は笑いがイマイチという人いますよね。
三遊亭円丈というのは名古屋市瑞穂区は雁道の出身で、実家は商店街を上がった3丁目の大角写真館です。

同級生なども多くて、その縁で雁道七夕祭りに来たこともあり、テレビのリポーターで商店街を歩いたりしてうちの父親と一緒に写った写真もある。
そういう訳で親しみもあり、ひそかに応援もしているのですが、あまりテレビにも出ないし、正直に言えば円丈の新作落語はそれほど好きではない。
でもこの本は、落語家自身があまたの落語家の評価を実名でしているという稀有な本。落語マニアというのは世にたくさんいてそれこそ何の仕事をしているかわからないけど毎日のように寄席に通うなどして聞いている人もいる。そういう人が落語評論家などと称して数多の本を書いているのだが、彼らは当然ながら落語はできない。落語を生業としている人の書いた評論はまた違った観点があるのだが、業界人だからこそ狭い世界ではっきり点をつける通信簿を書いていいのかどうか、総スカンされる恐れも多々あり、結構勇気ある行為ですね。
ちなみに落語家は一門の人とか一緒に落語会をやる人以外の人の落語をあまり聞く機会はなくて、円丈自身はこの本を書くのに結構CDとかユーチューブを見聞きして改めて確認しています。
まあ、知っている人も知らない人もいて、円丈自身がもう70歳(この本を書くときは68歳)なので、どうしても世代的に上になりますけどね。
ところでこの本で円丈が絶対にかなわないと書かれた落語家は、圓生と志ん朝。圓生は円丈の師匠なので、そういうことなのでしょうが、やっぱり志ん朝か。志ん生の息子で36人抜きで真打昇進、まさに落語界のサラブレッドです。その芸もすごくて30代前半の志ん朝の高座を見たら客席全体が志ん朝ワールドになっていて、円丈自身が悔しいけど後にも先にも見たことがないと書いている。気配りのできるやさしかった志ん朝ですが、心の中には「志ん生の息子」「36人抜き真打昇進」の十字架を背負っていたのだろう。あんなにけいこする、そしてそれを人に見せないようにする落語家はいなかったとか。本当はもっと自由に新作落語でも語りたい時もあったかもしれないけれどサラブレッドには許されなかったんだよね。
関西ではなんといっても枝雀。でもあのオーバーアクションは古今亭圓菊をもとにしたとか。もっとも上方だからああいうオーバーアクションやって、なおかつそれをブラッシュアップして爆笑落語にできたんでしょうけど。東京落語から見ると枝雀の落語は受け入れられない。その枝雀も無類のけいこ好きで、頭もよくて記憶力抜群。ふつうに古典落語をやっても米朝直伝でうまい。円丈は例えるならスーパー志ん朝とさえ言っている。だけどうつを患てしまうことでわかるように枝雀も心に闇を抱えていたんですよね。本当に惜しい…
談志についても述べているのですが、談志はやっぱり天才なんです。人たらしで、会うとすっかり魅せられてしまう。宗教家とすると分かりやすいとか。強烈な魅力があるんだろう。弟子の立川談春が書いた「赤めだか」などは談春の見た談志論だし、談春はいつも談志という天才落語家がいた中で師匠のまねでないオリジナルな自分の落語はどうすればいいのか考えて古典落語のいまの境地に行きついている。でも「芸は砂の山」(これは師匠の圓生の言葉)でどんなに天才でもけいこしないで怠ければズルズル滑り落ちてしまう。談志と志ん朝を分けるのはそこなんかな。
談志の生き方やり方については辛口ですが家元立川流が真打昇進の基準をきちんとしたことについては評価しています。
新作落語については文枝の評価が高いですね。一緒にやってもウケが違うと正直です。まあ、総じて新作落語については点が甘いかも。
林家三平についても高い評価。でもあの芸はライブで見ないとわからない芸。CDではよさはわからない。となると同時代で見た人しかわからないだろうな~私はかろうじてテレビで見ていますが、落語というより漫談だったのですが、小学生にも面白かった記憶です。同時代を体験している人にはわかるのですが、CDとかビデオでしか見ていない人にはわからない。観客のドカンドカンという反応も含めての客席と一体になった面白さなんだよね。
まあ、こうはっきり書いていいのかということも含めていろいろな人が出てきますが、人生ここまでくると何を書いても怖くないのか。それだから面白く読むことができたんですけど…落語でもどこかに気づかないほどの毒があるとそれが薬味になるんです。まあ、この本は毒がすぐわかるほどいっぱいですけど。
円丈自身についていうと、この本に自分で書いているのですが、新作落語を作る創作力、構成力、観察力があり、芸の力もそこそこあるのですが、コセコセ仕事をするの嫌いな心の貴族。芸が好きでなくて噺のけいこも嫌い。人づきあいが下手でヨイショもできない。典型的な仕事が来ないタイプ。それなら落語家なんかしないで脚本家かなんかになればよかったかも。お笑い芸人でも「笑い」についてよく考えていて、芸人に対する批評も鋭いのですが、自分の芸は笑いがイマイチという人いますよね。










 。
。 を強行したのでした。
を強行したのでした。 降ってきました。雲の動きを見てみると7時ごろまでは雲は切れそうもない。
降ってきました。雲の動きを見てみると7時ごろまでは雲は切れそうもない。 。どうやらヤッターマンは来週都合が悪いみたいで、そういえば先週も来れなかったので、今から行くとのこと。それならば行くか…テニスの支度をするのですが雨は一向に降りやまない。
。どうやらヤッターマンは来週都合が悪いみたいで、そういえば先週も来れなかったので、今から行くとのこと。それならば行くか…テニスの支度をするのですが雨は一向に降りやまない。




 を飲みつつ寛いでいるとはげ親父からメール
を飲みつつ寛いでいるとはげ親父からメール 金山へ。ちょうど来たところの10時6分の快速
金山へ。ちょうど来たところの10時6分の快速 に乗って鶴舞公園テニスコートへ。
に乗って鶴舞公園テニスコートへ。 で来ました。
で来ました。 。
。 。あとで確認したらちゃんとパソコンのメールに行くと返事がありました。
。あとで確認したらちゃんとパソコンのメールに行くと返事がありました。


 して試合に。
して試合に。 …
…

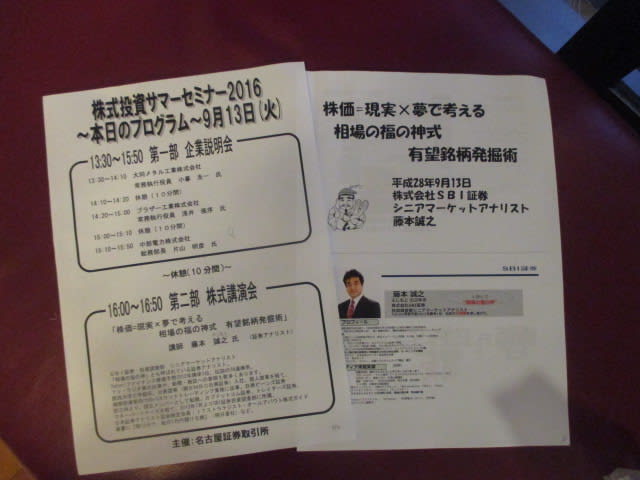





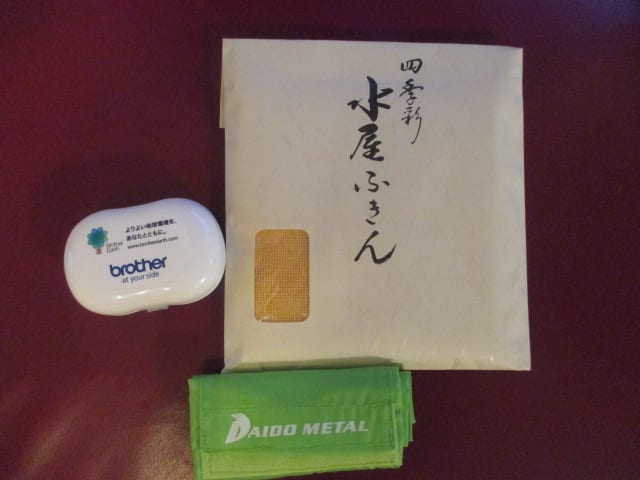
 を飲んで盛り上がっている。
を飲んで盛り上がっている。



 盛り上がって長尻になってきたのですが、タケちゃんマンは帰りのバスの時間があるので3千円を置いておいて途中退場。
盛り上がって長尻になってきたのですが、タケちゃんマンは帰りのバスの時間があるので3千円を置いておいて途中退場。


 を炊きます。
を炊きます。










