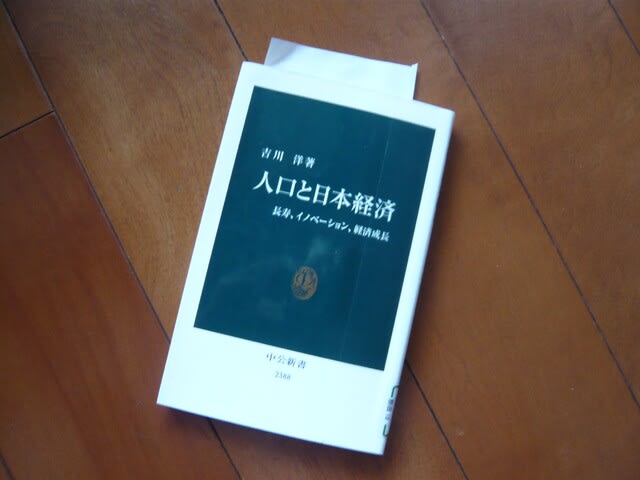今月末は総選挙の投票日。
勝ちすぎていた安倍自民党が、菅を経て岸田になってどうなるのか。
前回並みの自民党が絶対安定多数とはいかないけれど、どうひっくり返っても政権交代とはなりそうもない。
まあ、そんな季節ものとして読んでみました。
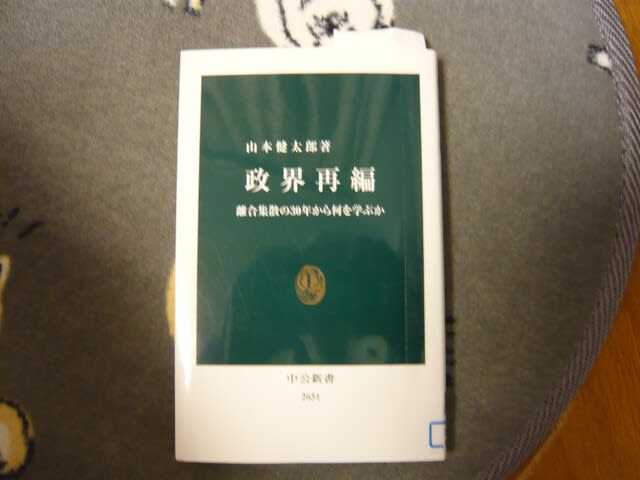
この本で改めて55年体制崩壊後の政党の有為転変を見てみるとそんな政党があったのだと感慨深い。ちゃんと変わらず存在感を保っているのは自民党と共産党だけ。
社会党は自壊してしまい、継承者の社会民主党はこの選挙で議席を獲得できるかどうかの瀬戸際でもはや絶滅危惧種。昔の名古屋人にはおなじみの春日一宏率いる民社党はもはや影も形もない。固い支持層がある公明党さえも新進党に参加したりとフラフラしていた。


新自由クラブ、新生党、新党さきがけ、日本新党、新進党ぐらいはまだ記憶があるけれど、黎明クラブ、新党平和、自由党、改革クラブ、新党友愛、太陽党、フロムファイブ、民政党とか言われるとどういう経緯でメンバーは誰かなのかはまるで記憶にない。
2010年以降でも、新党大地、みどりの風、日本未来の党、次世代の党、結の党、日本のこころを大切にする党、生活の党などなどどれくらい覚えているのか。減税日本などと言うのもありました。どれだけ記憶に残っているでしょうか。
自民党政権が続く中、激しい派閥間の争いが疑似政権交代をもたらしていたのだが、中選挙区での自民党の派閥争いが金権選挙になったことを改革するために政治改革が大きな争点となった。結果、今の小選挙区比例代表制となったのだが、小選挙区で勝つためには小異を捨てて大きくまとまらないと勝てないことに。
主義主張、理念、政策にこだわるとなかなかまとまらないのですが、少数政党はその存在意義をアピールするためにはなかなかこだわりを捨てることはできない。野党の場合は生き残るためには、どうしてもくっついたり離れたりするしかない…
それにしてもこの変遷を見てみると絶えず中心に小沢一郎がいる。もし彼が首相になっていたらどういう政治を行っていたのだろうか。ある時には反自民で主張の違いの多い政党をまとめ上げ政権交代を成し遂げ、ある時には自民党と連立を組み、政策が実現しないと連立を離脱。民主党をまとめ上げ選挙で圧勝し政権交代を実現するのだが、政治手法、意見の違いの中での激しい政争の当事者となって内部は迷走。政権を失うとともに民主党は自壊していった。今は存在感も薄れているのだが、今回の選挙協力ではまだまだ陰で動いていたのだろうか。彼がイマイチこの日本をどうしていきたいのか、どういう政策をしたいのかがよく分からない。
政権を担っている内は求心力が働くので、自民党を離脱するものはおらず、逆に権力にすり寄るものをどんどん引き付けていく。自分の主張するところを何分かの一でも実現するためには、多少のことは目をつぶるなりして政権与党にいるしかないのだから当然なのか。
この本の最後に今の小選挙区制度の下で立憲民主党が政権を担う対象とみなされるには、左寄りのリベラル政党と言うイメージを発展的に脱却し、中道の有権者にどうアプローチしていくのかが問われる。第三極を抑え込みつつ、中道を自ら引き寄せるのが政権交代の必要条件と言うのだが、共産党・社民党との選挙協力のように、今の立憲民主党は左寄りのリベラル政党の方向に純化しつつあるようで、政権交代までたどり着くのは難しい。
でも、安倍政治の極右路線(主張はヨーロッパの極右政党と同類)と主張を共にする身内だけを大事にする政治の私物化と、平気でうそをつく姿勢は気持ちが悪いのですが、どうなることでしょうか。なんとなく岸から池田、佐藤、田中、三木、福田、大平と熾烈な派閥争いの中での疑似政権交代があらまほしく思えてしまいます。
勝ちすぎていた安倍自民党が、菅を経て岸田になってどうなるのか。
前回並みの自民党が絶対安定多数とはいかないけれど、どうひっくり返っても政権交代とはなりそうもない。
まあ、そんな季節ものとして読んでみました。
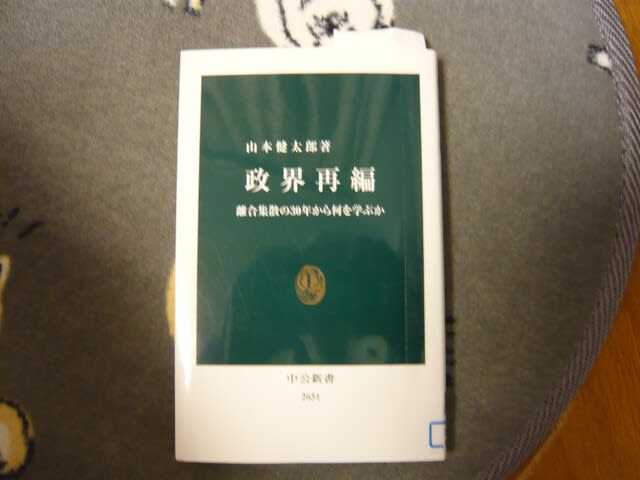
この本で改めて55年体制崩壊後の政党の有為転変を見てみるとそんな政党があったのだと感慨深い。ちゃんと変わらず存在感を保っているのは自民党と共産党だけ。
社会党は自壊してしまい、継承者の社会民主党はこの選挙で議席を獲得できるかどうかの瀬戸際でもはや絶滅危惧種。昔の名古屋人にはおなじみの春日一宏率いる民社党はもはや影も形もない。固い支持層がある公明党さえも新進党に参加したりとフラフラしていた。


新自由クラブ、新生党、新党さきがけ、日本新党、新進党ぐらいはまだ記憶があるけれど、黎明クラブ、新党平和、自由党、改革クラブ、新党友愛、太陽党、フロムファイブ、民政党とか言われるとどういう経緯でメンバーは誰かなのかはまるで記憶にない。
2010年以降でも、新党大地、みどりの風、日本未来の党、次世代の党、結の党、日本のこころを大切にする党、生活の党などなどどれくらい覚えているのか。減税日本などと言うのもありました。どれだけ記憶に残っているでしょうか。
自民党政権が続く中、激しい派閥間の争いが疑似政権交代をもたらしていたのだが、中選挙区での自民党の派閥争いが金権選挙になったことを改革するために政治改革が大きな争点となった。結果、今の小選挙区比例代表制となったのだが、小選挙区で勝つためには小異を捨てて大きくまとまらないと勝てないことに。
主義主張、理念、政策にこだわるとなかなかまとまらないのですが、少数政党はその存在意義をアピールするためにはなかなかこだわりを捨てることはできない。野党の場合は生き残るためには、どうしてもくっついたり離れたりするしかない…
それにしてもこの変遷を見てみると絶えず中心に小沢一郎がいる。もし彼が首相になっていたらどういう政治を行っていたのだろうか。ある時には反自民で主張の違いの多い政党をまとめ上げ政権交代を成し遂げ、ある時には自民党と連立を組み、政策が実現しないと連立を離脱。民主党をまとめ上げ選挙で圧勝し政権交代を実現するのだが、政治手法、意見の違いの中での激しい政争の当事者となって内部は迷走。政権を失うとともに民主党は自壊していった。今は存在感も薄れているのだが、今回の選挙協力ではまだまだ陰で動いていたのだろうか。彼がイマイチこの日本をどうしていきたいのか、どういう政策をしたいのかがよく分からない。
政権を担っている内は求心力が働くので、自民党を離脱するものはおらず、逆に権力にすり寄るものをどんどん引き付けていく。自分の主張するところを何分かの一でも実現するためには、多少のことは目をつぶるなりして政権与党にいるしかないのだから当然なのか。
この本の最後に今の小選挙区制度の下で立憲民主党が政権を担う対象とみなされるには、左寄りのリベラル政党と言うイメージを発展的に脱却し、中道の有権者にどうアプローチしていくのかが問われる。第三極を抑え込みつつ、中道を自ら引き寄せるのが政権交代の必要条件と言うのだが、共産党・社民党との選挙協力のように、今の立憲民主党は左寄りのリベラル政党の方向に純化しつつあるようで、政権交代までたどり着くのは難しい。
でも、安倍政治の極右路線(主張はヨーロッパの極右政党と同類)と主張を共にする身内だけを大事にする政治の私物化と、平気でうそをつく姿勢は気持ちが悪いのですが、どうなることでしょうか。なんとなく岸から池田、佐藤、田中、三木、福田、大平と熾烈な派閥争いの中での疑似政権交代があらまほしく思えてしまいます。












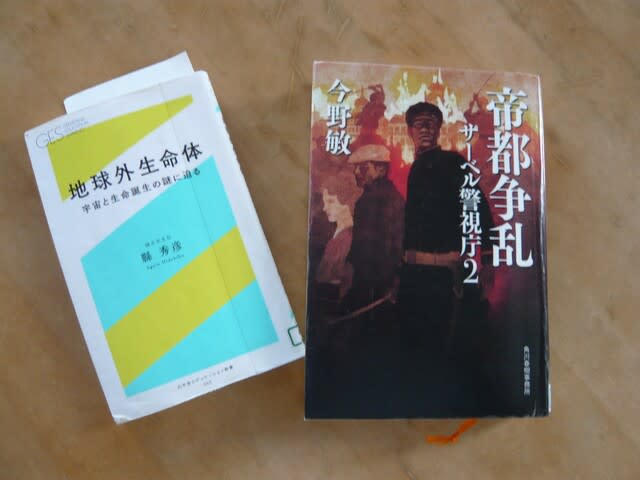
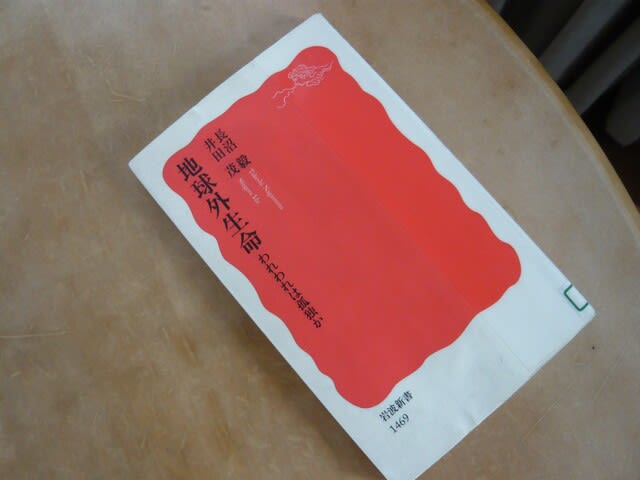









 14時50分には管理事務所で受け付け手続き。
14時50分には管理事務所で受け付け手続き。
 をします。
をします。















 。
。

 して試合にしましょう。私は最後の6番目に決定。
して試合にしましょう。私は最後の6番目に決定。

 をガンガン飲んできたそうで、コートに来てもさらに飲んでいるので動きが悪いのは当然でしょうか。
をガンガン飲んできたそうで、コートに来てもさらに飲んでいるので動きが悪いのは当然でしょうか。