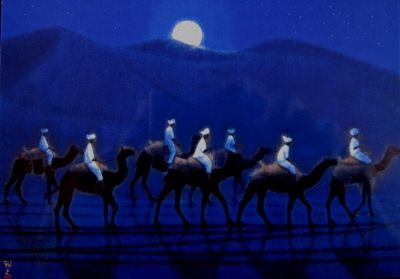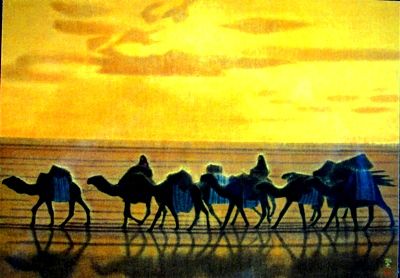【11月中旬の最終戦にもつれ込む? カギ握る3位「湯郷ベル」】
ロンドン五輪などのため中断していたサッカー女子のなでしこリーグは15日から後半戦に突入、10チームによる2回戦総当たりの2順目に入る。前半戦はINAC神戸が8勝1分けの無敗で独走、これを6勝2分け1敗の日テレと6勝1分け2敗の湯郷ベルが追う展開。優勝争いはほぼこの3チームに絞られてきた。神戸の連覇が成るのか、過去12回優勝の名門・日テレが雪辱を果たすのか、それとも日本代表の主将・宮間あや率いる湯郷の大逆転があるのか。場合によってはリーグ戦最終日(11月11日)の神戸―日テレ戦が雌雄を決する大一番になるかもしれない。
なでしこリーグ前半戦の順位と勝敗(勝ち点) ①神戸8勝1分け(25点)②日テレ6勝2分け1敗(20点)③湯郷ベル6勝1分け2敗(19点)④浦和4勝4分け1敗(16点)⑤ジェフ市原3勝2分け4敗(11点)⑥新潟3勝1分け5敗(10点)⑦伊賀2勝3分け4敗(9点)⑧狭山2勝2分け5敗(8点)⑨大阪高槻1勝2分け6敗(5点)⑩福岡0勝2分け7敗(2点)
神戸はロンドン五輪の日本代表7人を擁し、2年前の2010年10月以来公式戦の連続無敗記録(37勝6分け)を続けていた。ところが、9月9日の「なでしこリーグカップ」決勝で、日テレが神戸を3―2で破り2年ぶりに無敗記録にストップをかけた。日テレはこれで同カップが開かれた2007年、10年に続いて3大会を連覇。後半戦も宿敵の両チームを中心に激しい戦いが繰り広げられそうだ。
神戸の1分けは5月の湯郷との対戦で、0―0の引き分けだった。今季リーグ戦無敗の神戸は得点数も29点で他を引き離している。これは4月の初戦高槻戦、2戦目福岡戦でともに7―0と、2試合で14点を挙げたのが大きい。ただし、その後は接戦が続いている。2位日テレの唯一の敗戦は前半最終戦の神戸戦で0―1の惜敗だった。しかもこの1点もPK(川澄奈穂美)によるもの。日テレにとってはFW岩渕真奈が古傷の右足小指を痛め、この試合の後半に欠場を余儀なくされたのが痛かった。3チームの後半戦の対戦日程は10月21日=日テレ―湯郷、同28日=湯郷―神戸、11月11日=神戸―日テレとなっている。
前半戦のゴールランキング ①永里亜紗乃(日テレ)8点①吉良知夏(浦和)8点③高瀬愛実(神戸)7点④大野忍(神戸)5点④京川舞(神戸)5点④岩渕真奈(日テレ)5点➆川澄奈穂美(神戸)4点➆荒川恵理子(浦和)4点➆保坂のどか(市原)4点
日テレが1週間前の「なでしこリーグカップ」決勝で、神戸の連続無敗記録にストップをかけた最大の要因は永里の2得点・1アシストの大活躍。姉・大儀見優季(ポツダム)のロンドン五輪での活躍がいい刺激になっているのだろう。永里はリーグ戦前半のゴールランキングでも吉良とともに8得点で神戸勢を押しのけてトップ。吉良は昨年のリーグ戦で新人賞を獲得しているが、今年も期待通りの活躍を見せている。
昨年ともに12点でリーグ戦の得点王に輝いた神戸の大野と川澄も2年連続へ後半戦に賭けている。その中でランキング4位に名を連ねる若手のホープ京川と岩渕の2人が、けがによる手術で後半戦ピッチで見られそうにないのが残念。その代わり、U―20(20歳以下)女子W杯で存在感を発揮した田中陽子(神戸)や藤田のぞみ(浦和)、猶本光(浦和)、土光真代(日テレ)、田中美南(日テレ)ら「ヤングなでしこ」勢の活躍に期待したい。