
お城のデータ
市 (旧高島郡朽本村野尻) map:http://yahoo.jp/9FrpOP
別名:朽木陣屋
区 分:平城
城 域 :500m×180m
築城期:室町期
築城者:佐々木信綱・朽木五郎
城 主:佐々木信綱・朽木五郎・朽木元綱
遺 構:曲輪 ・土塁・井戸・
目標地:朽木資料館
駐車場:朽木資料館駐車場
訪城日:2013.8.23
 朽木城(江戸期は朽木陣屋)の石積
朽木城(江戸期は朽木陣屋)の石積
お城の概要
朽木郷土資料館横の史跡公園に、わずかな石垣と共に土塁、井戸が、また県道横には堀跡が残っていたが駐車場に。
当時は約10万平方メートルの敷地に本丸をはじめ、二の丸、三の丸、御殿,侍所,剣術道場、および馬場などがあったされる。
この朽木陣屋(朽木氏城)は、安曇川本流と支流の北川が合流する野尻に位置している。この地は若狭や越前などと京都を結ぶ朽木街道に面し、軍事上、政治的、および経済的にも交通の要衝である。
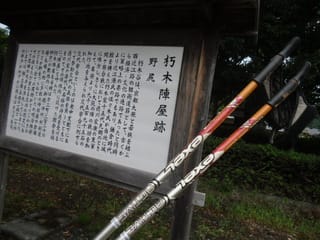
歴 史
朽木陣屋は佐々木氏の庶流である朽木氏の館跡に建てられたもので、江戸時代に陣屋へと変遷を遂げたと推定されている。
朽木氏は、承久3年(1221年)の承久の乱の後、佐々木信綱が朽木荘地頭職を得て、その子孫・義綱が朽木五郎と称したのに始まり、代々室町幕府の奉公衆を務め、天文22年(1553)三好長慶に京を追われた将軍足利義晴、義輝父子を匿うなど室町幕府を補佐した。
元亀元年(1570)織田信長の朝倉攻めが浅井長政の離反で失敗した際、信長の朽木越えを助けた。その後は織田信長、豊臣秀吉に仕え、朽木谷2万石を領有した。
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでは、当初は大谷吉継に従って西軍に属したものの、小早川秀秋に呼応して脇坂安治や小川祐忠、赤座直保らとともに東軍に寝返った。
戦後、寝返り理由を明らかにしなかったとの理由により厳封されたが、以後準大名格でこの地を領有し、明治維新を迎えた
朽木元綱
元亀元年(1570年)の朝倉攻めにおいては松永久秀の説得を受けて織田信長の京都撤退(朽木越え)を助け、後に信長に仕え信長麾下として磯野員昌、その追放後は津田信澄に配されているが、天正7年(1579年)には代官を罷免されているので、信長からは厚遇されていなかったようである。
信長の死後は豊臣秀吉に仕え、伊勢安濃郡・高島郡内の蔵入地の代官に任ぜられ、小田原征伐にも参加、朽木谷2万石を安堵されている。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、甲賀の城、
本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!



























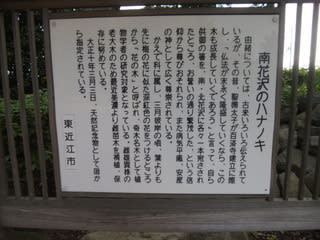
 候補地は、2ヶ所
候補地は、2ヶ所 遠望の林:善明寺
遠望の林:善明寺 小池集落
小池集落 遠望:鹿島神社
遠望:鹿島神社