先日、筑波大学発ベンチャー企業であるソフトイーサ(茨城県つくば市)の登大遊(のぼりだいゆう)代表取締役にお目にかかりました。同社は、2003年に筑波大に入学した登さんが、第三学群情報学類1年生の時に起業した大学発ベンチャー企業として有名です。
登さんは2004年4月1日に資本金100万円で同社を創立し、代表取締役社長に就任しました。
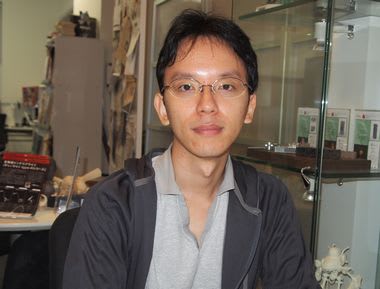
筑波大発ベンチャー企業の中では、学生が創業した企業としては第2番目だそうです。
同社を創業してから7年が過ぎ、同社は少数精鋭の研究開発型ベンチャー企業として順調に成長しています。現在27歳の登さんは、独創的なソフトウエア開発を目指す若手IT開発者などにとってのあこがれの人であり、その生き様が目標にもなっている“伝説の人物”です。
登さんは、小学生の時に親がゲーム機を買ってくれなかったために、もらったパソコンを用いて、いくつかのプログラミング言語を使ってゲーム系のソフトウエアを自作したそうです。高校生の時には、学校のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)導入を支援するなどの実績を残し、教師たちに一目置かれる存在になりました。
高校生の時に、パソコン雑誌などにゲーム系の解説を書き始め、これがきっかけになってゲーム作成用プログラミングの単行本を数冊執筆しました。また、当時出始めたばかりの携帯電話機向けのシェアソフトウエアを書いて、“お小遣い”以上の収入をえました。この収入の一部が、2004年に創業したソフトイーサの出資金の原資となったそうです。
成績優秀な高校生だった登さんは、いろいろな大学を見学して、設備がそろっている点と、大学教員がいろいろと親身に教えてくれた点が気に入って、筑波大のAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)を受けます(筑波大ではAC=アドミッションセンター入試と呼んでいます)。自分の得意技の実力を示し、その審査結果によって合否が決まる入試の方法です。
筑波大1年生の登さんは、2003年度に経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構(IPA」)が2002年度から始めた通称“未踏ユース”の一人に選ばれます。未踏ユースは、30歳以下の若手の突出したIT開発者を育成するために実施された未踏ソフトウェア創造事業です。有名な教授などが務めるプロジェクトマネージャー(PM)の下で、選ばれた若手人材が開発資金を受け取って開発目標を達成する委託開発事業でした。
2003年12月に、筑波大1年生の登さんは、未踏ユースで開発したVPN(仮想プライベートネットワーク)ソフトウエアの「SoftEther1.0」のβ版を公開しました。翌年2004年3月には「SoftEther1.0」完成版(Linux対応)を公表しました。この「SoftEther1.0」はとても使いやすいソフトウエアだと好評だったことを受けて、登さんは大学の仲間2人と、ソフトイーサを創業しました。
同社は創業第3期の2006年度から2009年度まで、1億円強の売上高を達成し続けています。税引き後の利益は2006年度から2008年度まで黒字を維持しています。公表されている最新の2009年度は同利益が約1000万円の赤字になっていますが、これは事業投資によるもののようです。
驚くことは、同社の役員3人と従業員の総数は、2010年3月時点で10人と少数精鋭です。「つい最近1人減って、9人になった」と、登さんはいいます。闇雲に従業員を増やすという成長路線を採っていないそうです。
日本の若手プログラマーなどにとっては、同社はあこがれの存在ですが、原則、求人募集をしていないそうです。「入社志願者は確かにたくさんいますが、入社してほしい人物と、入社希望者の資質の差が大きい」とのことです。この点から、同社は未踏ユースなどで育成された、飛び抜けて優秀な若手IT開発者だけが集まる場であり続けることが成長戦略になっているようです。
登さんは2004年4月1日に資本金100万円で同社を創立し、代表取締役社長に就任しました。
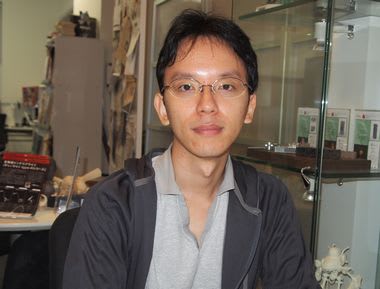
筑波大発ベンチャー企業の中では、学生が創業した企業としては第2番目だそうです。
同社を創業してから7年が過ぎ、同社は少数精鋭の研究開発型ベンチャー企業として順調に成長しています。現在27歳の登さんは、独創的なソフトウエア開発を目指す若手IT開発者などにとってのあこがれの人であり、その生き様が目標にもなっている“伝説の人物”です。
登さんは、小学生の時に親がゲーム機を買ってくれなかったために、もらったパソコンを用いて、いくつかのプログラミング言語を使ってゲーム系のソフトウエアを自作したそうです。高校生の時には、学校のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)導入を支援するなどの実績を残し、教師たちに一目置かれる存在になりました。
高校生の時に、パソコン雑誌などにゲーム系の解説を書き始め、これがきっかけになってゲーム作成用プログラミングの単行本を数冊執筆しました。また、当時出始めたばかりの携帯電話機向けのシェアソフトウエアを書いて、“お小遣い”以上の収入をえました。この収入の一部が、2004年に創業したソフトイーサの出資金の原資となったそうです。
成績優秀な高校生だった登さんは、いろいろな大学を見学して、設備がそろっている点と、大学教員がいろいろと親身に教えてくれた点が気に入って、筑波大のAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)を受けます(筑波大ではAC=アドミッションセンター入試と呼んでいます)。自分の得意技の実力を示し、その審査結果によって合否が決まる入試の方法です。
筑波大1年生の登さんは、2003年度に経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構(IPA」)が2002年度から始めた通称“未踏ユース”の一人に選ばれます。未踏ユースは、30歳以下の若手の突出したIT開発者を育成するために実施された未踏ソフトウェア創造事業です。有名な教授などが務めるプロジェクトマネージャー(PM)の下で、選ばれた若手人材が開発資金を受け取って開発目標を達成する委託開発事業でした。
2003年12月に、筑波大1年生の登さんは、未踏ユースで開発したVPN(仮想プライベートネットワーク)ソフトウエアの「SoftEther1.0」のβ版を公開しました。翌年2004年3月には「SoftEther1.0」完成版(Linux対応)を公表しました。この「SoftEther1.0」はとても使いやすいソフトウエアだと好評だったことを受けて、登さんは大学の仲間2人と、ソフトイーサを創業しました。
同社は創業第3期の2006年度から2009年度まで、1億円強の売上高を達成し続けています。税引き後の利益は2006年度から2008年度まで黒字を維持しています。公表されている最新の2009年度は同利益が約1000万円の赤字になっていますが、これは事業投資によるもののようです。
驚くことは、同社の役員3人と従業員の総数は、2010年3月時点で10人と少数精鋭です。「つい最近1人減って、9人になった」と、登さんはいいます。闇雲に従業員を増やすという成長路線を採っていないそうです。
日本の若手プログラマーなどにとっては、同社はあこがれの存在ですが、原則、求人募集をしていないそうです。「入社志願者は確かにたくさんいますが、入社してほしい人物と、入社希望者の資質の差が大きい」とのことです。この点から、同社は未踏ユースなどで育成された、飛び抜けて優秀な若手IT開発者だけが集まる場であり続けることが成長戦略になっているようです。









