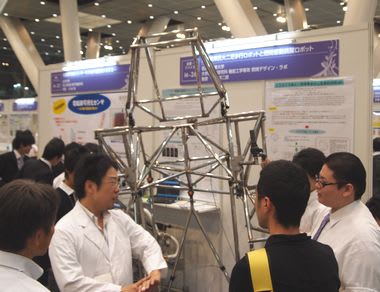長野県茅野市などにまたがる“北八ヶ岳”と呼ばれる地域にある、北横岳直下の「坪庭」から、日本の中部にある代表的な山々が展望できました。
標高2480メートルの北横岳の直下に広がる「坪庭」と呼ばれる溶岩台地からは、日本を代表する南アルプスの北側、中央アルプスの南西側、北アルプスの東側の山々を見ることができます。当然、南八ヶ岳の山々も見ることができます。
坪庭のすぐ目の前に縞枯山(標高2403メートル)を仰ぎ見ることができます。北横岳の東側に位置します。この縞枯山の山肌は、針葉樹が帯状に立ち枯れる“縞枯れ現象”が起きています。

この“縞枯れ現象”が起こる原因はまだ分からないとのことです。
標高が2240メートルぐらいある坪庭入り口の、ピラタス蓼科ロープウェイの山麓駅近くからは、180度ぐらいのパノラマが展望できました。パンフレットに掲載された山々の形との照らし合わせから、展望できる山々の名前を推測しました。
南アルプスの山々は、中央部左の峰が北岳、真ん中が甲斐駒ヶ岳、左側の少し広がった峰々が仙丈岳のようです。

南アルプスの山々の山頂部分は晴れているようです。この部分の青空がきれいです。
中央アルプスの山々は左側の峰々が空木岳、右側の峰々が木曽駒ヶ岳・宝剣岳のようです(記憶と写真画像が微妙に一致しないので)。

北アルプスは独特の峰の形の槍ケ岳が見え、その左側に穂高連山の山々が見えます。その背景には、視界がいい時は白山も見えるそうです。日本の中央部分は山国であると、改めて思いました。
ピラタス蓼科ロープウェイで降りてくる途中では、独特の溶岩ド-ムが目につく蓼科山や、霧ヶ峰の中央にそびえる車山を見ることができました。

車山の山頂にある気象庁の車山気象観測レーダー観測所がよく見えます。その背後には美ヶ原も見えました。霧ヶ峰高原から美ヶ原高原までの山々も、日本を代表する山岳風景だと改めて思いました。
標高2480メートルの北横岳の直下に広がる「坪庭」と呼ばれる溶岩台地からは、日本を代表する南アルプスの北側、中央アルプスの南西側、北アルプスの東側の山々を見ることができます。当然、南八ヶ岳の山々も見ることができます。
坪庭のすぐ目の前に縞枯山(標高2403メートル)を仰ぎ見ることができます。北横岳の東側に位置します。この縞枯山の山肌は、針葉樹が帯状に立ち枯れる“縞枯れ現象”が起きています。

この“縞枯れ現象”が起こる原因はまだ分からないとのことです。
標高が2240メートルぐらいある坪庭入り口の、ピラタス蓼科ロープウェイの山麓駅近くからは、180度ぐらいのパノラマが展望できました。パンフレットに掲載された山々の形との照らし合わせから、展望できる山々の名前を推測しました。
南アルプスの山々は、中央部左の峰が北岳、真ん中が甲斐駒ヶ岳、左側の少し広がった峰々が仙丈岳のようです。

南アルプスの山々の山頂部分は晴れているようです。この部分の青空がきれいです。
中央アルプスの山々は左側の峰々が空木岳、右側の峰々が木曽駒ヶ岳・宝剣岳のようです(記憶と写真画像が微妙に一致しないので)。

北アルプスは独特の峰の形の槍ケ岳が見え、その左側に穂高連山の山々が見えます。その背景には、視界がいい時は白山も見えるそうです。日本の中央部分は山国であると、改めて思いました。
ピラタス蓼科ロープウェイで降りてくる途中では、独特の溶岩ド-ムが目につく蓼科山や、霧ヶ峰の中央にそびえる車山を見ることができました。

車山の山頂にある気象庁の車山気象観測レーダー観測所がよく見えます。その背後には美ヶ原も見えました。霧ヶ峰高原から美ヶ原高原までの山々も、日本を代表する山岳風景だと改めて思いました。