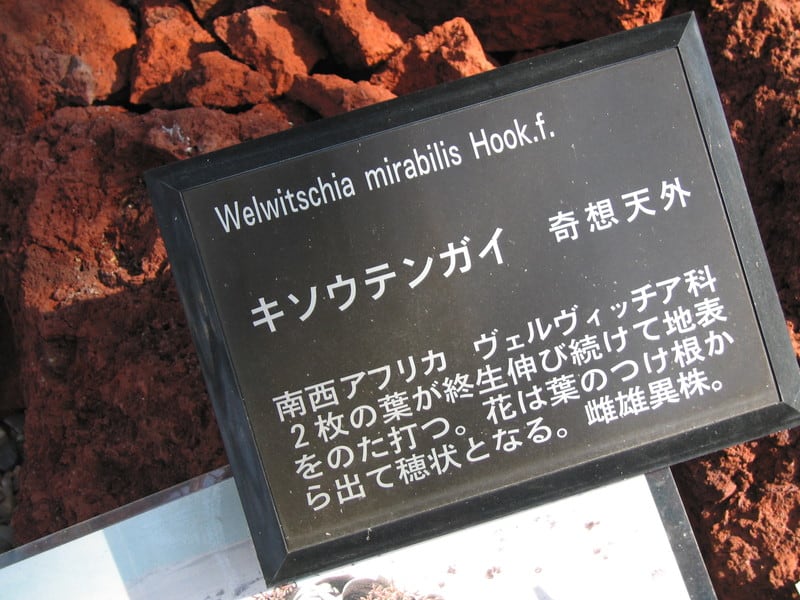京都の都道府県対抗女子駅伝をテレビ観戦しながら、年明けに、京都の高麗美術館から届いた2008年の展覧会案内に目を通しています。映像作品『朝鮮通信使』の取材・ロケで大変お世話になった朝鮮美術専門の私立美術館で、今年、開館20周年を迎えます。
平成と同時に誕生した美術館ですが、創設までには多くの道程があったようです。上田正昭館長のメッセージによると、発端は、1969年に創刊された季刊誌「日本のなかの朝鮮文化」。72年に奈良の明日香村で高松塚古墳が発見され、高句麗壁画との関わりが広く知られ、日本の古代文化と朝鮮文化の関係にいち早く着目した同誌が高く評価されました。73年に東京で開催された「日本のなかの朝鮮文化を励ます会」には、司馬遼太郎、金達寿、谷川徹三、中野重治、松本清張、陳舜臣、岡本太郎、有吉佐和子、永井路子、和歌森太郎、井上光貞といった錚々たる名士が揃ったそうです。
「すべての国の人々が、祖国の歴史や文化を正しく理解することで、真の国際人となる一歩を踏み出してほしい」・・・私財を投げ打って館の創設に尽力した故・鄭詔文氏(初代理事長)の言葉です。これは、朝鮮通信使の接待役を務めた雨森芳洲(対馬藩の儒学者)の「互いの違いを知り、理解し、敬い、誠意を尽くせ」という誠信の教えにも通じます。
私はそのことを、『朝鮮通信使』の取材・ロケでお世話になった高麗美術館の学芸員・片山真理子さん(写真奥)からも、身をもって教えられました。
片山さんは、私が最初、飛び込みで美術館を訪れたとき、不快な顔ひとつせず、時間を割き、丁寧に取材に応じてくれました。他の施設では門前払いをくらったり、撮影許可が下りなかったり、煩雑な手続きで時間がかかる文化財撮影にも、「朝鮮文化を伝える素晴らしい機会だから」とすんなり応じてくれました。
撮影時には場所や道具をきちんと用意し、監督やカメラマンの要望にきめ細かく対応してくれます。カメラマンの成岡正之さんは「この手の撮影の場合、勝手に撮れと放っておかれるか、いちいちダメ出しをしてこちらにプレッシャーをかけるところが多いけど、こんなにすんなり気持ちよく撮影ができるケースは珍しい」と感心していました。
キュレーターという職業に憧れ、学芸員資格も持つ私は、片山さんの仕事ぶりに感激し、すっかりファンになり、撮影後も折に触れて連絡を取り、館が92年から定期的に開催する『高麗美術館研究講座』にも通うようになりました。次回2月23日(土)の第105回講座は、朝鮮通信使の画人と日本の画家の交流をテーマにした内容で、個人的にも楽しみです。
20周年特別展では4月12日~5月25日まで「愉快なクリム―朝鮮民画」を開催。クリムとは朝鮮語で絵や図のことで、静岡市立芹沢銈介美術館のコレクションも出品されます。「静岡との縁が再び出来て、うれしい」と片山さんも喜んでくれました。
自国や隣国の文化を正しく理解し、その交流がもたらした功績を知る・・・『朝鮮通信使』の仕事は、私のこれからの取材活動に多くの道標を与えてくれました。脚本の出来栄えには不満足な点も多々ありますが、とにかく、多くの人に見ていただかないことには、片山さんたちの思いを伝えられないわけです。未見の方は、ぜひ2月15日の上映会に来てくださいね。