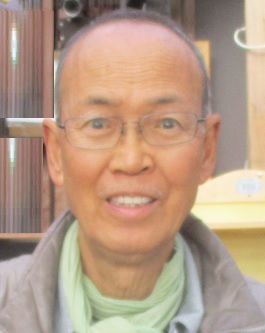村上和隆
京都事務所:京都市伏見区深草出羽屋敷町23ファミール伏見B905
滋賀支所:滋賀県高島市安曇川町長尾字上塚野1189-10
新:村上和隆総合支援&村上原基人生勉強会
新:関西ISOシニアコンサルタントネットワーク
台東区立育英小学校⇒台東中学校⇒都立白鴎高校⇒東工大⇒大阪松下電器⇒京都エンゼル工業⇒ローム⇒テクノ経営⇒関西ISOシニアコンサルタントネットワーク創業⇒人生勉強会創設
いつでも気軽に人生相談や人生談義にお越し下さい⇒滋賀人生勉強会・クリック
村上原基今日の一言
人生とは何ぞや、人それぞれいろいろな考えがあるが
「人生とは楽あり苦あり」楽ばかりでないどころか苦ばかりと嘆く人も多い
はたから見ると、結構楽ばかりしているのだが、本人は勝手に苦悶する
人生で一生涯、最も大きな難問は、人生につきまとう苦との向き合い方だ
苦とは一体なんだろう?真剣に深く考えたことがありますか?
意外に「苦とは何か、苦にどう向き合うか」を答えようとしない
人間は死・病・老・貧など嫌なことは深く考えない傾向がある
まあ、それもそうだろう、嫌なことを考えると憂鬱になるばかり
つらいのはわかる、でも
「嫌なものは考えない」ではなくむしろ必死に考えるべきだ
『苦とは自分の思いどおりにならないこと』と説明されている
自分にとって”思い通りとは”どんな状態か常に深く考えること
ポイントは、”自分の思い通り”が人によって大きく異なることである
結果的に人によって苦の感じ方や対処の仕方も大きく異なる
ある人には深刻な苦であることでも別の人には全く苦でないということがある
又は苦であっても、狼狽する人もいるし、明るく前向きに対処する人もいる
当然ですが質素・謙虚・誠実・素直・真面目・健康な人には、苦も大した苦ではない
苦が多い、大きいという人は、まずそういうものを見直すべきなんだ
苦にはまった時に冷静に苦の元である”自分の思い通り”を分析してみることだ
自分は何を思い通りにしたいのか?何が思い通りにならないのか?と
自分の思いが甘いのではないか?
自然観に基づく冷静さが人間には必要だが、
苦の体験は、冷静に対処する能力を身につけてもくれるものなのだ
そのためにも、苦の原因を他のせいにしてはならない
例外なく「自分自身が苦を作り出している」と認識すべきなのだ
そして苦をわが友、わが親、わが師のように対処すべきなのだ
多くの人にとっては苦は、嫌な、遠ざけたい、辛いものである
そして苦が大きいほど、そのつらさは持続し、永く苦しめる
人により年齢により、置かれている状況により苦の感じ方は相対的である
かなりつらい苦さえも喜びだという人生の達人みたいな人もいる
苦=嫌でなく、苦=歓迎と考える人も僅かにいるが、実に望ましいことだ
僧侶の修行なんてのも全て、苦に強くなるための心身の修練である
そういう立派な僧侶には、凡人が感じる苦はなくなる
苦から逃れようとする人は、逆に、永遠に苦を卒業できない
むしろいつも苦に追い回される悲しい運命をたどることになる
苦とは結果的には、後々自分を大きく成長させるのだ
苦に耐え、苦に負けず、味方にさえするには
・深刻な苦にならないように巧みに予防する知恵を持つか
・まともに苦に耐えられる自分を磨くか
苦とは自分自身の間違った行いによって起こる
他から降りかかってくるものは皆無と認識すべきなのだ
苦=自分が原因=自分の責任であることを重々知っておかないといけない
苦がやってきて、その苦にうまく対応するには
①苦をすぐに忘れる(深い、長い悩みは人をボロボロにする可能性がある)
②苦に強くなる(打たれ強くなる)
③苦を感じなくさせる(苦に反応し過ぎるのは?)
④自分の思いをレベルダウンする
⑤確実に思い通りになるように創意工夫する(これはあまり望ましくないが)
⑥確実に思い通りになるようにきちんとルールを決め守る
⑦苦の元を解消する
⑧苦を一人で抱え込まない(他人に相談する)
⑨専門家や能力ある人に助けを求める
⑩苦と戦う(一種の修行、苦こそ自分を高めるものだと自覚する)
⑪苦を何かで紛らわす
⑫苦をむしろ嬉しいことだと思う
それぞれに簡単なようで案外難しい
姑息に対応すればするほど苦から逃れられない
悩み相談で多いのが「次々に苦るしいことが起きるがどうしたらいいでしょうか?」
こういう人の多くは”苦からいかに簡単に逃れるか”だけを考えようとする
大病をして、手術も嫌、禁煙禁酒も嫌、過食も止められない、運動もしない、生活習慣も直せない
麻薬中毒なのに、なんとか麻薬を止めずに健康を取り戻せないかと考える
「つらいことは何にもせずに、なんとかこの大病を直したい」なんていうようなものだ、虫のいい話だ
苦へのうまい対応が当たり前に出来れば人生も楽しい
決して喜びでも幸でもないかもしれないが、
苦と上手に付き合えれば、それだけでも大きな儲けものだ
それぞれに解決法があるが、苦るしい時に
こういう場合は以上に示した12のどの方法で解決すべきか
自分の能力と相談して適切に選ぶことだ
場合によっては苦に逆らわず、紛らわしたり、通り過ぎるのをじっと待つほうがよい場合もあるだろう
一時的な癒しや逃避は緊急的・便宜的な対処法に過ぎない
そんなことばかりで、いつもうまく行くということはない
時間や能力があれば、簡単ではないが時間をかけ、まともに苦を克服する方法を習得すべきだろう
しかしそうは言っても、年齢とともに、境遇に応じて次々に大きな苦はやって来る
苦は止まってくれない、待ってはくれない
苦への抵抗力を蓄えれば、それだけ苦から逃れることができる
というよりは、苦が苦でなくなる、苦の大きさが軽減する
苦から逃げてばかりいればどんどん苦は増え、強まる
自分の思い通りにならないこと=苦とどのように向き合い
自分を苦に強くならしめるか
私が最近心掛けていること
①ため息つかない
②嘆かない
③愚痴零さない
④暗い顔しない
⑤嫌だと思わない
⑥笑顔・明るさを保つ
⑦嫌なことを考え込まない
⑧悪いことは一日以内で忘れる
⑨前向きな思考
⑩前向きな発言
⑪どげんかなる・どげんかする
⑫更に最悪な人や状況を考え、それよりもましだと考える
「人間は本来無一物」「人間はやがて死ぬ」「もっとつらいことはあるまだましなほうだ」
と思えばよいのだ
苦とどう向き合うか、人生の最大かつ重要な課題だ
幸を求めるより、苦を友とし、師とし、うまく付き合うことこそ本物の幸への道だ
苦しみの多い人は、次のような人だ
①だらしない
②甘え
③依存
④逃避
⑤浪費
⑥不勉強
⑦病弱
⑧頑固
⑨怠惰
⑩責任転嫁
⑪傲慢
⑫孤独・引籠り

京都事務所:京都市伏見区深草出羽屋敷町23ファミール伏見B905
滋賀支所:滋賀県高島市安曇川町長尾字上塚野1189-10
新:村上和隆総合支援&村上原基人生勉強会
新:関西ISOシニアコンサルタントネットワーク
台東区立育英小学校⇒台東中学校⇒都立白鴎高校⇒東工大⇒大阪松下電器⇒京都エンゼル工業⇒ローム⇒テクノ経営⇒関西ISOシニアコンサルタントネットワーク創業⇒人生勉強会創設
いつでも気軽に人生相談や人生談義にお越し下さい⇒滋賀人生勉強会・クリック
村上原基今日の一言
人生とは何ぞや、人それぞれいろいろな考えがあるが
「人生とは楽あり苦あり」楽ばかりでないどころか苦ばかりと嘆く人も多い
はたから見ると、結構楽ばかりしているのだが、本人は勝手に苦悶する
人生で一生涯、最も大きな難問は、人生につきまとう苦との向き合い方だ
苦とは一体なんだろう?真剣に深く考えたことがありますか?
意外に「苦とは何か、苦にどう向き合うか」を答えようとしない
人間は死・病・老・貧など嫌なことは深く考えない傾向がある
まあ、それもそうだろう、嫌なことを考えると憂鬱になるばかり
つらいのはわかる、でも
「嫌なものは考えない」ではなくむしろ必死に考えるべきだ
『苦とは自分の思いどおりにならないこと』と説明されている
自分にとって”思い通りとは”どんな状態か常に深く考えること
ポイントは、”自分の思い通り”が人によって大きく異なることである
結果的に人によって苦の感じ方や対処の仕方も大きく異なる
ある人には深刻な苦であることでも別の人には全く苦でないということがある
又は苦であっても、狼狽する人もいるし、明るく前向きに対処する人もいる
当然ですが質素・謙虚・誠実・素直・真面目・健康な人には、苦も大した苦ではない
苦が多い、大きいという人は、まずそういうものを見直すべきなんだ
苦にはまった時に冷静に苦の元である”自分の思い通り”を分析してみることだ
自分は何を思い通りにしたいのか?何が思い通りにならないのか?と
自分の思いが甘いのではないか?
自然観に基づく冷静さが人間には必要だが、
苦の体験は、冷静に対処する能力を身につけてもくれるものなのだ
そのためにも、苦の原因を他のせいにしてはならない
例外なく「自分自身が苦を作り出している」と認識すべきなのだ
そして苦をわが友、わが親、わが師のように対処すべきなのだ
多くの人にとっては苦は、嫌な、遠ざけたい、辛いものである
そして苦が大きいほど、そのつらさは持続し、永く苦しめる
人により年齢により、置かれている状況により苦の感じ方は相対的である
かなりつらい苦さえも喜びだという人生の達人みたいな人もいる
苦=嫌でなく、苦=歓迎と考える人も僅かにいるが、実に望ましいことだ
僧侶の修行なんてのも全て、苦に強くなるための心身の修練である
そういう立派な僧侶には、凡人が感じる苦はなくなる
苦から逃れようとする人は、逆に、永遠に苦を卒業できない
むしろいつも苦に追い回される悲しい運命をたどることになる
苦とは結果的には、後々自分を大きく成長させるのだ
苦に耐え、苦に負けず、味方にさえするには
・深刻な苦にならないように巧みに予防する知恵を持つか
・まともに苦に耐えられる自分を磨くか
苦とは自分自身の間違った行いによって起こる
他から降りかかってくるものは皆無と認識すべきなのだ
苦=自分が原因=自分の責任であることを重々知っておかないといけない
苦がやってきて、その苦にうまく対応するには
①苦をすぐに忘れる(深い、長い悩みは人をボロボロにする可能性がある)
②苦に強くなる(打たれ強くなる)
③苦を感じなくさせる(苦に反応し過ぎるのは?)
④自分の思いをレベルダウンする
⑤確実に思い通りになるように創意工夫する(これはあまり望ましくないが)
⑥確実に思い通りになるようにきちんとルールを決め守る
⑦苦の元を解消する
⑧苦を一人で抱え込まない(他人に相談する)
⑨専門家や能力ある人に助けを求める
⑩苦と戦う(一種の修行、苦こそ自分を高めるものだと自覚する)
⑪苦を何かで紛らわす
⑫苦をむしろ嬉しいことだと思う
それぞれに簡単なようで案外難しい
姑息に対応すればするほど苦から逃れられない
悩み相談で多いのが「次々に苦るしいことが起きるがどうしたらいいでしょうか?」
こういう人の多くは”苦からいかに簡単に逃れるか”だけを考えようとする
大病をして、手術も嫌、禁煙禁酒も嫌、過食も止められない、運動もしない、生活習慣も直せない
麻薬中毒なのに、なんとか麻薬を止めずに健康を取り戻せないかと考える
「つらいことは何にもせずに、なんとかこの大病を直したい」なんていうようなものだ、虫のいい話だ
苦へのうまい対応が当たり前に出来れば人生も楽しい
決して喜びでも幸でもないかもしれないが、
苦と上手に付き合えれば、それだけでも大きな儲けものだ
それぞれに解決法があるが、苦るしい時に
こういう場合は以上に示した12のどの方法で解決すべきか
自分の能力と相談して適切に選ぶことだ
場合によっては苦に逆らわず、紛らわしたり、通り過ぎるのをじっと待つほうがよい場合もあるだろう
一時的な癒しや逃避は緊急的・便宜的な対処法に過ぎない
そんなことばかりで、いつもうまく行くということはない
時間や能力があれば、簡単ではないが時間をかけ、まともに苦を克服する方法を習得すべきだろう
しかしそうは言っても、年齢とともに、境遇に応じて次々に大きな苦はやって来る
苦は止まってくれない、待ってはくれない
苦への抵抗力を蓄えれば、それだけ苦から逃れることができる
というよりは、苦が苦でなくなる、苦の大きさが軽減する
苦から逃げてばかりいればどんどん苦は増え、強まる
自分の思い通りにならないこと=苦とどのように向き合い
自分を苦に強くならしめるか
私が最近心掛けていること
①ため息つかない
②嘆かない
③愚痴零さない
④暗い顔しない
⑤嫌だと思わない
⑥笑顔・明るさを保つ
⑦嫌なことを考え込まない
⑧悪いことは一日以内で忘れる
⑨前向きな思考
⑩前向きな発言
⑪どげんかなる・どげんかする
⑫更に最悪な人や状況を考え、それよりもましだと考える
「人間は本来無一物」「人間はやがて死ぬ」「もっとつらいことはあるまだましなほうだ」
と思えばよいのだ
苦とどう向き合うか、人生の最大かつ重要な課題だ
幸を求めるより、苦を友とし、師とし、うまく付き合うことこそ本物の幸への道だ
苦しみの多い人は、次のような人だ
①だらしない
②甘え
③依存
④逃避
⑤浪費
⑥不勉強
⑦病弱
⑧頑固
⑨怠惰
⑩責任転嫁
⑪傲慢
⑫孤独・引籠り