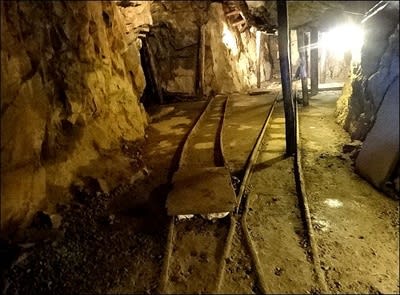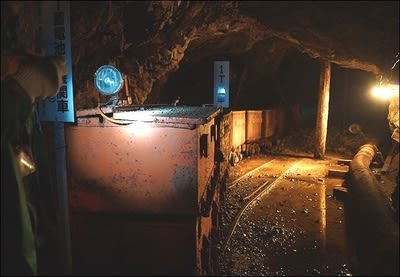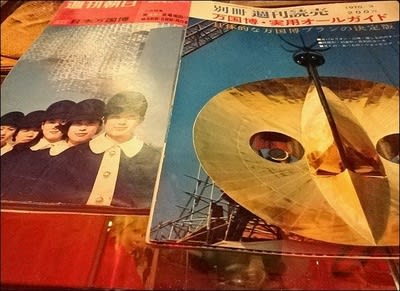広島県・三原市の「佛通寺」では、紅葉の頃になると
美しい風情が見られるそうな。
御許山「佛通寺」は、日本屈指の参禅道場として知られる
臨済宗・佛通寺派の大本山。
以前、旅の途中に出会った若い修行僧に教えてもらい、
出かけたことがありました。
その時のいきさつが⇒こちら
実際、黄色、朱色、赤色など見事に色づき、県屈指の
紅葉の名所として、多くの参拝者が訪れていました。
紅葉時期の広島へ行く機会があり、佛通寺を再訪することに。
紅葉スポットなのに、色づき具合がノーデータというのはなぜ!?
例年の見頃は11月中旬だから、外れはないかと思いますが…


参道や駐車場付近の公園はちょうど良い色づきでした。


巨蟒橋(きょもうきょう)という屋根付き橋を渡って境内へ。
蟒…うわばみ、巨大な蛇のこと。
邪念を捨てて橋を渡らなければならないとされる。

橋の下を流れる佛通寺川


橋を渡って総門へ
白壁の5本線は後小松天皇(一休さん父君)の勅願寺を示す。

─ 羅漢庭 ─


大玄関、奥の間には樟の一木彫りの坐禅達磨像も。


大方丈から多宝塔を眺める。 いい眺めだこと!
佛通寺は応永四年(1397)に、小早川春平公が
愚中周及禅師を招いて開いた禅宗のお寺で、
最盛期には山内塔頭八十八ヶ寺、末寺三千ヶ寺を
数えたという。


庫裏の横には禅堂があり、修行僧の坐禅や一般企業や
学生の研修なども行われている。


また巨蟒橋を渡り、公園まで戻ってくると、
嬉しいことに休憩所が!
おぜんざいをいただくことにしました。


紅葉を眺めながら、温かい飲み物をいただくと、
やっぱり落ち着きますね~


広島へは観光目的で来た訳じゃないのですが、
たっぷりと目の保養をさせてもらいました。
今度訪れるときは家族がひとり増えていることでしょう。