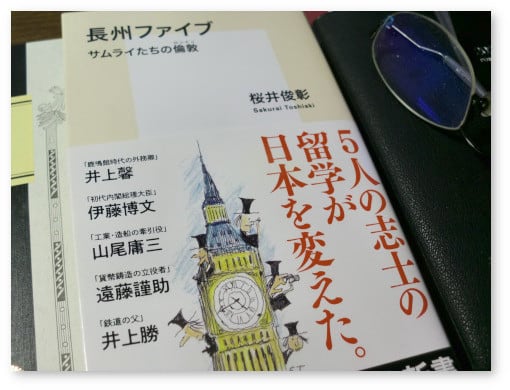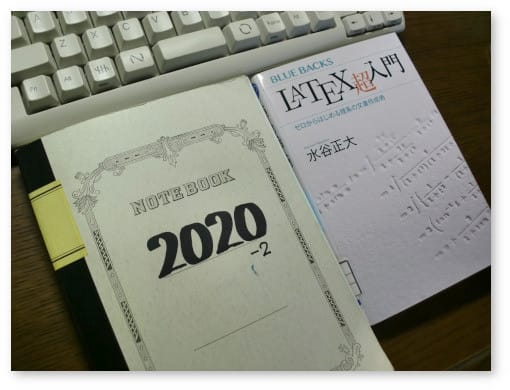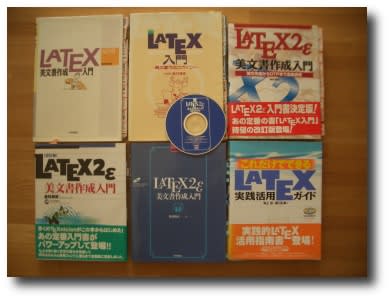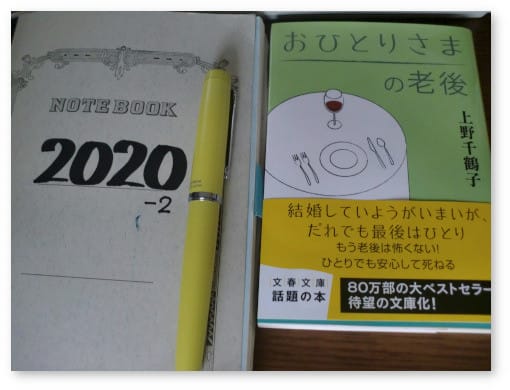明治維新の後、米沢藩主・上杉茂憲(もちのり)は県令として沖縄に赴任します。そういう史実があったことは承知していましたが、雪国生まれの元大名がなぜ南の島沖縄に行くことになったのか、またそこでどのような生活をしていたのか、実はかなり不思議でした。たまたま当地のローカルテレビで、作家の髙橋義夫氏が沖縄を訪れ、上杉茂憲の足跡をたどるという番組を観て、『沖縄の殿様〜最後の米沢藩主・上杉茂憲の県令奮闘記』という中公新書の存在を知り、さっそく入手して読んでみたものです。
本書の構成は次のとおりです。
序章 雪国と南島
第1章 沖縄の発見
第2章 沖縄本島巡回
第3章 教育と予算
第4章 刑法と慣習
第5章 上杉県令の改革意見
第6章 政治的刺客
第7章 辻遊廓
第8章 県費留学生
第9章 那覇八景
元大名というと、苦労知らずのボンボンというような誤解が生まれがちですが、上杉茂憲は明治維新と戊辰戦争という荒波を経て、廃藩置県の翌年にあたる明治五年、華族に海外留学を促す明治天皇の勅諭に従い、およそ一年間の英国留学をしているそうです。この間に妻と長女を亡くしたばかりか、側室の不義が発覚、継室と離縁し、三十六歳で十五歳下の妻を得てようやく身辺が落ちつくという、公私ともに苦労人だったようです。明治十四年に沖縄県令に着任することになったきっかけというのが、やっぱり「家計の窮乏」によるもので、初代県令鍋島直彬が病気で辞任した後に、池田成章を抜擢する形で上杉に決まった、ということのようです。
しかし、当時の沖縄は、宮古島の上納船が台湾に漂着し、乗組員が現地住民に殺害された事件をきっかけに「征台の役」が起こり、軍事力を持って琉球国を琉球藩として帰属を清国に認めさせ、賠償を勝ち取り沖縄県を設置するという、いわゆる琉球処分を行って十年にも満たない頃でした。この微妙な時期に、「県治においては決して美治の急施を要むべからず」との方針のもとに、上杉新県令が発令されたことになります。
ここからは、上杉県令の沖縄の旅を記録した『沖縄本島巡回日誌』等をもとに、様々な視点から茂憲が庶民生活を視察した様子が具体的に描かれます。端的に言えば、薩摩藩の過酷な収奪に発する貧しさと借金、およびそこから派生する諸問題です。
具体的な中身は省きますが、上杉県令は改革意見を政府に上申します。ところが、これが明治政府の沖縄統治の方針に異を唱えたとして問題になります。その回答が、政治的刺客として尾崎三良を送り込み、上杉の県政を覆すことでした。このあたりは、改革派の支社長に本店側が腹心を送り込み、改革を頓挫させるという権力闘争を思わせるドラマです。
では、上杉茂憲の改革案はすべて水泡に帰したのかというと、必ずしもそうとは言えないのが救いです。著者は、教育の振興や内地への県費留学生の推進などをあげ、彼らの活躍が沖縄振興に貢献したとして、上杉の人材育成策を評価します。たしかに、「外交的・政治的に微妙なのだから、旧のまま放っとけ、あまり急に変えるな」という方針は政治的には老獪なのかもしれませんが、例えば辻遊郭に対する上杉県令が立てた規則を、遊郭側の苦情に応じて旧に復した結果が、笹森儀助の『南島探検』における指摘「成年男子の六割が梅毒に感染」し、「徴兵の予備検査をこころみたが徴兵適当者は百人中二、三人しかいなかった」(p.183)という惨状になってしまったのではないか。

歴史に「If〜」はなく、上杉県令の統治を美化するのも必ずしも正しいとは言えないのでしょうが、それにしても尾崎の妨害がなく、もう少し上杉県令の統治が続いていたらどうなっていたのだろうかとちらりと想像してしまいます。と同時に、やっぱり明治政府というのはある意味元テロリストの政権であり、本性というか、軍事的・強権的性格はここにも流れているのだな、と痛感させられます。