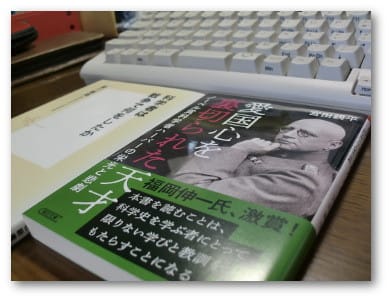
だいぶ前に購入していた朝日文庫で、宮田親平著『愛国心を裏切られた天才〜ノーベル賞科学者ハーバーの栄光と悲劇』を読み終えました。空中窒素を固定しアンモニアを合成するハーバー・ボッシュ法を開発した功績でノーベル賞を受賞した化学者ですが、夫の毒ガス研究を嫌って妻が自殺したというようなエピソードは断片的に承知しておりました。けれども、まとまった伝記的な書物は見たことがなく、たいへん興味深く読みました。
本書の構成は次のとおりです。
1868年にプロイセンのユダヤ系の両親のもとに生まれたフリッツ・ハーバーは、産後の不良のために生母を亡くし、勤勉な父と聡明な継母と兄たちからなる家族の中で育ちます。上昇機運にあった家業は染色業でしたので、自宅や織物倉庫を実験室として化学に親しみます。父ジークフリートはフリッツを取引関係のあった染料商に弟子入りさせますが、うまくいきません。叔父と継母の応援もあって、ベルリン大学へ、後にハイデルベルグ大学のブンゼンの下に学び、軍務についた後、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学に編入し、有機化学で学位を得ます。しかし、尊敬するオストワルドの下で研究をするという望みは叶わず、醸造会社や肥料会社に職を求め、実務経験を経た後に、スイスのチューリヒ工科大学を経て父の染料会社に入りますが、父子相克があきらかとなり、イエナ大学からカールスルーエ工科大学の無給助手として採用されることとなります。このあたりは、ユダヤ人の出自が不利に働いた面が強かったようで、キリスト教に改宗し、本物の「ドイツ人」として社会に溶け込もうとしたようです。
カールスルーエでは炭化水素の熱分解に関する実験的研究により物理化学的な解釈を行い、高い評価を受け注目を集めて、無給助手からようやく私講師の地位を得ることとなります。このあたりの経緯から、先生が弟子を推薦し道を開いてやるというような様子が見られず、おそらくハーバーは先生に可愛がられるタイプではなく、「一匹狼」に近い存在だったのではなかろうかと想像されます。その気質は、逆に独創的な発想を生み、本来の専門分野である有機化学に電気化学を結びつけて、ニトロベンゼンを電解還元しアニリンを製造するという技術的成果(*1)を生み出します。同時に、フライブルグで行われた学会で、かつて想いを寄せ、今は女性化学者となっていたクララ・インマーヴァーと再会し、同様にユダヤ系であった二人は結婚します。しかし、幸福な結婚生活も、長男ヘルマンの誕生と育児はクララの肩にのしかかり、夫フリッツは研究一筋の多忙な生活に追われるばかりで、妻自身の持つ化学者としての希望を助けようとしてはくれません。
19世紀末から20世紀の初頭、窒素肥料の欠乏は飢餓を招く重大な問題でした。多くの化学者が、水を分解して得られる水素と空気中の窒素とを原料としてアンモニアを合成する方法に取り組んでいましたが、当時は誰も成功していませんでした。原料としての水素と窒素は、生成物としてのアンモニアと平衡状態にあるとき、アンモニアの生成の方に平衡を移動させるにはどうするか? というのは、化学平衡に関する高校化学の代表的なテーマです。実は、ハーバーが取り組んだのはまさしくこの問題であり、温度、圧力、そして触媒というのが結論でした。実用化にはBASF社の技術者であるボッシュが引き継ぎ、鉄が触媒として優れていることを発見し、工業化を実現したため、現在はハーバー・ボッシュ法と呼ばれている、というわけです。
夫フリッツ・ハーバーは、アンモニア合成という花道を得て、カイザー・ウィルヘルム研究所の所長というポストに登り、ますます多忙な毎日を送りますが、妻クララは失意に沈み、家庭は崩壊の危機に至ります。何よりも、第一次世界大戦に際し、「早く戦争を終わらせるため」として夫が毒ガス戦の研究にのめり込んだことが、妻にはおそらく理解できなかったのでしょう。1915年5月、妻クララは抗議自殺します。
しかし、ベルリンの社交クラブの若い秘書で、同じくユダヤ系のシャルロッテを妻に迎え、ハーバーの毒ガス研究はやみません。塩素ガスやジホスゲンなどは防毒マスクで防御できますが、さらにイペリットの開発となると、皮膚に触れただけでびらん状態になるという凶悪さで、防毒マスクさえ無効になってしまいます。チューリヒ工科大学のシュタウジンガー教授等からハーバーの毒ガス研究が痛烈に批判される中でドイツは敗戦を迎え、ハーバーはスイスに逃亡しますが、1918年、アンモニア合成法の開発研究の業績で、ハーバーはノーベル化学賞を受賞、ドイツに復帰します。
両大戦の間の時期に、ハーバーはドイツ科学の再生に力を尽くしますが、ここでもシャルロッテとの間に不和を生じて離婚、反ユダヤ主義を掲げるナチス党の台頭によりユダヤ人の全追放が行われます。ドイツ化学工業界のトップであったボッシュはこれに反対し、「ユダヤ系の科学者を追放することは、ドイツから物理や化学を追放することである」と警告しますが、ヒトラーは「それならこれから百年、ドイツは物理も化学もなしにやっていこうではないか」と答えたそうな(p.218)。ハーバーは辞職し、国外追放となります。この後のドイツの歩む道は歴史が示すとおりですし、ハーバーもまた失意の道を歩みます。
◯
いやはや、これまでよく知らなかったハーバーの生涯が、具体的にわかりました。と同時に、合成の技術的な困難さの反面の、風向きにより「敵を倒すだけでなく味方にも犠牲を出してしまう」毒ガスという兵器の本質的愚かしさを感じます。二人の妻に去られる人間性は、仕事中毒により地位と権力を手にした一匹狼が、持ち前の組織力を活かし「傑出した科学的才能を大量殺戮のために使っている」(*2)ようなものだと思います。
『愛国心を裏切られた天才』という表題について、国を愛するという言葉もいささか漠然としているように思います。「国民」を愛することや「国土」を愛するということはすんなりと理解できますが、「国家機構」は無条件に愛するとは限らない。国民を迫害収奪し、国土を破壊するようなら、その国家機構は果たして愛するに値するのかどうか。同様に、ハーバーの愛国心は歪んでいなかったのかどうか。
(*1):ハーバーの業績など何も知らなかった若い頃、某高校でニトロベンゼンを入れたビーカー中で水の電気分解を行い、発生する水素でニトロベンゼンが還元されてアニリンができるかどうかを調べ、さらし粉が赤紫色に変化するのを確かめて喜んだ記憶があります。
(*2):アインシュタインがハーバーを批判した言葉だそうです。(p.159)
本書の構成は次のとおりです。
- 生い立ち
- 挫折と苦闘の日々
- 陽の当たる場所へ
- 空中窒素固定法の成功
- 家庭崩壊の兆し
- 毒ガス戦の先頭に立つ
- 死の抗議と第二のロマンス
- 敗戦と逃亡
- ノーベル賞、星基金、チクロンB
- 海水から金を採取せよ
- 日本訪問
- 報酬は国外追放
- 最愛の国家に裏切られて
エピローグ
プロローグ
1868年にプロイセンのユダヤ系の両親のもとに生まれたフリッツ・ハーバーは、産後の不良のために生母を亡くし、勤勉な父と聡明な継母と兄たちからなる家族の中で育ちます。上昇機運にあった家業は染色業でしたので、自宅や織物倉庫を実験室として化学に親しみます。父ジークフリートはフリッツを取引関係のあった染料商に弟子入りさせますが、うまくいきません。叔父と継母の応援もあって、ベルリン大学へ、後にハイデルベルグ大学のブンゼンの下に学び、軍務についた後、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学に編入し、有機化学で学位を得ます。しかし、尊敬するオストワルドの下で研究をするという望みは叶わず、醸造会社や肥料会社に職を求め、実務経験を経た後に、スイスのチューリヒ工科大学を経て父の染料会社に入りますが、父子相克があきらかとなり、イエナ大学からカールスルーエ工科大学の無給助手として採用されることとなります。このあたりは、ユダヤ人の出自が不利に働いた面が強かったようで、キリスト教に改宗し、本物の「ドイツ人」として社会に溶け込もうとしたようです。
カールスルーエでは炭化水素の熱分解に関する実験的研究により物理化学的な解釈を行い、高い評価を受け注目を集めて、無給助手からようやく私講師の地位を得ることとなります。このあたりの経緯から、先生が弟子を推薦し道を開いてやるというような様子が見られず、おそらくハーバーは先生に可愛がられるタイプではなく、「一匹狼」に近い存在だったのではなかろうかと想像されます。その気質は、逆に独創的な発想を生み、本来の専門分野である有機化学に電気化学を結びつけて、ニトロベンゼンを電解還元しアニリンを製造するという技術的成果(*1)を生み出します。同時に、フライブルグで行われた学会で、かつて想いを寄せ、今は女性化学者となっていたクララ・インマーヴァーと再会し、同様にユダヤ系であった二人は結婚します。しかし、幸福な結婚生活も、長男ヘルマンの誕生と育児はクララの肩にのしかかり、夫フリッツは研究一筋の多忙な生活に追われるばかりで、妻自身の持つ化学者としての希望を助けようとしてはくれません。
19世紀末から20世紀の初頭、窒素肥料の欠乏は飢餓を招く重大な問題でした。多くの化学者が、水を分解して得られる水素と空気中の窒素とを原料としてアンモニアを合成する方法に取り組んでいましたが、当時は誰も成功していませんでした。原料としての水素と窒素は、生成物としてのアンモニアと平衡状態にあるとき、アンモニアの生成の方に平衡を移動させるにはどうするか? というのは、化学平衡に関する高校化学の代表的なテーマです。実は、ハーバーが取り組んだのはまさしくこの問題であり、温度、圧力、そして触媒というのが結論でした。実用化にはBASF社の技術者であるボッシュが引き継ぎ、鉄が触媒として優れていることを発見し、工業化を実現したため、現在はハーバー・ボッシュ法と呼ばれている、というわけです。
夫フリッツ・ハーバーは、アンモニア合成という花道を得て、カイザー・ウィルヘルム研究所の所長というポストに登り、ますます多忙な毎日を送りますが、妻クララは失意に沈み、家庭は崩壊の危機に至ります。何よりも、第一次世界大戦に際し、「早く戦争を終わらせるため」として夫が毒ガス戦の研究にのめり込んだことが、妻にはおそらく理解できなかったのでしょう。1915年5月、妻クララは抗議自殺します。
しかし、ベルリンの社交クラブの若い秘書で、同じくユダヤ系のシャルロッテを妻に迎え、ハーバーの毒ガス研究はやみません。塩素ガスやジホスゲンなどは防毒マスクで防御できますが、さらにイペリットの開発となると、皮膚に触れただけでびらん状態になるという凶悪さで、防毒マスクさえ無効になってしまいます。チューリヒ工科大学のシュタウジンガー教授等からハーバーの毒ガス研究が痛烈に批判される中でドイツは敗戦を迎え、ハーバーはスイスに逃亡しますが、1918年、アンモニア合成法の開発研究の業績で、ハーバーはノーベル化学賞を受賞、ドイツに復帰します。
両大戦の間の時期に、ハーバーはドイツ科学の再生に力を尽くしますが、ここでもシャルロッテとの間に不和を生じて離婚、反ユダヤ主義を掲げるナチス党の台頭によりユダヤ人の全追放が行われます。ドイツ化学工業界のトップであったボッシュはこれに反対し、「ユダヤ系の科学者を追放することは、ドイツから物理や化学を追放することである」と警告しますが、ヒトラーは「それならこれから百年、ドイツは物理も化学もなしにやっていこうではないか」と答えたそうな(p.218)。ハーバーは辞職し、国外追放となります。この後のドイツの歩む道は歴史が示すとおりですし、ハーバーもまた失意の道を歩みます。
◯
いやはや、これまでよく知らなかったハーバーの生涯が、具体的にわかりました。と同時に、合成の技術的な困難さの反面の、風向きにより「敵を倒すだけでなく味方にも犠牲を出してしまう」毒ガスという兵器の本質的愚かしさを感じます。二人の妻に去られる人間性は、仕事中毒により地位と権力を手にした一匹狼が、持ち前の組織力を活かし「傑出した科学的才能を大量殺戮のために使っている」(*2)ようなものだと思います。
『愛国心を裏切られた天才』という表題について、国を愛するという言葉もいささか漠然としているように思います。「国民」を愛することや「国土」を愛するということはすんなりと理解できますが、「国家機構」は無条件に愛するとは限らない。国民を迫害収奪し、国土を破壊するようなら、その国家機構は果たして愛するに値するのかどうか。同様に、ハーバーの愛国心は歪んでいなかったのかどうか。
(*1):ハーバーの業績など何も知らなかった若い頃、某高校でニトロベンゼンを入れたビーカー中で水の電気分解を行い、発生する水素でニトロベンゼンが還元されてアニリンができるかどうかを調べ、さらし粉が赤紫色に変化するのを確かめて喜んだ記憶があります。
(*2):アインシュタインがハーバーを批判した言葉だそうです。(p.159)
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます