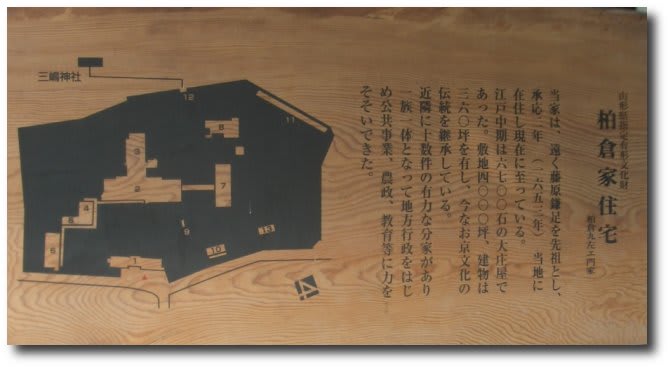極力オリジナル楽器を用い、ノン・ヴィヴラート奏法で一貫した、八年がかりのモーツァルト交響曲全曲演奏「アマデウスへの旅」、昨日は第5回目でした。仕事で出発が遅くなり、高速を飛ばしましたが間に合わず、会場の山形テルサホールに到着したら駐車場も満車です。しかたなくUターンして近隣の別の駐車場へ。一曲目の交響曲ヘ長調K.76は、途中から会場ロビーで聴きました。ロビーで事務局の方が休憩時に販売するCDの準備をしていましたが、11月末にオクタヴィア・レコード社から39番の交響曲ほかの新録音がCDとして発売予定とのことで、次の11月22日と23日の定期演奏会で先行発売しますとのことでした。指揮者の飯森範親さんの、恒例のプレトークは、どんな内容だったのでしょうか。
演奏が終わり、曲目の合間にようやく入場できた席は、ハープの内田奈織さんの横顔が間近に見える、右前方の位置でした。曲目は、「フルートとハープのための協奏曲」。ほどなく山響団員の皆さんが着席、曲目にあわせて、ぐっと編成をしぼったらしく、第1・第2ヴァイオリンとも第4プルトまで8名ずつで、この座席からはよく見えませんが、ヴィオラは4人かな?チェロの人数は数名で詳細不明、コントラバス、ホルンとオーボエが2本ずつ、といったところでしょうか。女性の団員は、モーツァルト定期らしく、皆さん色とりどりのドレス姿が多く、華やかです。
やがて本日のソリストが登場、内田奈織さんは、すらりとした長身に裾まわりに花模様を散らしたピンクのドレス、ハープの色に合わせた金色の靴で、たいへんチャーミングな方です。フルートの足達祥治さんは、山響の主席フルート奏者で、演奏会ではいつも素晴らしい音色を披露してくれています。今日も笑顔で余裕の表情ですが、内心は緊張しているのでしょうね。指揮者の飯森さん、指揮棒なしです。
第1楽章、アレグロ。演奏が始まると、足達さんのフルートの音色が美しい!この席では、ハープの音がよく聞こえます。ハープ奏者は、腕を伸ばして低弦まで指が届くかどうかを考えると、長身の人の方が有利なのでしょうか。ノン・ヴィヴラート奏法のオーケストラは、たいそう軽やかです。
第2楽章、アンダンティーノ。ふわっと優しい弦楽の響きに、透明感があります。フルートの音色によくマッチして、ゆったりしたテンポの、夢見るような音楽になっています。フルートとハープの対話が、エレガントに響き、透明感に魅了されました。
第3楽章、アレグロ。編成を小さくしたオーケストラが奏する間、ソロの2人は少しお休み。再びフルートとハープがリズミカルに参加するようになると、やっぱり音楽が華やかです。ナチュラルホルンが響き、コントラバスがベースを刻む中で、私の席から内田さんの髪飾りが光を反射して螺鈿細工のような多彩な色に光ります。ハープの音も、ギターのアルアイレのように乾いた音を出す奏法もあるのですね。
盛大な拍手に、二人のアンコール。車を飛ばして急いだ甲斐がありました!

写真は休憩時のステージの様子です。観客席は通路右側の最前列から三列ほど空席がありましたが、ステージ直前にもお客さんが陣取り、それ以外はほぼぎっしり満席のようでした。
休憩の後は、交響曲第36番「リンツ」です。飯森さんは、やっぱり指揮棒なし。腕と指で、表情豊かに指示します。編成は、弦5部に、木管がオーボエとファゴット2本ずつ、金管はナチュラルホルンとナチュラルトランペットが各2本、そしてバロック・ティンパニのようです。
第1楽章、荘重なアダージョから入り、アレグロへ。ヴァイオリンを左右に配した対向配置です。管楽器の音色も対比をくっきりとつけて、ティンパニも活躍、晴れやかで躍動的な音楽になっていきます。
第2楽章、アンダンテ。ティンパニとファゴットと低弦が刻むリズムが、しっかりした足取りを感じさせ、短調に転じてからファゴットと低弦かな?「ボポポポポポポッポッポー」。この森のフクロウのような動機が、パートを変えて繰り返し奏されます。おもしろい!
第3楽章、メヌエット。弦と木管とティンパニが活躍、トランペットやホルンは存在を主張しませんが、要所で音色の隠し味になっています。楽章の終わり、最後の消えゆく音が、本当に澄んでいます。
第4楽章、プレスト。ゲスト・コンサートマスター高木和弘さんを中心に、きわめて集中した緊張感に富むプレスト。なぐりがきのメモを取る手を休めて、思わず聴き入ってしまいました。
今回も堪能しました。演奏会後の交流会にも出たかったのですが、駐車料金の小銭が乏しく、急いで会場を出ました。テルサホールの駐車場なら百円玉数枚ですむのですが、一般の駐車場ですとその五割増以上は覚悟しなければなりません。ゲートを出るとき小銭入れを逆さに振って、ようやく間に合いました(^o^)/