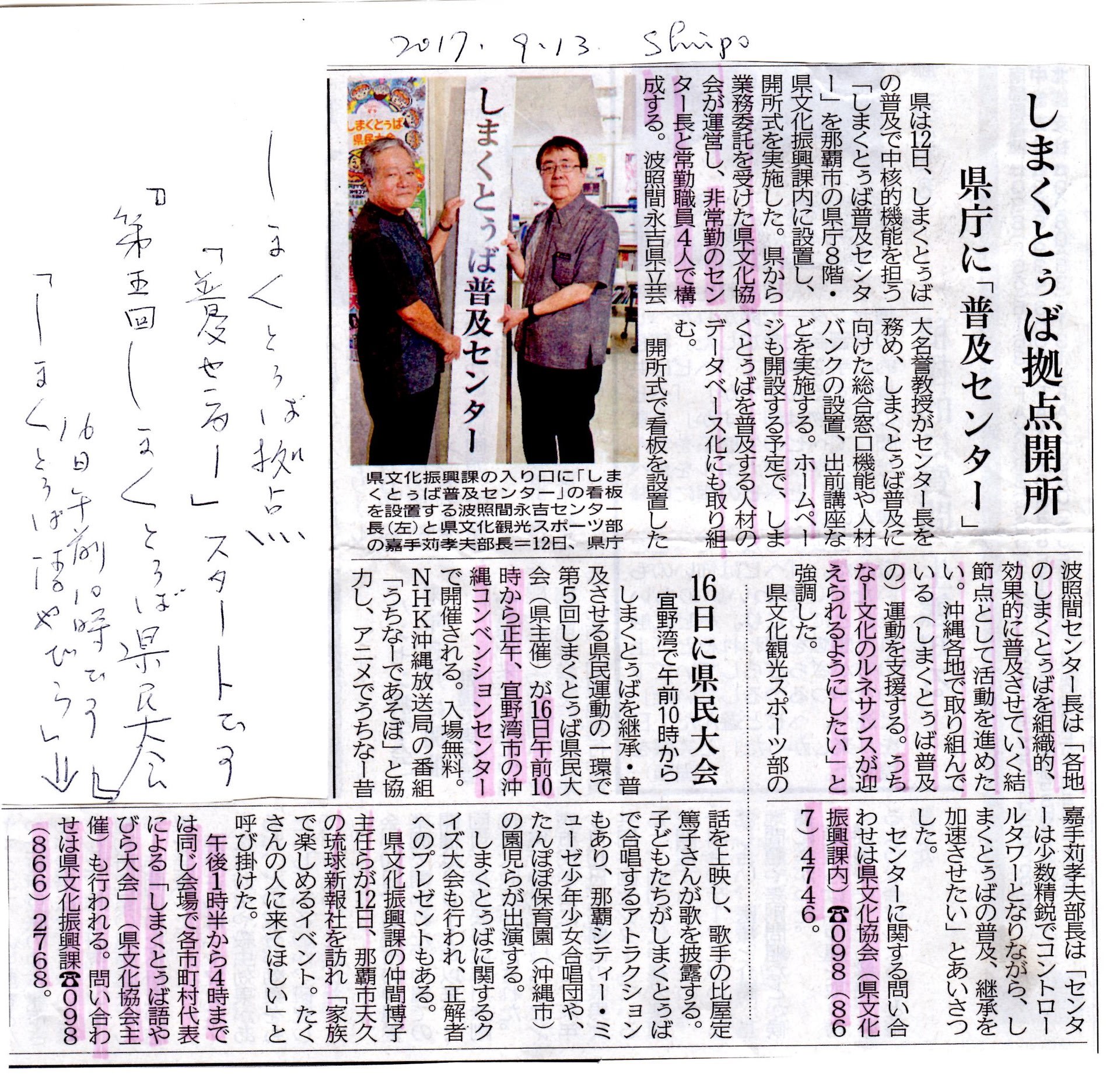
うちなー文化のルネサンスを!と新センター長の波照間先生です!氏は古謡研究者として評価が高い方です。幅広い知的人脈を持っている方ですので、適任かとも思います。でもなぜ言語専門の方がセンター長ではないのか、ちょっと気になりました。多言語研究会や危機言語研究会、琉球継承言語研究会もありますね。
組踊の詞章は「首里方言」と科目の概要に書かれた方ですので、気になります。世界的にエスニック&マイノリティー言語の権利が欧米は進んでいるので、そうした世界の動向にも視野の深い方がいいのではないのかと考えます。身近なアジアの多言語政策がどうなっているかも気になります。それはその分野の研究者がいますね。
先住民族への文化的収奪に関しても、その問題を先に取りあげたのは欧米でしたね。先住民の遺骨返還運動も今世紀冒頭から始まっていますね。沖縄は遅いですね。最近からです。先駆者の欧米、オーストラリアも新聞社は取材したらいいですね。このブログにも2010年だったかミュンヘンの国際学会の基調講演で取りあげられた先住民の文化収奪について紹介しています。内国植民地の沖縄人の人類学的研究の名目の元に遺骨が取り出された経緯は、詳細を京都大学は明らかにするべきですね。単に人骨研究と異なるスタンスが戦前あったとしても 比較人類学の大義名分があったにしても、地域共同体との関係・承諾関係がよく見えてきませんね。 植民地がトータルに収奪の対象になったことは事実ですね。



















